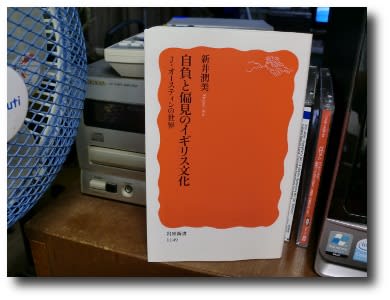岩波新書で、新井潤美著『自負と偏見のイギリス文化』を読みました。「J.オースティンの世界」という副題からもわかるように、『高慢と偏見』または『自負と偏見』という代表作を持つイギリスの作家オースティンの評伝及び作品論という性格を持つ、18世期末から19世紀初頭にかけてのイギリス社会を扱った本です。本書の構成は、次のようなものです。
オースティンの『高慢と偏見』は、たぶん学生時代に岩波文庫かなにかで一度読んだきりで、そのときはあまりピンと来なかったのだろうと思います。その後は、モノクロ映画の『高慢と偏見』を観ましたが、これはかなり記憶に残っています。解説本を先に読んでしまって原作が後になるなんて、本末転倒もはなはだしい状況ですが、実は活字のポイントが大きい(^o^;)光文社の古典新訳文庫にこのタイトルを見つけ、探している次第です。
○
イギリス社会における階級の意味は、東北農村の生活の中では、想像に難くありません。70年ほど前には、大地主~中小地主~自作農~小作農という歴然たる格差が存在していたわけで、縁組も似た階級どうしで行われていたようです。大地主階級になると、県内どこに行っても古い姻戚関係があることは珍しくありませんし、平成の現代にも、それぞれの家庭にかつての階級の残渣が残っていたりします。農地改革以後、テレビやマスメディアの影響もあり、かなり均質化してきているとはいうものの、それでも結婚生活の中で思いがけない波乱のタネになるものが実はかつての階級に由来するズレであったりするため、生まれや育ちを考慮に入れて、などと言い出す年寄りも。そんな話を聞くと、思わず『高慢と偏見』の世界にタイムスリップしたような錯覚を覚えます(^o^)/
第1章 オースティンは「お上品」ではない~奢侈と堕落の時代のヒロインたち
第2章 パロディから始まる恋愛小説~分別と多感のヒロインたち
第3章 恋愛と結婚~女性の死活問題
第4章 アッパー・ミドル・クラスのこだわり
第5章 オースティンと現代~空前のブームの背景
オースティンの『高慢と偏見』は、たぶん学生時代に岩波文庫かなにかで一度読んだきりで、そのときはあまりピンと来なかったのだろうと思います。その後は、モノクロ映画の『高慢と偏見』を観ましたが、これはかなり記憶に残っています。解説本を先に読んでしまって原作が後になるなんて、本末転倒もはなはだしい状況ですが、実は活字のポイントが大きい(^o^;)光文社の古典新訳文庫にこのタイトルを見つけ、探している次第です。
○
イギリス社会における階級の意味は、東北農村の生活の中では、想像に難くありません。70年ほど前には、大地主~中小地主~自作農~小作農という歴然たる格差が存在していたわけで、縁組も似た階級どうしで行われていたようです。大地主階級になると、県内どこに行っても古い姻戚関係があることは珍しくありませんし、平成の現代にも、それぞれの家庭にかつての階級の残渣が残っていたりします。農地改革以後、テレビやマスメディアの影響もあり、かなり均質化してきているとはいうものの、それでも結婚生活の中で思いがけない波乱のタネになるものが実はかつての階級に由来するズレであったりするため、生まれや育ちを考慮に入れて、などと言い出す年寄りも。そんな話を聞くと、思わず『高慢と偏見』の世界にタイムスリップしたような錯覚を覚えます(^o^)/