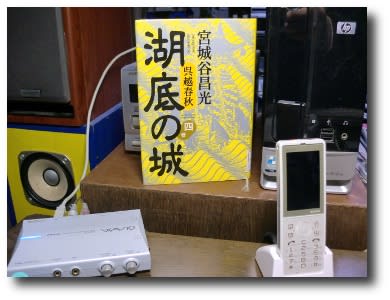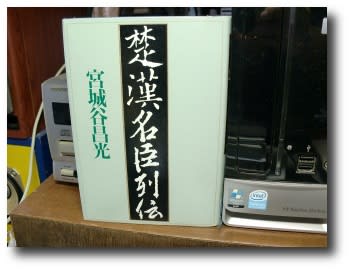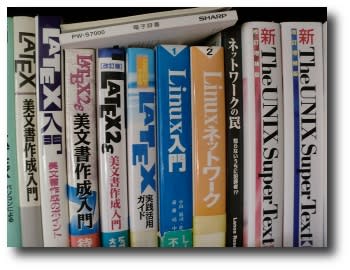真冬の連休の最終日、成人の日に、山形市の文翔館議場ホールにて、山形弦楽四重奏団第50回定期演奏会を聴きました。現在の山形弦楽四重奏団は、四人のメンバーがいずれも山形交響楽団の奏者で、オーケストラの仕事のかたわら室内楽の活動を続けている常設の弦楽四重奏団であり、こうした例は全国的にも珍しいものだそうです。年に四回の定期演奏会を開催して十三年目に入り、ついに今回は第50回目を迎えたという記念の演奏会。私はたしか第23回の佐藤敏直作品を取り上げたあたりから聴いているはずなので、半分くらいは聴いていることになります。当ブログの「室内楽」カテゴリーが突出して多いのも、このナマの演奏会の存在が大きいと感じます。
さて、夕食を済ませて会場に入ると、もうプレコンサートが始まっておりました。今回は、黒瀬美さんのヴァイオリンと田中知子さんのヴィオラで、シュターミッツの「ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲Op.18の3?」だそうです。シュターミッツらしく、優雅でなかなかすてきな曲でした。
そしてプレトークはヴィオラの倉田譲さん。とくに、ベートーヴェンの「古典還り」という解釈の妥当性についての話が興味深かった。要するに、中~後期の重厚な曲を作曲した後に、再び古典派のハイドンやモーツァルトの作品を見直し、新たに取り入れて、自分の作風の変化を意図していたのではないか、という考え方です。「重厚長大こそベートーヴェンの本領で総決算」という見方からは、なおも変化しつづけようとしていたベートーヴェンという視点は生まれにくいものですが、そのように考えれば、なるほどと理解できます。
第1曲、ハイドンの弦楽四重奏曲ト長調 Op.54-1、いわゆる第1トスト四重奏曲の一つらしい。当方、この曲はCDも持たず、初体験です。第1楽章:アレグロ・コン・ブリオ。活気ある明るい音楽。第2楽章:アレグレット。二つのヴァイオリンと、ヴィオラ・チェロとが、互いに対比したり合奏したりという趣向か。第3楽章:メヌエット。チェロが珍しくソロ的に活躍します。こういう例はあまり多くないのでは。第4楽章:フィナーレ、プレスト。軽やかで楽しいプレスト。最後もごく軽く終わります。ハイドンらしい晴れやかな音楽で、第50回目の演奏会のオープニングにふさわしい曲でした。
続いて第2曲めは、山田耕筰の弦楽四重奏曲第2番、ト長調。
単一楽章だけの曲です。アダージョ~アレグロ・モルト。ヴィオラとチェロから始まり、これにヴァイオリンが加わる形の出だしです。歌謡的な旋律が続き、なるほど山田耕筰らしい、フレッシュな佳曲でした。
ここで15分の休憩です。

後半は、第3曲目のベートーヴェン、弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調、Op.130 です。第1楽章:アダージョ・マ・ノン・トロッポ~アレグロ。ゆっくりと始まります。充実した響きです。この曲は、難曲だからというだけではなく、きっと奏者を没入させてしまうようなものがあるのでしょう。第2楽章:プレスト。暗めの色調で速いテンポの曲です。第3楽章:前の楽章と似た主題から、一転して田舎の散歩ふうな歩みに。途中、ピツィカートも。第4楽章:アレグロ・アッサイ。Alla Danza tedesca は、「~のように、舞曲」の意味らしいとはわかりますが、最後のがわかりませんでしたので、ネットで調べたら(*1)「ドイツの」という意味だそうな。すると、意味は「ドイツ舞曲風に」でしょうか。たしかに、ベートーヴェン風な味付けですが、軽やかな舞曲のような音楽です。第5楽章:カヴァティーナ:アダージョ・モルト・エスプレッシーヴォ。瞑想的というのか思索的というのか、とてもステキな緩徐楽章。酒飲みで不器用な中年男ベートーヴェンの優しさが伝わり、ごく静かに終わります。第6楽章:アレグロ。ここは「大フーガ」ではなく、改訂した方の終楽章を採用。なるほど、「古典還り」と言われるだけのことはあります。けれど、チェロの役割の大きさや、四人の奏者の緊密な集中の度合いは格別で、ハイドンの時代のおおらかな気分とは違います。やっぱりベートーヴェンの迫力はあり、充分に満足です。
アンコールは、山田耕筰の「赤とんぼ」を弦楽四重奏で。「15でねえやは嫁にいき~、お里の便りも絶え果てた~」、うーん、やっぱりいいですね~。
次回の第51回定期演奏会は、4月、担当:中島、とまでは決まっているそうですが、山形交響楽団のスケジュールが決まるまで、まだ日取りの確定はできないそうです。これはしかたがないでしょう。曲目はすでに決まっていて、山響の「アマデウスへの旅」完結年にちなみ、モーツァルトのハイドンセット全曲を二回に分けて全曲演奏する予定、とのことです。こちらも楽しみです。
議場ホールを出て、文翔館駐車場へ向かう途中の冬景色を見ながら、まだ高校生だった頃に、県民会館で巌本真理弦楽四重奏団の演奏会が開かれ、まさにベートーヴェンの弦楽四重奏曲が取り上げられていた(*2)ことを思い出してしまいました。あれから45年、同じ山形で、このような形で聴くことができることを、嬉しく感慨深く思います。
(*1):
Tedesca 日本語・イタリア語 翻訳辞書
(*2):
巌本真理弦楽四重奏団と山形~「電網郊外散歩道」2008年3月