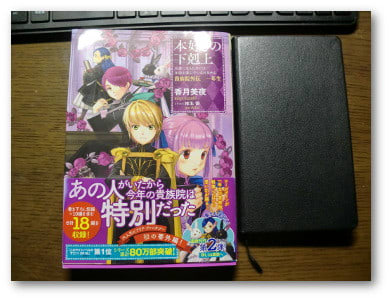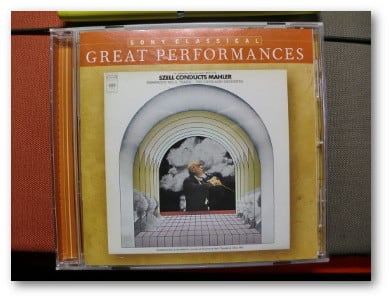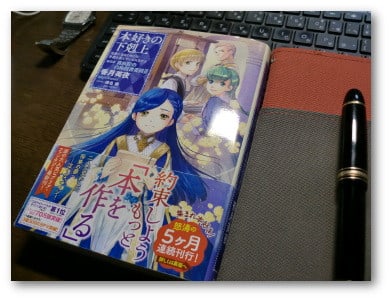当方、長年コクヨの野帳に給油記録を残しております(*1)が、最近はDPF再生の間隔も記録するようにしました。野帳の見開きで左頁と右頁の記入項目は、
という具合です。
この記録を見ると、2月にスス対策のリコールを実施して以降、DPF再生の間隔は、400km→300km→200km台 と低下していたのが、この11月末と12月上旬の長距離往復ドライブの後の状況は、400km 台になりました。
この DPF 再生の間隔はどのように記録しているかというと、リアルタイム燃費表示を参考に、iSTOP(アイドリング・ストップ) の表示が消え、かつ10分以上連続して極端に燃費が低い値を示す状態から、再び iSTOP 表示が点灯した時にトリップメーター(B)をリセットし、前回のリセットから今回のリセットまでの走行キロ数を読み取る、というやり方です。おそらく、DPF 再生の間隔をかなり精確に表しているものと考えます。
一定の速度でたんたんと走り続ける走行条件では、あまりディーゼル・パーティクル(スス)も発生せず、DPF 再生に頼る量も少ないのではないか。逆に、負荷がかかるチョイ乗りが繰り返されるような走行条件では、ススもたまりやすいのではなかろうか。
(*1):コクヨの野帳で車の燃費と整備を管理する〜「電網郊外散歩道」2012年2月
(左頁) 月/日 積算距離(km) 走行距離(km) 給油量(L) 支払額(円) 燃料消費率(km/L) 単価(円)
(右頁) DPF再生間隔(km) 給油時表示燃費(km/L) 給油SS
という具合です。
この記録を見ると、2月にスス対策のリコールを実施して以降、DPF再生の間隔は、400km→300km→200km台 と低下していたのが、この11月末と12月上旬の長距離往復ドライブの後の状況は、400km 台になりました。
この DPF 再生の間隔はどのように記録しているかというと、リアルタイム燃費表示を参考に、iSTOP(アイドリング・ストップ) の表示が消え、かつ10分以上連続して極端に燃費が低い値を示す状態から、再び iSTOP 表示が点灯した時にトリップメーター(B)をリセットし、前回のリセットから今回のリセットまでの走行キロ数を読み取る、というやり方です。おそらく、DPF 再生の間隔をかなり精確に表しているものと考えます。
一定の速度でたんたんと走り続ける走行条件では、あまりディーゼル・パーティクル(スス)も発生せず、DPF 再生に頼る量も少ないのではないか。逆に、負荷がかかるチョイ乗りが繰り返されるような走行条件では、ススもたまりやすいのではなかろうか。
(*1):コクヨの野帳で車の燃費と整備を管理する〜「電網郊外散歩道」2012年2月