
震災被災地の小学校入学児童に匿名でランドセルを届けたり、祖父母や親戚のお祝いで頂くランドセルは6年間使っても形が崩れず、ミニにして保存し思い出にしてとプレゼントする方もおられる。丈夫な革製品で多方面への再利用もされている。
幕末の幕府が洋式陸軍導入の際、将兵の携行品を収納する装備品としてオランダからもたらされた背嚢(ransel)ランセルの発音が訛りランドセルになったと広辞苑第四版に載っている。明治以降も帝国陸軍では歩兵や下士官以下の革製背嚢が採用された。
明治18年(1885)に、学習院初等科で教育現場の平等から馬車や人力車での通学を禁止、通学用としてリックサックのような背嚢に学習用品を収納し通学すように規則を改めた。1887年昭和天皇が皇太子として、学習院初等科に入学する際、伊藤博文がお祝いとして特注で作らせ献上したものが、現在の箱型ランドセルの始まりであるという。
暫くこのランドセルは学習院の指定品だったが、業者が学習院に許可を得て市販すると富裕層の子弟から広まった。しかし、一般の子弟は風呂敷や安価なショルダーに入れて通学していた。昭和30年代に入ってようやく全国に広まった。
現在のランドセルは人工の皮革や牛革が普通で6年間持つ丈夫なものであるが、過去にはブタやサメ、アザラシの皮を利用したこともあったようだ。頂いたランドセルを大切に使って欲しいが、それを学童に押し付けることなく、そーと暖かく見守ることが大人の努めでもある。
幕末の幕府が洋式陸軍導入の際、将兵の携行品を収納する装備品としてオランダからもたらされた背嚢(ransel)ランセルの発音が訛りランドセルになったと広辞苑第四版に載っている。明治以降も帝国陸軍では歩兵や下士官以下の革製背嚢が採用された。
明治18年(1885)に、学習院初等科で教育現場の平等から馬車や人力車での通学を禁止、通学用としてリックサックのような背嚢に学習用品を収納し通学すように規則を改めた。1887年昭和天皇が皇太子として、学習院初等科に入学する際、伊藤博文がお祝いとして特注で作らせ献上したものが、現在の箱型ランドセルの始まりであるという。
暫くこのランドセルは学習院の指定品だったが、業者が学習院に許可を得て市販すると富裕層の子弟から広まった。しかし、一般の子弟は風呂敷や安価なショルダーに入れて通学していた。昭和30年代に入ってようやく全国に広まった。
現在のランドセルは人工の皮革や牛革が普通で6年間持つ丈夫なものであるが、過去にはブタやサメ、アザラシの皮を利用したこともあったようだ。頂いたランドセルを大切に使って欲しいが、それを学童に押し付けることなく、そーと暖かく見守ることが大人の努めでもある。














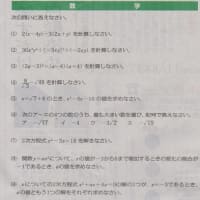


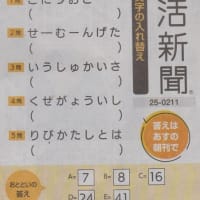


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます