「ふと思い立って浅草 #1」のつづきです。
昨夜のニュース を視ていると、毎年5月に行われている三社祭が、コロナ禍
を視ていると、毎年5月に行われている三社祭が、コロナ禍 の影響を受けて、大幅に規模を縮小
の影響を受けて、大幅に規模を縮小 して先週末に行われたと伝えていました。
して先週末に行われたと伝えていました。
私は、翌週末に三社祭が行われるともつゆ知らず 、浅草寺に続いて、浅草神社にお参りしました。
、浅草寺に続いて、浅草神社にお参りしました。
老婆心ながら書いておきますと、浅草寺は「せんそうじ」と読みますが、浅草神社は「あさくさじんじゃ」と読みます。
それはさておき、浅草神社の由来書き を転記
を転記 しましょう。
しましょう。
明治初年の文書によると、祭神は土師真中知命(はじのまつちのみこと)・桧前浜成命(ひのくまのはまなりのみこと)・桧前竹成命(ひのくまのたけなりのみこと)・東照宮である。浜成と竹成は隅田川で漁猟中、浅草寺本尊の観音像を網で拾い上げた人物、真中知はその像の奉安者といわれている。三神を祀る神社なので、「三社様」と呼ばれた。しかし鎮座年代は不詳。東照宮は権現様すなわち徳川家康のことで、慶安2年(1649)に合祀された。以来、三社大権現といい、明治元年(1868)三社明神、同6年浅草神社と改称した。
だそうです。 浅草神社の神紋の「三網」は、由来そのままの意匠なんですな。
浅草神社の神紋の「三網」は、由来そのままの意匠なんですな。
由緒書きは、更に社殿についても触れていまして、
現在の社殿は慶安2年12月、徳川家光が再建したもの。建築様式は、本殿と拝殿との間に「石の間」(弊殿・相の間ともいう)を設け、屋根の棟数の多いことを特徴とする権現造。この社殿は江戸時代初期の代表的権現造として評価が高く、国の重要文化財に指定されている。
とな。
浅草寺の方は、約10万人 が亡くなった1945年3月10日の東京大空襲のため、関東大震災にも耐えた本堂や五重塔が焼失したのに、すぐ隣の浅草神社は無事だったんだ…
が亡くなった1945年3月10日の東京大空襲のため、関東大震災にも耐えた本堂や五重塔が焼失したのに、すぐ隣の浅草神社は無事だったんだ…
塀や樹木越しに、本殿を拝見…
拝殿は瓦葺きだけど、本殿は銅板葺きなんですな。
「三つ葉葵」の紋が輝いています。
で、もう一枚 、裏側から…
、裏側から…
この本殿の裏にあるお家 の表札からググる
の表札からググる と、こちらのサイトにこんな話が出てきました。
と、こちらのサイトにこんな話が出てきました。
慶応3年徳川幕府の大政奉還となり、翌慶応4年(明治元年)3月28日神仏分離の令が下され、太政官布告により、神社と神職は神祇官の直属となり、社僧、別当は復飾(還俗)を命じられ、神仏混淆が禁じられたのである。
これまで三社大権現に祀られた土師中知、檜前浜成、竹成の子孫は三譜代と称して、観音堂に使えていたが、神仏分離で誰か一人は復飾して三社の祭典に専従しなければならなくなった。三家とも千余年の間観音に仕えてきたのに、いまさら復飾させられるのは迷惑だったので、檜前斎頭の倅相模を復飾させることを願い出たが認められず、斎頭も常音も復飾を拒否したので、やむなく土師専堂が復飾に応じて、三社の神官となり土師内膳と称した。
そして、現在の宮司さん は、「土師氏62代に当たる」のだとか…
は、「土師氏62代に当たる」のだとか…
「神仏分離」 は、明治政府の思いつき
は、明治政府の思いつき で行われたものではなさそうですが、日本の文化・風俗の一部を破壊
で行われたものではなさそうですが、日本の文化・風俗の一部を破壊 した事実は厳然としています
した事実は厳然としています

浅草神社にお参りしたあと、浅草寺本堂の裏手を通り、九代目市川團十郎の銅像(「暫」の鎌倉権五郎)を見物 し、
し、
この日は日曜日で、競馬開催日 だったのですが、WINS浅草に出入りする人はホント、少なかった。
だったのですが、WINS浅草に出入りする人はホント、少なかった。
六区ブロードウェイも人通りが少ないし、まだまだコロナ禍のさなかなんだな…
と、WINS浅草の駐輪場 に、G1レース
に、G1レース の優勝肩掛けが飾られているのを見つけました
の優勝肩掛けが飾られているのを見つけました
え" ホンモノ
ホンモノ
と、思いましたが、既に終わったレースのもあって、なぁ~んだ、レプリカか…  でした
でした
WINS浅草の前に、「瓢箪池と凌雲閣(十二階)」の説明板がありました。
瓢箪池、この池は浅草場外発売所や東宝映画などの建ち並んでいるところにあった。明治17年(1884)に浅草寺境内にあった奥山の見世物小屋などを現在の六区に移転させる計画のもとに、浅草田圃(この辺一帯)の一部を掘って池をつくり、その土で六区を造成した。大池が正式の名であるが瓢箪池の愛称で呼ばれ親しまれていた。池の広さは1820余坪あり、池の中央に中の島があって藤棚や茶店が憩いの場となり東西を橋でつないであった。夜ともなれば池面に興業街を彩るイルミネーションが浅草の灯をうつして美観を呈した。
当時の浅草公園にはあらゆる階級の人間が集り、人間の生の息吹が渦巻いていた。瓢箪池は青春の思い出であり、人生哀歓のオアシスであり、夢の泉でもあった。
凌雲閣、通称十二階の名で知られ、明治23年(1890)に浅草の空に聳え立った日本最高の凌雲閣は、東京市民驚嘆の的であった。凌雲閣は今の浅草東映から西北約50mの地点にあった。(浅草公園五区、千束2丁目38番地) 設計者はイギリス人WKバートン氏。高さ約60m、1階から10階までが煉瓦積みで、11階と12階それに屋根は木造であった。八角形の塔状で8階まで日本最初の昇降装置があり、明治23年11月10日に開業した。
浅草の文明開化の金字塔であった東京名物凌雲閣も、大正12年(1923) 9月1日の関東大震災で8階から二つに折れ取りこわされてしまった。
池なんて気配もないし、凌雲閣も、その存在は知っているものの、浅草のどこにあったのか判りません。
「今の浅草東映から西北約50mの地点」と言われても、浅草東映も既にない…
帰宅してから、蔵書の江戸東京博物館の図録「図表でみる江戸東京」 を見ると、載っていました
を見ると、載っていました 、関東大震災直前の1921年の地図
、関東大震災直前の1921年の地図
へぇ~
現在は、、といいますと、
 WINS浅草のあるブロックとその南のブロックが瓢箪池の跡で、凌雲閣跡はパチンコ屋など(パチンコ屋は閉店??)になっているようです。
WINS浅草のあるブロックとその南のブロックが瓢箪池の跡で、凌雲閣跡はパチンコ屋など(パチンコ屋は閉店??)になっているようです。
そして、Googleマップを拡大していくと、
「凌雲閣記念碑」があるではありませんか
しかも、何も知らない私は、その記念碑に気づくこともなく、その数m先を通り過ぎていた
ありゃぁ~~ と、ストリートビュー
と、ストリートビュー を見ると、、、
を見ると、、、
へ????
記念碑って、この小さなパネル?
と、一喜一憂しているところで、#3につづきます。
 つづき:2020/10/21 ふと思い立って浅草 #3
つづき:2020/10/21 ふと思い立って浅草 #3




















 、ふと思い立って
、ふと思い立って
 ⇒
⇒

 、、、、
、、、、



 がメインのお店だと、今のように
がメインのお店だと、今のように





 されたもので、
されたもので、













 したもの。
したもの。









 も
も














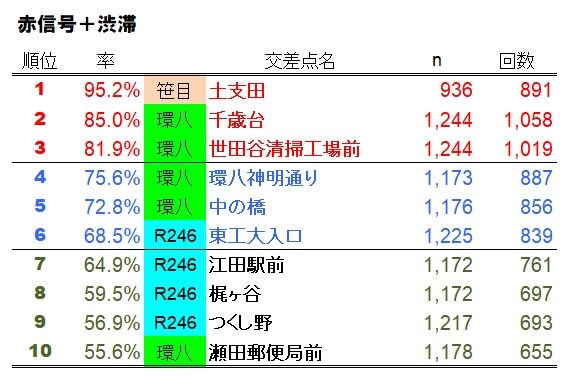













































 一見、
一見、















 ・
・









 です
です




















