きのうの記事「日本でも『曜日』を昔から使っていたらしい」は、なんとかきのうのうちにアップしたくて、シンデレラ気分でドタバタ と書きました(記事のタイムスタンプ
と書きました(記事のタイムスタンプ は23:58
は23:58 )。
)。
そんなことから、読み返すと、かなり手抜きっつうか、説明不足が目につきます
このブログでよく使っている「追記」にしようかとも思いましたが、ちょいと長くなりそうですので、稿を改めました。
きのうの記事で書けなかったことは、
1)古代欧州での惑星命名の由来
2)惑星の名前と五行思想との関係
3)なぜ「一週間」は7日なのか
4)「肉眼で見える太陽系の星7個を、地球から遠い順番に並べる」と、なぜ「土星⇒木星⇒火星⇒太陽⇒金星⇒水星⇒月」なのか
5)4)の配列を「24毎(=24時間毎)に改行していくと、各行の先頭が『土⇒太陽(日)⇒月⇒火⇒水⇒木⇒金』になる」とはどういうことか
6)日本語、英語以外での「曜日」の呼び名
といったところ。

それでは始めましょう。
1)欧州での惑星命名の由来
2)惑星の名前と五行思想との関係
については、国立科学博物館(科博)のサイトに判りやすい説明が載っていました。
まず、1)は、
水星は太陽のまわりをめまぐるしく動くことで、伝令の神マーキュリー。金星は明けの明星・宵の明星としてとても美しく、美の女神ビーナス。火星は赤く不気味な輝きから、戦争の神マース。木星はそのどっしりと落ち着いた輝きにたいし、神々の王者ジュピター。土星はそのくすんだ黄色の光に、土と農耕の神サターン、と名づけられました。
望遠鏡時代になって発見された惑星にも同様に神々の名がつけられました。天王星はその青い色に、天空の神ウラヌス。海王星も青い色から、海の神ネプチューン。準惑星となった冥王星は太陽系の果ての天体として、冥界の神プルート、というようにです。
と説明されています。
「『惑星』を楽しむ」で書いたホルストの組曲「惑星」の各曲は、まさしくこの説明どおりのイメージですな。
また、2)については、
(中国で)古代から知られた五惑星も五行説に都合がよく、要素が割り当てられました。中国名で辰星ともよばれる水星は太陽のまわりをめまぐるしく動くので水の要素の星。太白ともよぶ金星は明るく白く光るので金の要素。螢惑ともよぶ火星は赤い色の火の要素。木星と土星は、よりくすんだ黄色の方が土の要素の土星。残った木の要素を木星に割り当てました。木星はまた中国名では歳星、土星は鎮星ともよびます。
天王星・海王星・冥王星の三つは神々の名前を訳したものです。
惑星の動きや色で名付けるやり方は東西相通じるところが多い点が興味深い
それと共に、格段に大きく見える太陽 と月
と月 は別として、水星・金星・火星・木星・土星の5惑星を特別扱いするとは、古代ギリシア人も古代中国人もたいしたものだと思います。
は別として、水星・金星・火星・木星・土星の5惑星を特別扱いするとは、古代ギリシア人も古代中国人もたいしたものだと思います。
しっかりと天体を観測していたんですなぁ~。

3)なぜ「一週間」は7日なのか
なんとも根本的な疑問でして、その答は、この手の疑問にはつきものの「確固とした解明はなされていない」というもの
称えられている説には、①月の満ち欠け(周期:約29.53日)を四等分した、②惑星(太陽・月を含む)の数に合わせた、③旧約聖書「創世記」の「神が6日かけて世界をつくり7日目に休んだ」との記述、④ロシア民謡「一週間」から採られた といったものがあるようです。
といったものがあるようです。
私の感覚としては、①と②の合わせ技のような気がします。
「7日毎に区切りがあったら便利なんだけど…。そういえば、惑星は7つある きっと「7」という数字には霊力があるんだ みたいな…
きっと「7」という数字には霊力があるんだ みたいな…
結論が出なくて申しわけありませぬ。

4)「肉眼で見える太陽系の星7個を、地球から遠い順番に並べる」と、なぜ「土星⇒木星⇒火星⇒太陽⇒金星⇒水星⇒月」なのか
 彗星や流れ星を除けば、この7つの星だけが空で妙な動きをしています(だから「惑星」)。
彗星や流れ星を除けば、この7つの星だけが空で妙な動きをしています(だから「惑星」)。
古代ギリシア人の多くは、地球を中心にした天球があり、天球そのものが動くと共に、天球と地球の間では太陽・月を含む惑星が動いていると考えていたようです(天動説)。そして、動くスピードが速い惑星ほど地球に近いと考え、右図のように、地球から天球に向かって、
月⇒水星⇒金星⇒太陽⇒火星⇒木星⇒土星
の順にならんで、地球を中心にした同心円運動をしていると考えたのだそうな。
ところが、このモデルでは、惑星が妙に動く(逆行など)理由を説明できません。
 古代ローマの偉大な学者・プトレマイオスは綿密な観測と思考の末、「惑星の軌道上にさらに半径の小さな円を描き、惑星はこの上を円運動しながら、その小さな円そのものが地球のまわりを回るという軌道の二重構造を導入」しました。
古代ローマの偉大な学者・プトレマイオスは綿密な観測と思考の末、「惑星の軌道上にさらに半径の小さな円を描き、惑星はこの上を円運動しながら、その小さな円そのものが地球のまわりを回るという軌道の二重構造を導入」しました。
このプトレマイオスの宇宙観は、その後1400年間 にわたって「定説
にわたって「定説 」であり続けたのですから、かなりたいしたものだと思います。
」であり続けたのですから、かなりたいしたものだと思います。
この理論でかなりの部分まで現象を説明できる、こりゃ思いついた人にとって快感以外の何ものではないことでしょう。
ここで「脚注」を。上に載せた宇宙モデルの図はこちらのサイトから拝借しました。
また、「逆行」の仕組みは、こちらのサイトの動画が判りやすいと思いました。

5)4)の配列を「24毎(=24時間毎)に改行していくと、各行の先頭が『土⇒太陽(日)⇒月⇒火⇒水⇒木⇒金』になる」とはどういうことか
asahi.comの子ども向け科学コラム「ののちゃんのDO科学」の「曜日の順番はどう決めたの」では、
◆先生 ここからちょっと難しくなるからよく聞いてね。惑星たちはこの順番で1時間ごとに世の中を支配すると思われていたの。最初の日の最初の1時間目は土星が支配する時間で、次の1時間は木星の時間という順番ね。このまま1時間ごとに惑星を当てはめていくと、25番目となる次の日の1時間目は太陽に当たるわけ。この順で行くと、その次の日の1時間目の星は何になるか分かる?
◇ののちゃん ええとね、ええとね、指で数えるとね、ああ分かった、月だ。
◆先生 そう、月で正解。最初の日の1時間目を支配するのが土星、そして次の日の1時間目が太陽、その次の日は月という順番になるでしょ。ほら、土、日、月と曜日の順番になった!このようにその日の1時間目を支配する惑星がその日を代表する星だと考えられていたため、その惑星の名前がそのまま曜日の名前となったというわけね。
◇ののちゃん こんなことを決めたのは誰なの?
◆先生 ローマ時代の歴史書の中でこの曜日の並び方を紹介したカシウスという歴史家によると、最初に曜日を使ったのはエジプト人だそうよ。でもメソポタミア人だという説もあるわ。
と説明されています。
なるほどねぇ~ 、、、なのですが、1日が24時間となったのはいつ? 1時間はどうやって決めた?計った? という新たな疑問がわいてきます
、、、なのですが、1日が24時間となったのはいつ? 1時間はどうやって決めた?計った? という新たな疑問がわいてきます
学研の子ども向けHPによれば、
大昔、人間は月を見てカレンダーを作りました。月は満ちたり欠けたりしながら、30日ほどでもとにもどります。つまり、1か月が約30日というのは、月を見てカレンダーを作った大昔の人の考えが残っているからです。
また、30日ほどで1周期のみちかけをくり返す月が、この周期を12回くり返すと約1年になります。大昔の人は、この月の満ち欠けが12回くり返すと1年になるということをちゃんと知っていたのです。したがって、この12という数字は、ものごとの区切りとして、とても大切なものとされていたのです。
それで、1日をいくつに分けるか、つまり時こくを決めるとき、この12という数字が使われました。これは、昔メソポタミアという所に住んでいた人たちによって、最初に決められました。
ところが、エジプトに住んでいた人たちは、1日を夜と昼に分けて、それぞれを12に分ける方法をとったのです。すると昼は12時間、夜も12時間で、1日は合計24時間ということになります。ここで24という数字がでてきて、1日は24時間となったわけです。
現在も1日24時間なのは、この大昔のエジプト人が考えた方法がずっと使われてきたからなのです。
これまた壮大な歴史があるんですなぁ
ちなみに、古代エジプト人が始めた「昼12時間、夜12時間」は、やがて「1日24時間」(定時法)に変わったとな。
また、1時間の長さは、水時計 を使って、日の出
を使って、日の出 から翌日の日の出
から翌日の日の出 までを計時
までを計時 して、それを24で割って計りだしたそうです。
して、それを24で割って計りだしたそうです。

6)日本語、英語以外での「曜日」の呼び名
もうずいぶん前のこと、中国出張したとき、中国では曜日を数字で表記していることを初めて知りました(ホテル のエレベーターのカーペットが日替わりで曜日を示していたりした)。
のエレベーターのカーペットが日替わりで曜日を示していたりした)。
日:星期日、月:星期一、火:星期二……土:星期六
ってな具合。
こちらのサイトによりますと、中国のほか、スラブ/アラブも「数字表記」派で、驚くことに、惑星由来の元祖 、ギリシャが「数字表記」派に寝返っているではありませんか
、ギリシャが「数字表記」派に寝返っているではありませんか
1300年の昔、西方からシルクロードを通って伝わった宝物 が、正倉院にたどり着いて、大切に保管されています。
が、正倉院にたどり着いて、大切に保管されています。
なんだかそれと似たような話に思えてきます。
日本でも、残念ながら「月」の一般的な呼び名は数字になってしまいましたが、それでも「睦月」「如月」「弥生」「卯月」「皐月」「水無月」「葉月」「文月」「長月」「神無月」「霜月」「師走」という太陰暦で使われた和名もたまに使われています。
こういうのは大事にしたいものだと思う私です。
ちなみに、「水無月」「神無月」の「無」は、「無い」ではなく「の」という意味らしい。
つまり、「水無月=水の月」「神無月=神の月」となります。
これで「梅雨時 なのにどうして『水無月』だ?」という疑問も解けますでしょ
なのにどうして『水無月』だ?」という疑問も解けますでしょ

 だし、きょうのブログネタもハシゴはずし状態です
だし、きょうのブログネタもハシゴはずし状態です
 、と、ネットをさまよっていると、こんなサイトに行き当たりました
、と、ネットをさまよっていると、こんなサイトに行き当たりました
 です
です
 OPENING賞」に輝いたTHE TOUR OF MISIA 2005 THE SINGER SHOWから「K.I.T」のビデオ
OPENING賞」に輝いたTHE TOUR OF MISIA 2005 THE SINGER SHOWから「K.I.T」のビデオ だけが公開されています。
だけが公開されています。 も私のコメント(こちらの記事をご参照方)と共に公開される
も私のコメント(こちらの記事をご参照方)と共に公開される っつうことですか?
っつうことですか? (ただ、あの企画はどうなった? デス
(ただ、あの企画はどうなった? デス )
)
 OPENING賞」に選出されたTHE TOUR OF MISIA 2005 THE SINGER SHOWの「K.I.T」、私にとってもとても印象的
OPENING賞」に選出されたTHE TOUR OF MISIA 2005 THE SINGER SHOWの「K.I.T」、私にとってもとても印象的 なパフォーマンスです。
なパフォーマンスです。 の2列目の席で、「K.I.T」が始まる時には、あそこからMISIAがせり上がってくる、あっ出てきた
の2列目の席で、「K.I.T」が始まる時には、あそこからMISIAがせり上がってくる、あっ出てきた 、MISIAが近ぁ~い
、MISIAが近ぁ~い と大興奮させていただきました。
と大興奮させていただきました。 といっても良いほど、素晴らしいライヴ
といっても良いほど、素晴らしいライヴ だったのですが、困ったことに私はツアー初日&2日目のネタバレを読んでいました…
だったのですが、困ったことに私はツアー初日&2日目のネタバレを読んでいました…
 の状態で「K.I.T」の出だしを聴いたら、、、、、と思うと、なんとももったいないことをしたものだと思います
の状態で「K.I.T」の出だしを聴いたら、、、、、と思うと、なんとももったいないことをしたものだと思います
 デス
デス
 ことにしたのでありました。
ことにしたのでありました。 は、2月19日までの限定ですヨ
は、2月19日までの限定ですヨ












 が限られているものですから、いつ完結するのか不明ですが、お暇な方はお付き合いくださいませ。
が限られているものですから、いつ完結するのか不明ですが、お暇な方はお付き合いくださいませ。










 した
した 2010年秋に
2010年秋に とばかりに購入してしました
とばかりに購入してしました つづき:2012/02/01
つづき:2012/02/01 


 と目
と目 が
が と考え込む曲ありで、これから
と考え込む曲ありで、これから と嘆くのは早い
と嘆くのは早い
 に乗り込み、携帯
に乗り込み、携帯 の電源を切ろうとすると、、裏蓋が無い!!
の電源を切ろうとすると、、裏蓋が無い!! 
 …)落っことしたようです。 何やら波乱の大阪遠征になりそうな気配です。[携帯]
…)落っことしたようです。 何やら波乱の大阪遠征になりそうな気配です。[携帯]
 が入ってしまいそうで、かなり
が入ってしまいそうで、かなり
 を覚えて、
を覚えて、 ここで思い出したのは、この展覧会(
ここで思い出したのは、この展覧会( に福島県立美術館の
に福島県立美術館の の最後の一節でした。
の最後の一節でした。 が福島で放射能に汚染されることを危惧するアメリカの美術館の気持ちも理解できますが、なんとも
が福島で放射能に汚染されることを危惧するアメリカの美術館の気持ちも理解できますが、なんとも 酒井館長の文を借りれば、「
酒井館長の文を借りれば、「
 をプレゼント
をプレゼント してくれた方の訃報が届きました。
してくれた方の訃報が届きました。
 がやってきたと思っていたら、もう
がやってきたと思っていたら、もう
 )
) がとれていますし
がとれていますし 、かなり
、かなり

 が降り出して、明日朝には都心部でも積雪あり
が降り出して、明日朝には都心部でも積雪あり で出勤して、雪の降り方によっては
で出勤して、雪の降り方によっては が雪
が雪 ということにしました。
ということにしました。


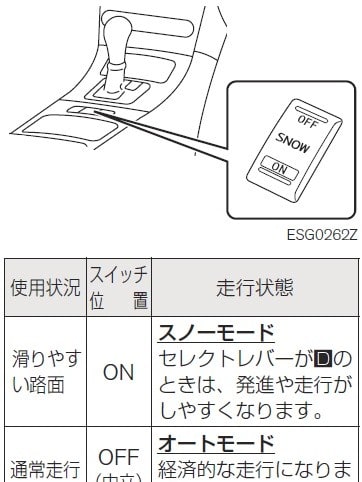


 になってしまうし(同じパスワードの
になってしまうし(同じパスワードの も危険
も危険 と月
と月 は別として、
は別として、

 古代ローマの偉大な学者・
古代ローマの偉大な学者・ して、それを
して、それを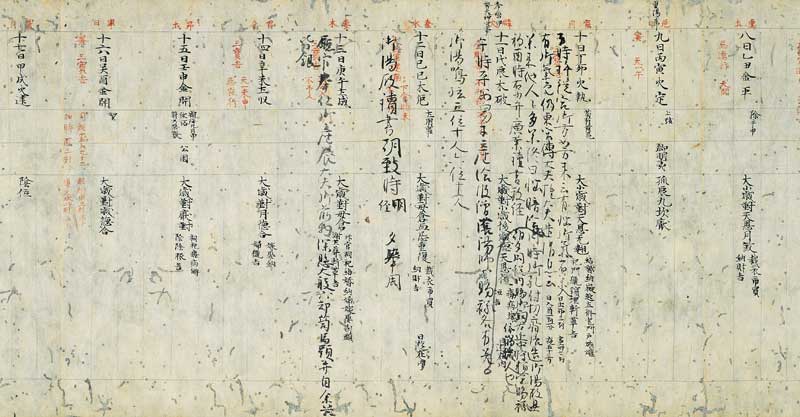

 」というわけではなかったようではありますが…。
」というわけではなかったようではありますが…。






