「土日祝日、乗用車と二輪車はどこまで走っても高速道路料金1,000円(一部地域を除く)」が始まって、世の中がETCで盛りあがっています。
 東京近郊と大阪近郊や、首都高速と阪神高速が例外扱いになって、複雑かつ東京圏と大阪圏のドライバーにはイマイチ「お得感」が乏しい制度ですが、地方の人たちや長距離ドライブを計画している人たちには朗報なんでしょう。一方で、レジャー渋滞が一層ひどくなる、とか、鉄道利用者がクルマに移るだけ、とか、CO2排出削減の観点からの「マイカーから公共交通機関へ」という流れに反するといった批判もあって、私としては、メリットよりもデメリットの方が大きいのではないかという気がしています(単に「気がする」だけです)。毎年恒例にしている夏休みの実家への長距離ドライブは、過去最悪のひどいことになるのではという危惧もあったりして…。
東京近郊と大阪近郊や、首都高速と阪神高速が例外扱いになって、複雑かつ東京圏と大阪圏のドライバーにはイマイチ「お得感」が乏しい制度ですが、地方の人たちや長距離ドライブを計画している人たちには朗報なんでしょう。一方で、レジャー渋滞が一層ひどくなる、とか、鉄道利用者がクルマに移るだけ、とか、CO2排出削減の観点からの「マイカーから公共交通機関へ」という流れに反するといった批判もあって、私としては、メリットよりもデメリットの方が大きいのではないかという気がしています(単に「気がする」だけです)。毎年恒例にしている夏休みの実家への長距離ドライブは、過去最悪のひどいことになるのではという危惧もあったりして…。
また、今行われているETC車載器の購入助成(こちら)にしても、財源が税金ではなく(財)高速道路交流推進財団の積立金だとはいえ、この積立金は、高速道路交流推進財団が前身の道路施設協会の頃に、全国のSA・PAの事業をほぼ独占して蓄えたお金が主。旧JHがファミリー財団を介さずに、直接、レストランや売店、ガソリンスタンドの運営業者を入札で決めて、「ショバ代」を稼いでいれば、もう少しは債務を減らすペースが上がったのではないかと思います。

ところで、私、かな~り古くからのETCユーザーです。私が初めてマイカーにETCをセットアップしたのは、2001年9月のこと。別に高速道路のヘビーユーザーというわけではなく、単に「新しもの好き」なだけですけど (Suicaも01年4~7月に埼京線・川越線&山手線の一部駅で実施されたモニターテストに参加しました)。
(Suicaも01年4~7月に埼京線・川越線&山手線の一部駅で実施されたモニターテストに参加しました)。
この01年9月という時期がどんな時期かといいますと、ETCの一般利用が千葉と沖縄で開始されたのが01年3月末、三大都市圏の一部区間で一般利用が開始されたのが同年7月末だったわけで、ETCを使える区間がホント少ない頃でした。セットアップ累計も、今年2月末時点で2,724万件を超えていますが、01年9月末時点ではわずか7万件 。利用率でみても、最新情報(3月19日現在)では76.9%であるのに対し、01年12月のデータではたったの0.9%。
。利用率でみても、最新情報(3月19日現在)では76.9%であるのに対し、01年12月のデータではたったの0.9%。
この 国交省の資料(オリジナルのPDFファイルはこちら)では、私がETCを使い始めた頃のデータはほとんどX軸上にあるように見えます。
国交省の資料(オリジナルのPDFファイルはこちら)では、私がETCを使い始めた頃のデータはほとんどX軸上にあるように見えます。

いやはや、隔世の感 とはこのことかもしれません。
とはこのことかもしれません。

そんな私がいうのも何ですが、通行料金を支払うための機械をユーザーが自腹で備え付けるって、変じゃありませんか?例えば、電気メーターやガスメーターをユーザーが購入して自宅につけますか?集金する側の電力会社やガス会社が(その調達費や運用費が使用料金に含まれているとしても)つけてくれるのが普通ですよね。
と、考えていたところ、ひょんなことから似たケースを思い出しました。
私が住んでいるマンションの管理組合から、水道使用量のテレメトリー用の電話料金が支出されています。検量作業する人の手間・費用を削減してあげているのに、妙だなぁと思っていたところ、テレメトリーのための電話代(基本料+通信料)を管理組合が負担することは、水道をマンションに引く条件になっていたんだそうな。
強気だぞぉ、埼玉県南水道企業団(旧浦和市と旧与野市で水道事業を展開していた公共機関。今はさいたま市水道局)
でも、やはりスッキリしません 。
。

さて、話をETCに戻しまして、ETCに「愛称」があるってご存じでした?
イーテックをよろしく、ってETCのこと?
国土交通省は28日、ETCの愛称を「イーテック」にすると発表した。7月から実施していた愛称コンテストの結果、決まったという。ちなみに他の候補は「イースルー」や「スルースルー」、「パスウェイ」など。
国交省はポスターなどに活用するほか、場合によっては料金所ゲートなどの名称変更も検討する、としている。ただ、すでにETCという名称がそれなりに浸透しているため、「税金の無駄遣い」という声も…。 (Response 01/11/28)
一時期、ETCのセットアップ申込書なんかにも「イーテック 」のロゴが載っていましたけれど、まさしく「E電」と同じ運命をたどっています。01年11月の時点で「すでにETCという名称がそれなりに浸透している」と書かれているのに、敢えてこんな不細工な「愛称」をつけたなんて、さすがは国交省の土木屋さんたちです。

「土日祝日、乗用車と二輪車はどこまで走っても高速道路料金1,000円(一部地域を除く)」は2年間は続くようですし、そのうち恩恵にあずかれることもあるでしょう。
まぁ、のんびり構えていきましょう 。
。
 のではありますけれど、ついうっかりと、第6章のタイトルを「番外編その1」にしたものですから、「番外編その1」の舞台となったベルリンで撮った写真を披露することにします。
のではありますけれど、ついうっかりと、第6章のタイトルを「番外編その1」にしたものですから、「番外編その1」の舞台となったベルリンで撮った写真を披露することにします。 。戦災にあったことから、かなり人工的な雰囲気が漂う街でしたが、ビルそのものや、装いが過激
。戦災にあったことから、かなり人工的な雰囲気が漂う街でしたが、ビルそのものや、装いが過激 で、ロンドンやパリと比べても遜色ないおもしろさでした。
で、ロンドンやパリと比べても遜色ないおもしろさでした。 。
。 は、ベルリンの最繁華街:ポツダム広場に面したビル。
は、ベルリンの最繁華街:ポツダム広場に面したビル。 です。
です。 は教会のようですが、なにやら「ブラック・ジャック風」。
は教会のようですが、なにやら「ブラック・ジャック風」。 が聞こえてきそうで、楽しいなぁ。
が聞こえてきそうで、楽しいなぁ。 。
。
 つづき:09/04/10 トイレからの脱出 (第8章=国内編その1)
つづき:09/04/10 トイレからの脱出 (第8章=国内編その1)

















 。場内もざわつくほどの揺れだったのですが、舞台は何事も起こっていないかのように進行していきました。まさに「
。場内もざわつくほどの揺れだったのですが、舞台は何事も起こっていないかのように進行していきました。まさに「
 、出演者の見事なテンポの会話の応酬
、出演者の見事なテンポの会話の応酬 、適度な笑い
、適度な笑い 。
。

 。
。 です。
です。 。
。

 (
(





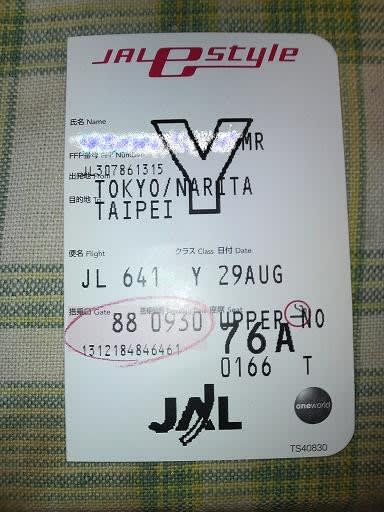

 と思いましたが、まさか
と思いましたが、まさか



 です。
です。 の「
の「 が無駄
が無駄

 が無いかな?と思ったんです。で、
が無いかな?と思ったんです。で、
 を思い出してしまいます。目をつむると、
を思い出してしまいます。目をつむると、



 )で、制作者の意図が理解できないでいるのですが、それはまた別の話。
)で、制作者の意図が理解できないでいるのですが、それはまた別の話。 )はありましたけれど、
)はありましたけれど、
 」を聞いてしまった赤坂2日目、初めての海外遠征となった台湾、これまた初めての体験だった幕張でのゲネプロ、、、、、。どのライヴ(参加できなかった赤坂初日を除く)でも、MISIAは楽しそうだったなぁ、ダンスが上手になったなぁ、素晴らしい歌声だったなぁ、と、思いは
」を聞いてしまった赤坂2日目、初めての海外遠征となった台湾、これまた初めての体験だった幕張でのゲネプロ、、、、、。どのライヴ(参加できなかった赤坂初日を除く)でも、MISIAは楽しそうだったなぁ、ダンスが上手になったなぁ、素晴らしい歌声だったなぁ、と、思いは と巡るのでありますよ。
と巡るのでありますよ。
 。空気がカラカラで、風邪とインフルエンザが大流行中のこの時期(私も珍しくインフルエンザに罹り、その前1週間はほとんどダウン状態
。空気がカラカラで、風邪とインフルエンザが大流行中のこの時期(私も珍しくインフルエンザに罹り、その前1週間はほとんどダウン状態 でした)、よくぞ体調を維持して、そして絶妙のペース配分をしたものだと
でした)、よくぞ体調を維持して、そして絶妙のペース配分をしたものだと です。
です。

 じゃありませんか? 何か「こども銀行」のようなイメージで…。
じゃありませんか? 何か「こども銀行」のようなイメージで…。










