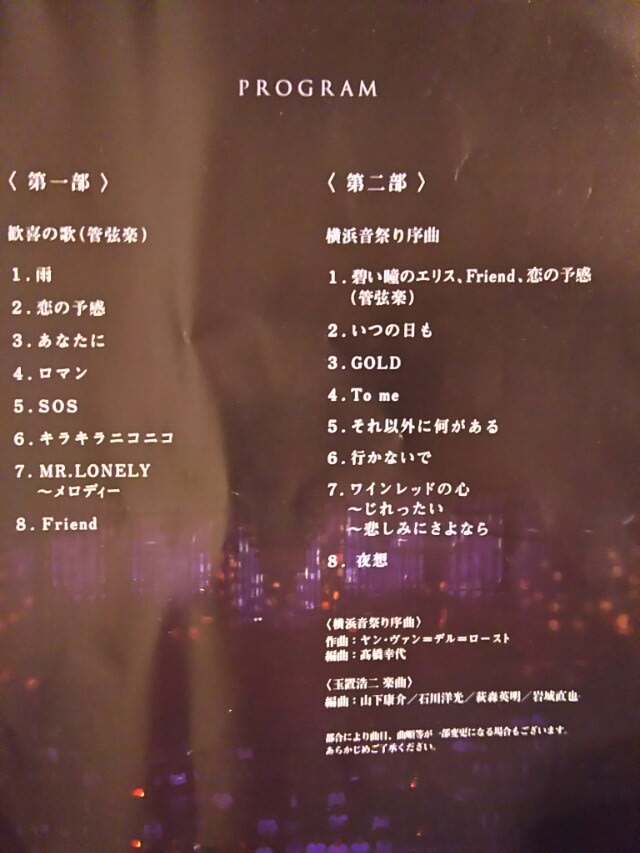KOJI TAMAKI PREMIUM SYMPHONIC CONCERT
栁澤寿男(指揮)
東京フィルハーモニー交響楽団
2016年9月22日(祝・木) 17:00開演
みなとみらいホール大ホール
噂の玉置浩二 with オーケストラを聴いた。
玉置浩二の歌声も歌心も天性のもので、それを生で体験できたのは嬉しい体験であった。ただ、期待を上回る感動であったか? と問われると、そこまでには至らなかった。
隣席のご婦人が、開演前からゲホゲホと激しく咳き込んでいたことで精神の集中を乱されたのも一因ではあるが、もっと根本的な問題としてはPAを通したときの玉置浩二の声だ。みなとみらいホールは、クラシック専用のホールのため、生の声でも響くように音響設計されている。そこに、リバーブの掛かった声がスピーカーから流れるとエコー過多となってしまうのだ。もともと美声なのだからリバーブなし、くらいの思い切った判断があっても良かったと思う。実際、マイク無しで歌われたアンコール2曲目の「夏の終わりのハーモニー」が全曲中でもっとも感動的だったのは、電気的な増幅や処理を一切施されない「生の声」だったからだと確信する。
そして、もうひとつの原因は、指揮者の存在。指揮者・柳澤寿男の振り方がボクの趣味にまったく合わず、それが絶えず視界に飛び込んでくるので落ち着かないのである。具体的には、地に足が着かず腰が浮き、肩甲骨が固定されたまま腕だけ振り回し、さらには打点ばかりが強調されて横に流れない棒の振り方によって、オケも鳴らず、歌が溢れてこないのだ。
玉置浩二が天才であり、狂気と正気の紙一重をゆく芸術家だとしたら、柳沢の棒から生まれる音楽はあまりに普通であり、その才能のギャップが見えすぎてしまう。東京フィルも、どれほど主力メンバーが乗っていたのか不明だが、普段聴かせてくれるより弦の音が薄かったような気がする。
「この指揮者でベートーヴェンだけは聴きたくないな」と思っていたところ、なんとアンコール1曲目でそれを聴かされてしまったのには苦笑してしまった。それは交響曲第6番ヘ長調「田園」である。「田園交響曲」の第1楽章がしばらく奏でられたところで、「生きていくんだ それでいいんだ」のフレーズが挟み込まれ、徐々に増幅し、遂にはすっかり玉置浩二の「田園」となる、という趣向は粋であるが、冒頭のベートーヴェンのオリジナルの部分が、これほど情けなく響くのを聴くのははじめてであった。ふだん、クラシックを聴かない客ばかりだろうから、と舐めていたわけではあるまいが・・・。とはいえ、ヴォーカルは絶好調で、客も沸いたしボクも愉しんだ。本編がスロー・バラードばかりだったので、アップテンポの曲で心が解放される感があった。オーケストラが乗りの良い、テンポの速い曲を出来ないわけではないのだから、本編にももっと多彩な曲想の置いてもよいのでは? と思った次第。
ところで、クラシック演奏会のフライングブラヴォーも困りものだが、本日のコンサートの「ボキャ貧掛け声」も考えものだ。隙をみては、「愛してる」「ありがとう」の2つの単語だけを大声で繰り返す男が二階席中央辺りに居たけど、時間の経過とともに、他に日本語を知らないのか? と苛立ちが募る(笑)。極め付きは、上にも述べたアンコール2曲目「夏の終わりのハーモニー」ラストで、ピアニシモからの美しい沈黙に聴衆が固唾を呑んでいるときの、間の抜けた「ありがとう」の叫び声。殺意を覚えたのはワタシだけではあるまい。