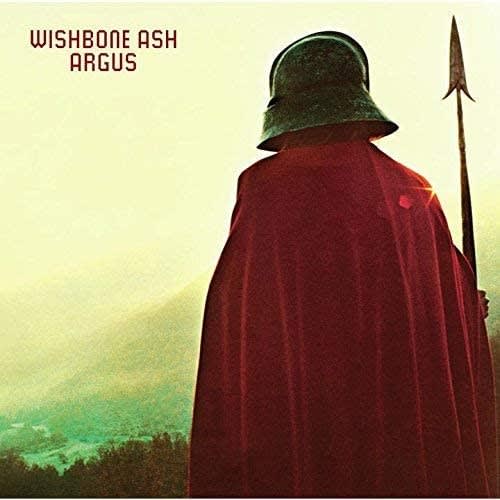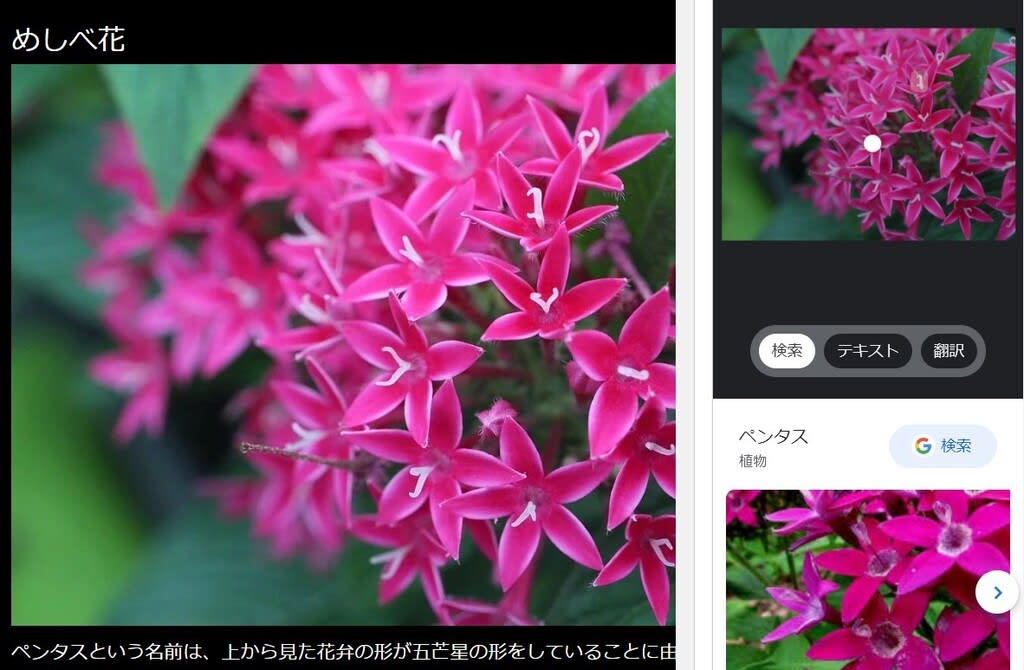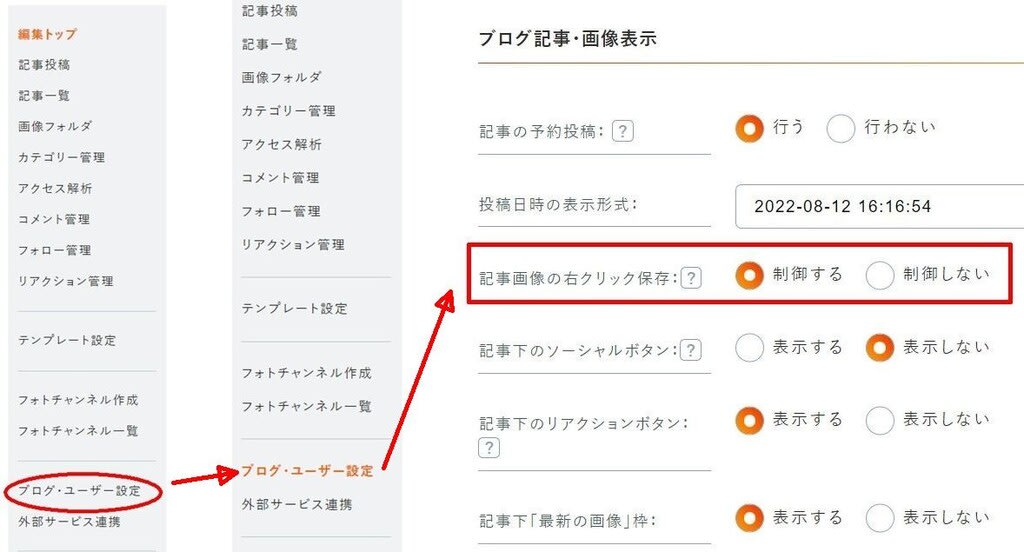涼しげなトレニアの花です。

安城デンパークの名板によると ’カタリーナ アイスリバー’ という品種のようです。
名前からして涼しそうですね

ところで、このトレニア(Torenia)は何科の植物なんでしょうか?
安城デンパークの名板では「アゼトウガラシ科」となっていますが・・・

「トレニアは、アゼナ科の非耐寒性一年草です。」(LOVEGREEN)との記事もあります。

トレニアには長短2組のおしべがあるのですが、長い一組同志、また短い一組同志が左右から花糸を出しアーチを作っていることが多いのが特徴です。
ウリクサという野草があって ↓

この花も左右の雄しべがアーチを作っています。
よく似ています。

トレニアがウリクサに似ているのもそのはずで、実をいうと、トレニアの別名は「ハナウリクサ」なのです。

松江の花図鑑によると、ウリクサは アゼナ科のハナウリクサ属に属してます。
学名は Torenia crustacea
属名は Torenia
そうです、ハナウリクサ属というのは Torenia属 のことだったんです !(^^)!

一方、三河の植物観察によると、ウリクサは「アゼナ属からツルウリクサ属に移動された。」とあります。
で、「ツルウリクサ属」とは何ぞや?と調べると、「ツルウリクサ属(学名:Torenia、トレニア属)はアゼナ科の属の1つ。」とあります。
ということは、結局、「ツルウリクサ属=Torenia トレニア属 =ハナウリクサ属」だったんですね (´∀`)
 アゼナ科
アゼナ科というのは比較的新しい科で、「旧分類ではゴマノハグサ科に含められ、APGⅡ(2003年)ではオオバコ科に移されたが、APG III(2009年版)ではアゼナ科として独立」(三河の植物観察「アゼナ科」)したのです。

先ほどの Wikipedia にも Torenia属は「クロンキスト体系ではゴマノハグサ科、APG IIではオオバコ科に分類されていた。」との記述が見られます。

トレニアでは5本ある雄しべの1本が退化してなくなり、上側の2本の雄しべはアーチ形につながり、下側に2本の雄しべは短く雌しべの基部にあります。これは科は違うけれどノウゼンカズラやアメリカノウゼンカズラの雄しべと同じです。

また、雌しべも面白いです。
ほかの花で花粉をつけたハチがこの花の中央の雌しべの柱頭に触れると花粉が柱頭につきます。
ハチが雌しべに触れると、雌しべの先が閉じます。花粉が乾燥しないように閉じるのだとも考えられています。花粉は雌しべから水分をもらってすぐに活動を始め、花粉管を伸ばします。花粉管は雌しべの中を伸びていきます。
ここから先は
NHK ミクロワールド 「トレニアの花 雌雄の出会い」
をご覧ください(^^♪

というわけで、確かに雌しべも面白いのですけれど・・・
でも、最初は 雄しべのアーチのほうが目につきやすいですよね
Wishbone flower

トレニアは 英語で Wishbone flower だそうです。
よく日本語サイトの説明では
「wishbone flowerは、先が二つに割れためしべの形が鶏のウィッシュボーン(胸骨)に似ていることに由来しています。」 ??
との説明がありますが・・・

私は 左右から雄しべの葯がくっついて花糸がアーチを作った姿が

ウィッシュボーン(暢思骨)(wiki 「叉骨」より)
に似ているからではないか、なんて、勝手に思ってます (^_-)-☆
〔追記〕
ちょっと英文サイトで 「wishbone flower の由来(origin)」を調べてみたところ、
案の定というか、こんなことが書いてありましたよ (´∀`)
The common name, wishbone flower, refers to the way the flower’s stamens form a wishbone shape at the anthers.
(一般名であるウィッシュボーン フラワーは、雄しべがその葯でウィッシュボーンの形をつくることに由来します)
これだから、詮索、いや、検索、止められませんね (^^ゞ
ついでに
wishbone とはそもそも Wish Bone。つまり直訳すれば「願い骨」。
実はこれ、鶏の胸骨に由来する。鳥の丸焼きを食べた後、λ型をした胸骨を外し、ふたりで両端を持って引っ張り合う。胸骨の頂点は丈夫だから、真ん中では割れず、どちらかの破片に頂点が付いてくる。その頂点を取った者の願いが叶う、という言い伝えから、鳥の胸骨を「ウィッシュボーン」と呼ぶようになったらしい。(Motor-fan Tech. 「ダブルウィッシュボーンの「ウィッシュボーン」とは何か——安藤眞の『テクノロジーのすべて』第56弾」)
そういえば、Wishbone Ash なんてロックバンドありましたね
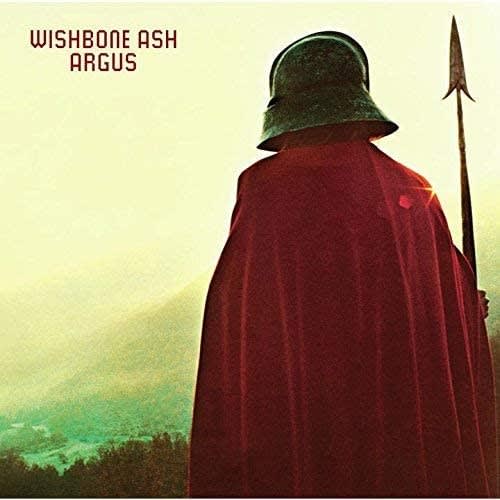
そのツインギターはオールマン・ブラザーズ・バンドとは違い、プログレッシヴ・ロックやフォーク、クラシックに強い影響を受けていた。この頃新しいバンド名を考案しようとした際に「ウィッシュボーン」と「アッシュ」の2例が上がり、マーティン・ターナーがその2つを組み合わせてバンド名とした。(Wikipediaより)
ひさしぶりに聞いてみようか (^^♪
Wishbone Ash - The King Will Come
.