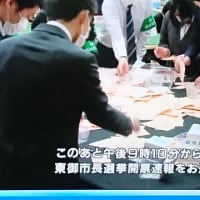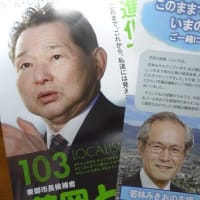先日上田産院のH医師と飲んだことを書きましたが、インターネットを検索していたら彼の講演録が掲載されていたので、以下に転記します。彼のお産に対する考えを知ってほしいと思います。以前掲載した東御市民病院の木村先生とも共通するものがあります(11月26日のブログ参照)。
講演会から-山梨県男女共同参画推進センター主催(山梨新報、2007.12)
「安心して産める場を求めて」 H医師 上田市産院院長(当時副院長)
○疑問視される過剰な医療介入
妊婦のお腹に触れながら、どこに赤ちゃんの何があるかを伝え、じっくり相談に応じて出産への不安を取り除く・・・。助産師はこうして母親に、生まれ来る我が子への身体感覚を研ぎ澄まさせることで、母性を目覚めさせ、安心して出産を迎えるための手助けをしてきた。
日本のお産はこれまで、正常出産の専門家であり、異常をきちんと見分けられる助産師と、病理的妊娠出産の専門家である医師とが役割分担し、連携しながら取り組んできた。
だが、太平洋戦争後、アメリカの産科学が入ると、超音波による検診、陣痛促進剤の使用、分娩台に体を固定された状態での出産、帝王切開など「母子の安全」の名の下で医療介入する病院出産が当たり前となり、医師への依存が強まった。
しかし、女性にとって過剰な医療介入がかえって出産を不安と恐怖に満ちたものにしている現代のお産は、本当に、「母親の産む力」と「赤ちゃんの生まれる力」を引き出しているのか、疑問に思えてならない。
○母子を離さないカンガルーケア
私が勤務する上田市産院では、産科医2人と助産師12人で年間700件のお産を扱っている。これは、助産師によるケアを中心にしているからこそ、可能な件数である。
そのほとんどで、生まれた赤ちゃんをすぐに母親の胸の上に置き、その後も母子を引き離さない「カンガルーケア」を実施している。カンガルーケアは、出産は病気ではなく健康で正常な営みであり、女性を母親へと変える『奇跡』なのだと感じさせる。
普通、病院出産では、生まれた赤ちゃんは直ちに母親から引き離され、口や鼻からの吸引などの処置を施された後、感染防止のために新生児室に運ばれる。だが、カンガルーケアでは、母親の胸の上で赤ちゃんは、急いでへその緒を切られることもない。何の医療行為を受けずとも、みるみるピンク色になり、そのまま静かに30分ほど過ごす。同時に、母親の肌の常在菌を取り込み、院内感染などへの抵抗力を付け、やがて自ら乳房を探し当てて初乳を吸う。
○女性の側に立ち、ケアを提供する
生まれたばかりの赤ちゃんを胸に抱いた母親は、なんとも表現できない美しい表情をしている。我々人間は、こうしたお産を何十万年と行ってきた。
全国的な産科医不足によって、各地で産科医療集約化の動きがあるが、それはかえって「産科医がいなければお産はできない」という意識を広め、医療介入の少ない素晴らしい出産体験の機会を失わせている。さらに、妊産婦が一カ所に集中することで、医者や助産師が忙しくなり、出産自体を安全でないものにする恐れさえある。
こうした中で、痛感するのは、助産師によるケアを中心にした第一次産科施設であるバースセンターを設立し、お産を分散化する必要である。バースセンターでは、助産師主導の産前ケア、陣痛と出産時の介助、母乳育児支援などを提供する。ここで大切なのは、何か異常があった時、医師が背後からきちんと医療介入できる仕組みや搬送システムを整備することである。
要は、女性の立場に立ったケアを継続的に提供できる助産師が活躍できる場所を広げることこそ、安心してお産できる場をつくることにつながっていくと考えている。
講演会から-山梨県男女共同参画推進センター主催(山梨新報、2007.12)
「安心して産める場を求めて」 H医師 上田市産院院長(当時副院長)
○疑問視される過剰な医療介入
妊婦のお腹に触れながら、どこに赤ちゃんの何があるかを伝え、じっくり相談に応じて出産への不安を取り除く・・・。助産師はこうして母親に、生まれ来る我が子への身体感覚を研ぎ澄まさせることで、母性を目覚めさせ、安心して出産を迎えるための手助けをしてきた。
日本のお産はこれまで、正常出産の専門家であり、異常をきちんと見分けられる助産師と、病理的妊娠出産の専門家である医師とが役割分担し、連携しながら取り組んできた。
だが、太平洋戦争後、アメリカの産科学が入ると、超音波による検診、陣痛促進剤の使用、分娩台に体を固定された状態での出産、帝王切開など「母子の安全」の名の下で医療介入する病院出産が当たり前となり、医師への依存が強まった。
しかし、女性にとって過剰な医療介入がかえって出産を不安と恐怖に満ちたものにしている現代のお産は、本当に、「母親の産む力」と「赤ちゃんの生まれる力」を引き出しているのか、疑問に思えてならない。
○母子を離さないカンガルーケア
私が勤務する上田市産院では、産科医2人と助産師12人で年間700件のお産を扱っている。これは、助産師によるケアを中心にしているからこそ、可能な件数である。
そのほとんどで、生まれた赤ちゃんをすぐに母親の胸の上に置き、その後も母子を引き離さない「カンガルーケア」を実施している。カンガルーケアは、出産は病気ではなく健康で正常な営みであり、女性を母親へと変える『奇跡』なのだと感じさせる。
普通、病院出産では、生まれた赤ちゃんは直ちに母親から引き離され、口や鼻からの吸引などの処置を施された後、感染防止のために新生児室に運ばれる。だが、カンガルーケアでは、母親の胸の上で赤ちゃんは、急いでへその緒を切られることもない。何の医療行為を受けずとも、みるみるピンク色になり、そのまま静かに30分ほど過ごす。同時に、母親の肌の常在菌を取り込み、院内感染などへの抵抗力を付け、やがて自ら乳房を探し当てて初乳を吸う。
○女性の側に立ち、ケアを提供する
生まれたばかりの赤ちゃんを胸に抱いた母親は、なんとも表現できない美しい表情をしている。我々人間は、こうしたお産を何十万年と行ってきた。
全国的な産科医不足によって、各地で産科医療集約化の動きがあるが、それはかえって「産科医がいなければお産はできない」という意識を広め、医療介入の少ない素晴らしい出産体験の機会を失わせている。さらに、妊産婦が一カ所に集中することで、医者や助産師が忙しくなり、出産自体を安全でないものにする恐れさえある。
こうした中で、痛感するのは、助産師によるケアを中心にした第一次産科施設であるバースセンターを設立し、お産を分散化する必要である。バースセンターでは、助産師主導の産前ケア、陣痛と出産時の介助、母乳育児支援などを提供する。ここで大切なのは、何か異常があった時、医師が背後からきちんと医療介入できる仕組みや搬送システムを整備することである。
要は、女性の立場に立ったケアを継続的に提供できる助産師が活躍できる場所を広げることこそ、安心してお産できる場をつくることにつながっていくと考えている。