またアンプを作りましたが、今回は初めてメーカー品に手を加えた物なので、あえて改造としました。アンプ基板や電源部は作り直したので、実質は新規製作に近いですが、フロントパネルやメインボリュームなどは流用したので、見栄えはメーカー品のままです。
ベースとなったのは、パイオニアのローコスト製品です。一応はダイレクトエナジーMOSというデバイスを使っていますが、回路のパーツはゴマ粒程度なので音は期待できません。これの「片チャンネルの音が出ません」というジャンクを1000円で落札してみました。メイドインジャパンなので、電源回りはそこそこに高級です。この電源部を利用して、使い慣れた回路を収めてみました。パワー段とドライブ段が独立した、往年のビクターが命名した前後独立電源です。本当の高級品は、ここからさらに、左右の干渉のない左右独立電源となるのです。
今回苦労したのは、小さなスペースに収めるレイアウトです。入力端子やスピーカー端子はオリジナルを流用するので、結構ギリギリのレイアウトとなりました。電源のブロックコンデンサーとメインアンプ基板は、穴開きのユニバーサル基板を用いました。終段の石は、前回と同様にNECの中出力MOS-FET、2SK2303/2SJ313のコンプリ(コンプリメンタリー=上下対象)です。ソニーの高級MOS-FETプリメインアンプのドライバー段に使われていた石で、ノイズと歪みの小さな名石です。無理をすれば大型の大出力MOSも使えたのですが、ヒートシンクが小さいので諦めました。

電源を入れるとボリューム回りが白く、入力インジケーターがオレンジ色に光ります。音ですが、電源トランスがしっかりしているので低音も苦になりませんが、やはりMOSの特徴である繊細さと空間表現に優れています。パワーは小さいので、パソコン用にはピッタリだと思います。


なお、日立の古いパワーアンプ、Lo-D HMA-4590ジャンクを1200円で落札し、中身を調べてみました。電源コードも切られていて、ボンネットは凹んで中も埃だらけでした。音も片方から小さく出る程度で、ジャンクも頷けます。でも、終段のMOS-FET(世界初のオーディオ用にして、未だに最高音質)を外して調べてみたら生きているようです。これだけで5千円から1万円近くの値段が付くこともあるプレミア品です。
回路を調べてみたら直りそうなので、トランス以外は全部分解して洗いました。でも、せっかくの石が壊れると嫌なので、後継のまた後継という2SK2221/2SJ352を代用しました。ヘッドフォンで聴いてみると、時々バチッという音がして、パワーレベルメーターが動かなくなります。音は大丈夫なので、パーツを換えれば直りそうです。それにしても、ローコスト製品なのでパーツの数が少なく、修理には手を出しやすいですね。フロントパネルが凹んでいるし、高級感もないので、パネルだけ黒っぽいアクリルにし、インジケーターなどをアクリルの向こうから透けて見えるようにすれば、高級感も出ると思います。音は、回路が古いのと、トランジスタが多用されているので、僕の自作FETアンプにかないません。外した高価な石は、僕のアンプで生かすつもりです ホルホルホル <`∀´*>。
12月03日 追加
Lo-D HMA-4590の修理が終わったので追記。抵抗とダイオードを除いて新品に交換。まあまあの音質になりました。メインスピーカーに繋ぐとサーというノイズが聞こえますが、これは終段以外に使われているトランジスタのノイズですね。

トランジスタの特徴である力強さと甘さが出ているのですが、終段のMOS-FETの特徴である高域の伸びと繊細さをマスクしています。空間表現では、春霞のような見通しで、上級機の秋晴れの空とは違います。全体的に、印象派のモネのようなタッチの荒さ(粒子の大きさ)が感じられますが、油絵のギトギトした感じよりは日本画の公募展に近いですね。東山魁夷(かいい)とかが好きな人に向いています。アンプとしては悪くないですね。

エフライム工房 平御幸
ベースとなったのは、パイオニアのローコスト製品です。一応はダイレクトエナジーMOSというデバイスを使っていますが、回路のパーツはゴマ粒程度なので音は期待できません。これの「片チャンネルの音が出ません」というジャンクを1000円で落札してみました。メイドインジャパンなので、電源回りはそこそこに高級です。この電源部を利用して、使い慣れた回路を収めてみました。パワー段とドライブ段が独立した、往年のビクターが命名した前後独立電源です。本当の高級品は、ここからさらに、左右の干渉のない左右独立電源となるのです。
今回苦労したのは、小さなスペースに収めるレイアウトです。入力端子やスピーカー端子はオリジナルを流用するので、結構ギリギリのレイアウトとなりました。電源のブロックコンデンサーとメインアンプ基板は、穴開きのユニバーサル基板を用いました。終段の石は、前回と同様にNECの中出力MOS-FET、2SK2303/2SJ313のコンプリ(コンプリメンタリー=上下対象)です。ソニーの高級MOS-FETプリメインアンプのドライバー段に使われていた石で、ノイズと歪みの小さな名石です。無理をすれば大型の大出力MOSも使えたのですが、ヒートシンクが小さいので諦めました。

電源を入れるとボリューム回りが白く、入力インジケーターがオレンジ色に光ります。音ですが、電源トランスがしっかりしているので低音も苦になりませんが、やはりMOSの特徴である繊細さと空間表現に優れています。パワーは小さいので、パソコン用にはピッタリだと思います。


なお、日立の古いパワーアンプ、Lo-D HMA-4590ジャンクを1200円で落札し、中身を調べてみました。電源コードも切られていて、ボンネットは凹んで中も埃だらけでした。音も片方から小さく出る程度で、ジャンクも頷けます。でも、終段のMOS-FET(世界初のオーディオ用にして、未だに最高音質)を外して調べてみたら生きているようです。これだけで5千円から1万円近くの値段が付くこともあるプレミア品です。
回路を調べてみたら直りそうなので、トランス以外は全部分解して洗いました。でも、せっかくの石が壊れると嫌なので、後継のまた後継という2SK2221/2SJ352を代用しました。ヘッドフォンで聴いてみると、時々バチッという音がして、パワーレベルメーターが動かなくなります。音は大丈夫なので、パーツを換えれば直りそうです。それにしても、ローコスト製品なのでパーツの数が少なく、修理には手を出しやすいですね。フロントパネルが凹んでいるし、高級感もないので、パネルだけ黒っぽいアクリルにし、インジケーターなどをアクリルの向こうから透けて見えるようにすれば、高級感も出ると思います。音は、回路が古いのと、トランジスタが多用されているので、僕の自作FETアンプにかないません。外した高価な石は、僕のアンプで生かすつもりです ホルホルホル <`∀´*>。
12月03日 追加
Lo-D HMA-4590の修理が終わったので追記。抵抗とダイオードを除いて新品に交換。まあまあの音質になりました。メインスピーカーに繋ぐとサーというノイズが聞こえますが、これは終段以外に使われているトランジスタのノイズですね。

トランジスタの特徴である力強さと甘さが出ているのですが、終段のMOS-FETの特徴である高域の伸びと繊細さをマスクしています。空間表現では、春霞のような見通しで、上級機の秋晴れの空とは違います。全体的に、印象派のモネのようなタッチの荒さ(粒子の大きさ)が感じられますが、油絵のギトギトした感じよりは日本画の公募展に近いですね。東山魁夷(かいい)とかが好きな人に向いています。アンプとしては悪くないですね。

エフライム工房 平御幸















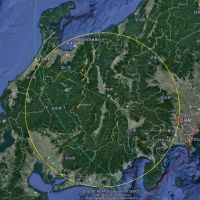
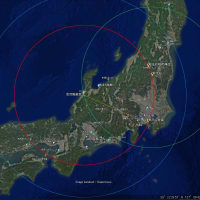

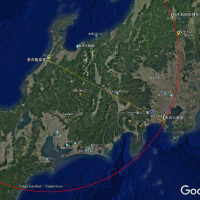







はじめまして。
だいまい14と申します。
ネット検索でたどり着きました。
アンプの改造ブログが私のアンプとあまりにもそっくりで書き込みしました。
使用機種や使用目的、製作期間、オークションでの落札金額まで同一でした。
概要ですが、初段はK246差動+定電流K246、2段目はJ103差動 終段K1056×2のDCアンプです。
PC用には十分すぎる実力です。
その写真をUPしました。
(頭にhttpを足して下さい)
://deaicafe.sakura.ne.jp/up/src/file0362.jpg
://deaicafe.sakura.ne.jp/up/src/file0361.jpg
さっそく拝見しました。僕のよりも本格的に改造されていますね。自作の鑑のような手抜きのなさで、いろいろと参考になります。僕は底板の穴開けをしないで済むレイアウトでしたから、グータラの見本でした。
僕は電圧増幅段と終段の電源を分ける、ビクターで有名になったA級B級独立電源にこだわっています。2SK79+中出力MOSを使った窪田式ヘッドフォンアンプをスピーカーに繋いだら荒い音で、これの終段電源を独立させ、2SK1057コンプリに換えたら激変しました。最初の自作機だったので、音の荒かった別の理由も存在するかもしれませんが、これ以降は独立電源しか作った事はありません。
2段目は2SK79を使いたかったのですが、高価なので2SK246で妥協しました。電流に余裕はないのですが、意外に良い石だと思います。2SK79の飛んでる高域より万人向きだと思います。
それにしても、落札時期も同じとは不思議ですね。もしかしたら、オークションで出会うかもしれませんね。その時はお手柔らかにお願いします。
早速お返事頂きありがとうございました。
また、作品をお褒め頂きうれしく思います。
シンプル&ローコストを狙った作品なので、なんだか恥ずかしいです。
平御幸様はあの小さなボディに2電源方式を組み入れており感心しております。
また、その音質が気に掛かります。
普段から同じようなFETを使用していることを伺い面白く思いました。
はじめまして paracat と申します。
Lo-D HMA-4590について調べていたらこちらにたどり着きました。
かなり以前に購入ストックしておいた綺麗な機械ですが復活してあげようと思いまして先日中身を開きまして眺めていました。オフセットの調整は旨くいきましたが技術力や回路図が無い為、バイアス調整とアイドリング調整の方法が解りません。
しっかり出力出来ていますがきちんと整備し安心して聴けるよう調整したいと思います。
お手数ではありますが教えていただければ幸いです。
以上よろしくお願いします。
HMA-4590は、通常のアンプで0.22オームや0.47Ωが使われるソース抵抗が省略されています。
金田アンプもソース抵抗を省略して音質向上を図っていますが、ソース抵抗がないと両端電圧に発生する電圧が測れません。
ソース抵抗両端電圧から計算してバイアス値を求めるので、HMA-4590にソース抵抗を追加して計測する必要があります。
これは、同じくソース抵抗のないHMA-7500やHA-7700などでも同じです。だから、ソース抵抗を調整の時だけ追加して、調整後に取外す必要があります。
自分は面倒なので、パワーMOSをキャラメル型に変更してソース抵抗を追加したままにしました。また、ゲート電圧とヒートシンクの温まり方から動作点を推量することも出来ます。ほんのり温かかったら100mA程度で、ソニーの250mAだとそこそこ熱く感じます。
ということで、ソース抵抗追加以外には方法はありません。英語版のHMA-7500回路図には調整方法が書いてあります。左のブックマークのエフライム工房へのリンクからメールを送ってもらえれば回路図は差し上げます。ファイルサイズが8Mですけど (;^ω^)