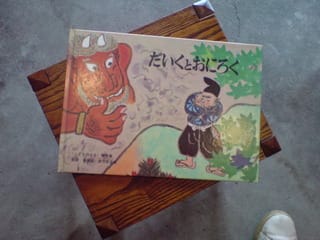本日お話が聞けたのは、人間国宝の大坂弘道さんです。
正倉院宝物などを復元するなどの実績をお持ちです。
非常にオープンなお話をして頂き、ためになっただけでなく大変楽しむことができました。
以下、お話の中での私のメモッたお言葉です。
■「木工が好きでなったわけではない」
職人さんによく聞かれる言葉ですね。大坂さんも兄弟が多く東京に出て自由になりたかった。昔は金工をやっていたけど、どうしても入賞できず木工に転向したなどのエピソードをお聞きしました。
■1/3主義
今まで人生1/3ずつ生きてきた。20代までの勉強の時期、40代後半までの教師生活(その間創作活動は継続)、そして現在に至る木工家としての時期。バランスが大事なのだと思います。
■「正倉院はすごい」
あそこには宝物がいっぱいある。写真で見たり、ガラス越しに見るのと、自分で手にとって実際に見てみるのでは全然違う。
■「微細の美」
正倉院の宝物はこの一言にまとめられる。微細な小さなものに大きな世界のことが凝縮されているという意味のお経もあるという。微細を勉強することは大きな世界の摂理にもつながるということ。
■「工芸品は小さくなくてはいけない」
昔、工芸品はお金持ちの旦那がお客さんに自慢するものだった。そのため小さなものであった。それが今の工芸品は展覧会のためのものになり大きすぎたりする。
■「箱が主役ではいけない」
箱はもともと宝物、貴重なものという主役をしまうための入れ物である。それが最近は箱自体が工芸品になり、展覧会に出品され、箱自体が主役になってしまっていることがある。また何を入れるものか明確でないものもある。これではいけない。
■自分の原動力は「人のやってないものをやろう、人の見てないものを見てやろう」
たいてい人が作れるものは人が作れるものである。自分だけのものを作りたいとか、正倉院の中は一般人が見ることなど許されていない聖域、そこを見てみたいという思いで木工を続けてきた。
■「歳をとると作風を変えないといけない」
名人でも歳をとると目が悪くなり、どうしても細かな作業、文様彫りなどは厳しくなるそうです。頑なに縛られるのではなく、自分の作風を変えていける勇気を持ちたいですね。
■「ゆっくり作って3年」
ひとつの作品にそれくらいの時間をかけることもあるそうです。「だってずっとやっているとい飽きちゃうじゃないですか」こんな気持ちのゆとりが継続するには必要なのでしょう。
■「ものつくり」であり「ものかたり」ではないので悪しからず。
講演の最後に、講演を謙遜して。
正倉院宝物などを復元するなどの実績をお持ちです。
非常にオープンなお話をして頂き、ためになっただけでなく大変楽しむことができました。
以下、お話の中での私のメモッたお言葉です。
■「木工が好きでなったわけではない」
職人さんによく聞かれる言葉ですね。大坂さんも兄弟が多く東京に出て自由になりたかった。昔は金工をやっていたけど、どうしても入賞できず木工に転向したなどのエピソードをお聞きしました。
■1/3主義
今まで人生1/3ずつ生きてきた。20代までの勉強の時期、40代後半までの教師生活(その間創作活動は継続)、そして現在に至る木工家としての時期。バランスが大事なのだと思います。
■「正倉院はすごい」
あそこには宝物がいっぱいある。写真で見たり、ガラス越しに見るのと、自分で手にとって実際に見てみるのでは全然違う。
■「微細の美」
正倉院の宝物はこの一言にまとめられる。微細な小さなものに大きな世界のことが凝縮されているという意味のお経もあるという。微細を勉強することは大きな世界の摂理にもつながるということ。
■「工芸品は小さくなくてはいけない」
昔、工芸品はお金持ちの旦那がお客さんに自慢するものだった。そのため小さなものであった。それが今の工芸品は展覧会のためのものになり大きすぎたりする。
■「箱が主役ではいけない」
箱はもともと宝物、貴重なものという主役をしまうための入れ物である。それが最近は箱自体が工芸品になり、展覧会に出品され、箱自体が主役になってしまっていることがある。また何を入れるものか明確でないものもある。これではいけない。
■自分の原動力は「人のやってないものをやろう、人の見てないものを見てやろう」
たいてい人が作れるものは人が作れるものである。自分だけのものを作りたいとか、正倉院の中は一般人が見ることなど許されていない聖域、そこを見てみたいという思いで木工を続けてきた。
■「歳をとると作風を変えないといけない」
名人でも歳をとると目が悪くなり、どうしても細かな作業、文様彫りなどは厳しくなるそうです。頑なに縛られるのではなく、自分の作風を変えていける勇気を持ちたいですね。
■「ゆっくり作って3年」
ひとつの作品にそれくらいの時間をかけることもあるそうです。「だってずっとやっているとい飽きちゃうじゃないですか」こんな気持ちのゆとりが継続するには必要なのでしょう。
■「ものつくり」であり「ものかたり」ではないので悪しからず。
講演の最後に、講演を謙遜して。