.


KATOから20系寝台車が再生産されましたので、早速ナハネ20を2両増備しました。


外からも寝台の様子がよくわかるナハネ20
前回再生産されたときに、20系寝台車セットとあわせて単品を1両づつ揃えました。その結果、ややナロ系が多くなってしまいましたので、今回はナハネだけ増備しました。これで少しはバランスが取れたかと思われます。


今回のナハネの車番 今回版(左)と前回版(右)
車番は前回と同様の81でした。見た目にほとんど差異はなく、一緒に置いたら、どっちだか区別がつきません。ただ、車輪は変更になったようで、前回版はローフランジでしたが、今回は元に戻ったようです。あまり上手く撮影出来ませんでしたが、下に車輪の比較をのせます。左が今回増備した車両で、右が前回版です。


弊社線ではローフランジ車に相当泣かされましたが、何とか頑張り、今ではどの車両も問題なく走行しております。

KATO マグネ・マティックカプラーに換装したEF66-54 TOMIX
最近、やたらとカプラー交換に熱中していますが、無謀にもKATO マグネ・マティックカプラーに挑戦してみました。見た目はとても格好良いのですが、結論から言うと、難しい、できませんでした・・・


暇さえあれば、チョコ、チョコといじっていました。切ったり貼ったりして、取り付けることは出来たのですが、KATOのマグネット線路上でカプラーが回転しません。今のところ大・失・敗!


上手く換装できたとしても、今度はTOMIXのレイアウトにどうやってKATOのマグネットを敷設するのか、という難題が横たわっています。
でも実現できたら、機回しができるようになるだろうなぁ、と今日も頭の中で思い浮かべては、カプラー片手に悪戦苦闘しております。
関連記事
・ED75 700番台 ナックルカプラー化に挑戦 - TOMIX
・EF66-54号機 入線 - TOMIX
・EF66-54号機 パート2 - TOMIX
・EF66-54号機 をメークアップ - TOMIX

KATOのナックルカプラーを装備したTOMIX銀河オハネフ
TOMIXのEF65PFを無事ナックルカプラー化することが出来ましたが、問題は客車側をどうするかです。ご承知の通り、TOMIXのアーノルドカプラー部にはフタがついており、外から内部が見えないようになっています。実はお恥ずかしながら、小生これまで一度もこのフタを外したことがありませんでした。何というか「聖域」のように考えており、外してはいけないところと認識していました。

TOMIXのカプラー部にはフタがついている
端の方に「止め」がありますので、勇気を出して外してみました。

ドライバを使って開けてみる
恐る恐るだったので、ちょっと手間取りましたが、何とかバラせることが出来ました。


内部をバラしたところ 使えそうな空間
上の赤丸の部分を如何に活用するかですが、差し当たり「つばめ用」のナックルカプラーを差し込んでみました。すると、意外にもすんなりと無加工で綺麗に収まりました。折角なので、スプリングも入れてみたところ、調子良さそうです。


つばめ用のナックルカプラー そのまま入る
ちょっと拍子抜けしてしまいましたが、復元してみました。これで、銀河オハネフのナックルカプラー化は完成でしょうか?上手く事が運んでいるときほど疑うべきでしょう。

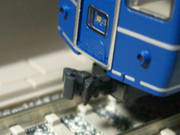
アーノルドカプラー ナックルカプラー
早速EF65PFと連結させてみましたが、問題ないような感じです。


本線に出場させてみました。弊社線の最小半径はR243(TOMIX)ですが、その場所での様子です。ぶつかり合うこともなく、さよなら銀河フル編成も難なく仕業をこなしました。


ただ、カーブで自然解放してしまうことがありましたので、オハネフ側のナックルカプラー部の裏(下の写真の赤四角の部位)に接着剤をほんの少し落とし、カプラーの開口部を固定しました。その結果、自然解放も起きなくなっています。

赤四角の凹んだ部位に接着剤をほんの少し落とす
どうすればいいのか、不安でしたが、思い切ってやってみたら意外と簡単に取り付けることが出来ました。KATOのナックルカプラーが標準装備になりそうな勢いです。
関連記事
・速報 KATO EF80 にTOMIX自連形TNカプラーを取り付ける
・C57-135号機 ナックルカプラー化に挑戦 - TOMIX
・ED75 700番台 ナックルカプラー化に挑戦 - TOMIX
・EF65PF(下関) ナックルカプラー化に挑戦 - TOMIX
・TOMIXにKATOカプラーを換装
・EF15 ナックルカプラーを装着 - TOMIX
最近、KATOのナックルカプラーにはまってしまい、試しにTOMIXのEF65PF(下関)を換装してました。


ナックルカプラー化したTOMIXのEF65PF
模型店でKATOのASSYパーツがあったので、黒と灰色二色とも購入しました。黒色だけ、EF66前期型と記載してありますが、特に差異はありません。


まずは、EF65についていたカプラーを取り外し分解します。マグネットとアーノルドは使いません。


TOMIXのカプラー部の下側にKATOのナックルを差し込んでみました。わかりやすいようにナックルは灰色を使うことにします。

この状態でも抜けにくい感じがありましたが・・・
長編成の牽引も考慮して、しっかりと保持することを考え、前回使ったつばめ用のナックルカプラーに付属していた台座部品を使うことにしました。


TOMIXのカプラー部 つばめ用の台座部品
赤丸の支柱を活用して、カプラーを強固(?!)に支える構造にします。つばめ用台座には支柱をささえるための穴が空いていませんので、ピンディバイスを用いて直径0.8mmの穴を開けました。また、そのままかぶせてもTOMIXのカプラー部と幅があいませんので、つばめ用台座の両端にある段差を目安にしてそこをニッパで切断しました。


穴の位置は適当です つばめ用台座と幅があわない

両端の赤丸部を適当に切り取る
幅は合いましたが、今度は高さが合わないので、TOMIXのカプラー部の一部をやはり適当に切り取ります(どうせ隠れて見えません)。また、とつばめ用台座も「しっぽ」を切り取りました。


それぞれ赤丸の部分を切断します。
支柱と穴をあわせてはめ込みます。


両者を併せる
この時、しっかり穴に入れ、上に若干の空間を確保します。TOMIXのカプラー部上側に突起があり、空間がないときっちりと合いません。この突起を削る方法もありますが、突起部がしっかり上から押さえる役割果たしていることを考慮して活かすことにしました。


赤丸の部分に空間を設ける 干渉する突起部分
上側を取り付けて復元すれば完成です。KATOのつばめスハ44と連結させてみましたが、特に問題ありませんでした。色違いになってしまいましたが、アーノルドの状態の写真ものせてみます。


完成したナックルカプラー


アーノルドカプラー ナックルカプラー
結構良い感じになったと思っています。実際につばめスハ44も牽引させることができました。しかし、さすがにEF65PFにつばめは似合いません。狙いはやはり・・・客車編については次回ご紹介致します。

関連記事
・速報 KATO EF80 にTOMIX自連形TNカプラーを取り付ける
・C57-135号機 ナックルカプラー化に挑戦 - TOMIX
・ED75 700番台 ナックルカプラー化に挑戦 - TOMIX
・銀河をナックルカプラー化 - TOMIX
・TOMIXにKATOカプラーを換装
・EF15 ナックルカプラーを装着 - TOMIX
先日、四国・松山駅のキヨスク売店で思わず記念にとDF50を2両購入しました。売店前のチラシに目がとまり、お店の人に尋ねたら、「はい、こちらです」と棚に案内され、何とも愛くるしい造形でしたので、迷わずゲットしてしまいました。


DF50現行塗色 登場時塗色
今回購入したTAKARA TOMYのDF50は、Nゲージではなく「チョロQ」です。線路の規格があわないため、弊社線内では走行させることが出来ませんが、パワーパックや電力を特に必要とせず、線路外で元気良く走行します。折角なので、簡単にファーストインプレッションをお届けします。
まずは、車体を模したデザインの外箱です。中が確認できるよう窓がついています。


パッケージ表面
裏側には車体全体のイラスト共に、車両の説明文があります。しかも両者の違いがきちんと説明されており、親切な作りになっています。


一部を拡大したところ


一般現行塗色も登場時塗色も共に同じ作りですので、一般現行塗色を用いて細部を見てみます。まずは、カプラーからですが、Nゲージと異なり独自のものが装備され、ナックルのような形状をした固定式です。しかし、重連も可能なようにきちんと連結させることができます。


DF50のカプラー 重連させたところ
ヘッドライトは点灯しませんが、程良い色で着色されており、点灯してるかのような鮮やかな色合いです。ごく一般的なNゲージの各種機関車同様、テールランプは非点灯です。

色鮮やかに点灯しているヘッドライト
屋根周りを見てみます。取り付けるパーツ類はありません。どれも一体形成ですが、きちんと作りわけされています。特にホイッスルなど金色で塗装されており、また、屋根の小窓なども表現されています。


取り付け済みのホイッスル 屋根周り


デフォルメされているが、雰囲気は十分
また、正面の手すりなども既に取り付けられていますが、チョロQらしい可愛らしい表現です。


手すりの形状まできちんと表現
側面ですが、車体長が短いので、ぎっしり詰め込んだ感じがしますが、これも違和感は感じられません。


DF50のサイド(撮影の関係で画像が多少歪んでいます)
それよりも驚くことに、ナンバー等がしっかりと印刷標記されています。かなりの力作かと思われます。

インレタではないが、しっかり記された標記類
足回りですが、独特の台車構造になっており、車体と一体成形されています。車体を後ろに引っ張り、手を離すと走行するタイプなので、致し方ないところでしょうか。


最後に、DF50の走行シーンですが、単機と重連させたものを紹介します。ややスローが苦手なようですが、加速性能は非常に高いように感じられました。一方、重連ですが、心配した協調も難なくこなし、力強い走りを見せてくれました。
電気を使わないエコライフにふさわしい機関車かと思われます。旅の記念として、いつまでも弊社線のそばを走り続けることでしょう。

DF50単機の走行シーン(約0.3M) DF501.wmvをダウンロード

DF50重連の走行シーン(約0.3M) DF502.wmvをダウンロード
※現在、動画配信は行っておりません
余談:翌日、四国内の別のキオスクで、この2両がセットになったものが売られていました。それには、機関車2両と別にDF50の写真カードが2枚入っている特別セットでした。既に単品で購入してしまったので、さすがに買えませんでした・・・