昔の銀塩写真のデジタル化画像シリーズの続き(第13弾)です。
大学進学で親戚等からいただいたお祝い金と初めてのアルバイトで得た僅かな稼ぎを合わせた軍資金で、赤道儀の
モータードライブ装置(日周運動によってズレていく星を電動追尾するためのアイテム)をゴールデンウィークにGet。
メーカーの当時のカタログや広告等に掲載されていた機材写真と同じ仕立てになりました。

『月刊 天文ガイド』の広告ページより抜粋
ちなみに、購入したのは単2乾電池4本で動作するタイプだったので、いずれ運転免許を取得したらクルマで空の暗い
場所へ行って天の川とかを撮影したいなぁーなどと妄想も広がっていくのでした。
で、入手直後にとりあえず試運転ということで、赤道儀への取付に少し手間取りながらも、自宅前にて2晩に渡って
惑星の強拡大撮影を敢行。まずは木星を狙って何コマか撮った中で最もマシな画像はコレでした。

【木星】
拡大撮影用カメラアダプター+Or5mmアイピース使用,F180,露出1秒
以前の撮影で拡大率不足を感じていたので、手持ちの接眼レンズで最も焦点距離の短いものを用いて撮影しました。
もちろんモータードライブを動作させた状態で撮りますが、モーターの仕様上、1.6倍速までしか出せなかったんで、
カメラのファインダーを覗いて写野内に目標の天体を導入する時にはクラッチ機構を用いて一時的にモーター駆動を
解除し、手動ハンドルで操作する必要がありました。その辺の操作に煩わしさを感じましたが、写野中心へ導入後に
モーター駆動を再開してからは木星がそのまま真ん中に居座ってくれるので連写が楽になりました。また、高拡大率
の条件で撮影する場合はピント合わせが大変で、モーター無しの時はファインダー視野内から逃げていく星を手動で
頻繁に引き戻しながらフォーカス調整する必要があったので、その操作から解放されたことにも有難みを感じました。
次に撮影したのは火星でした。
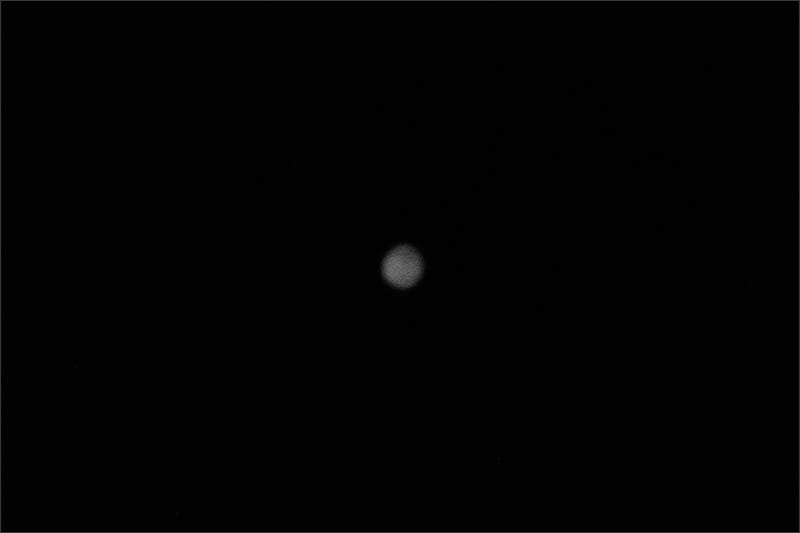
【火星】
拡大撮影用カメラアダプター+Or7mmアイピース使用,F128,露出1秒
火星は木星より暗いので、焦点距離の少し長いアイピースを使って合成F値を低くし、露出時間が短くなるようにして
撮影しました。この年の火星は小接近レベルで視直径があまり大きくなかったため、得られた像は随分と小さくて、
表面の暗色模様が微かに確認できる程度に終わり、火星撮影の難しさを痛感しました。
最後は土星の撮影で締めくくり。

【土星】
拡大撮影用カメラアダプター+Or7mmアイピース使用,F128,露出4秒
土星は火星より暗く、同じ合成F値で適正露出が4秒でした。モーター駆動無しでは日周運動でブレる露出時間ですが、
環が意外としっかり分かるイメージになってくれて、やっぱり電動追尾の威力は凄いなーって感じたのでした。
なお、共通撮影データは次のとおり。
カメラ:キヤノンEF
望遠鏡:タカハシ13cmパラボラニュートン反射
フィルム:ネオパン400(ASA/ISO400)
架台:タカハシ90S赤道儀使用(電動追尾)
※いずれの画像もトリミングをしています。









