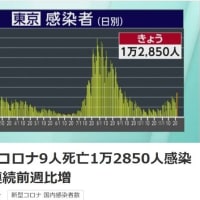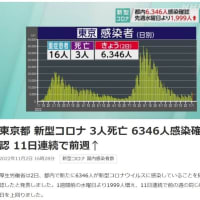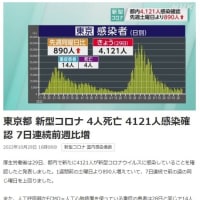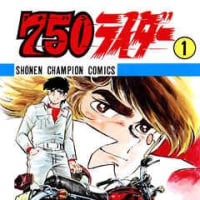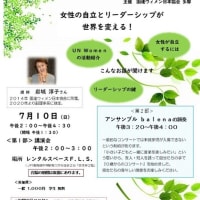語り部活動「あと5〜10年」 戦後77年、記憶継承難しく
2022/08/14 17:49
(毎日新聞)
第二次世界大戦の終戦から15日で77年を迎える。戦禍の記憶継承が年々難しくなる中、戦争を知る世代の人たちはあと何年、自身の体験を語ることができるのか。空襲などで民間人1万人以上が亡くなった7都府県の語り部団体に取材したところ、半数が「あと5年」と回答した。残された時間が少なくなる中、活動を次の世代に引き継ぐ取り組みも行われているが、先は見えない。
東京大空襲・戦災資料センター(東京都江東区)などの資料によると、1万人以上が亡くなったのは東京、愛知、大阪、兵庫、広島、長崎の6都府県。これに地上戦で住民約9万4000人が犠牲になった沖縄県を加えた。取材したのは、平和資料館などが主宰する各都府県で最大規模の8団体(東京都2団体、6府県は各1団体)。回答は文書で得た。
戦争を知る世代はあと何年、語り部活動を続けられるのか。東京、広島、長崎、沖縄の4団体は「あと10年」と回答。東京、愛知、大阪、兵庫の4団体は「あと5年」だった。
広島平和記念資料館(広島市)は「現在、証言を委嘱している被爆者32人の平均年齢が85歳(6月10日現在)。あと10年が一つの時期と考えられる」。神戸空襲を記録する会(神戸市)は「子供の頃の体験や親から聞いた話を伝えられる世代でも80、90代。あと数年と考えている」とした。
証言活動を子や孫の世代に継承できる見通しは、8団体のうち6団体が「ある」とした。ただ、市の事業として被爆証言の継承者を募っている広島、長崎両市以外は民間の取り組みがほとんどで、担い手探しに苦労している。東京大空襲・戦災資料センターは「現在、継承実践案を固めている段階」で先行きは不透明。ピースおおさか(大阪市)は継承の見通しが「分からない」とした。
とりわけ被害が大きかった7都府県では語り部の掘り起こしも積極的に行われてきた。それでも残された活動期間が「あと5〜10年」ということは、有志が草の根で取り組んできたような小都市は一層の窮状が見込まれる。帝塚山大の末吉洋文教授(平和学)は「そもそも語り部が少ない地方都市では、今後の活動が更に難しくなるだろう。インターネットで体験記を読んだり語り部の動画を閲覧したりできるよう、デジタルの力を活用した継承を検討するのも手だ」と話す。【山口桂子、中里顕】