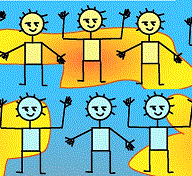
きのうの朝日新聞の教育面に、『高校の国語、文学を軽視? 2022年度からの新指導要領に懸念』というインタビュー記事があった。意見を述べているのは、大滝一登(文部科学省の視学官)と安藤宏(日本近代文学会理事、東大教授)である。
両者とも「国語」という教科の存続を前提とした話であって、私は高校に「国語」という教科があること自体に疑問をもつ。「国語」は小学校では必要な教科であるが、高校ではもはや必要がないと思う。「国語」のかわりに「日本文学」や「コミュニケーション学」や「言語学」という教科があれば、良いのではないか。それとともに、検定「教科書」を廃止すべきである。
「国語」という教科の問題は、ことばを教える装いをしながら、じつは、情緒教育、人格教育、社会道徳教育だったりする。すなわち、「国語」教育は洗脳教育になりやすいのである。しかも、現実の教科書は文部科学省の検定を受ける。また、その教科書の理解度をはかるという名目でテストを行い、子どもたちのもつ個性を奪っているのである。
大滝は、グローバル化の予測不可能な社会では、「多様な他者と共同して課題を解決することや様々な情報を見極める力が今より求められます」と言う。
なぜ、これを教える教科を「国語」というのか。「他者と共同して課題を解決する力」や「様々な情報を見極める力」は、本来「国語」という教科とはべつのものではないか。これらの力は、どのようにすれば身につくのか、また、身についたと判定するのか、文部科学省と教科書会社に任すのではなく、みんなでおおやけに議論すべき問題である。
また、大滝は「求められる」と言うが、誰が求めるのか。具体的には何を求めるのか。
自民党が経団連が日本政府が求めるからであってはならない。
教育とは、教育を受ける者にとって利益になるモノでなければならない。例えば、日本以外で教えられているライフスキル教育は、弱い者が強い者に負けないようにするにはどうするかを教える。また、高卒で働く場合もあるから、被雇用者が自分の身を守るのに、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法がどう役立つのか、法的権利について具体的に教えるのでなければならない。
大滝は「社会に出て会議や折衝の場面で小説や物語、詩歌をそのまま使うわけではありません」と「文学に偏った国語」教育を批判する。そして、必須科目の「現代の国語」では、「主張と論拠の関係や情報の妥当性や信頼性の吟味の仕方」を教え、また、選択科目の「論理国語」では、「論理的、批判的に考える力を伸ばし、伝え合う力を高めること」を教えるのだという。
「主張の妥当性や信頼性」は論理から出てくるのではない。ある人に妥当なことは他の人にとって妥当ではない。根底に利害の対立があるからだ。
アメリカの企業管理技術教育では、この利害が違うかもしれない集団(stakeholders)を分析し、妥協点を探る訓練をする。よくウィンウィン(win win)の関係と言うが、そんなものはない。あるなら、両者は同じ利害集団に属する。相手を押しまくるに必要な経費と妥協することの損失のバランスをはかるだけである。
大滝は、既得権益者のために、屁理屈を言っているだけである。
安藤は大滝の屁理屈に巻き込まれている。安藤の言う「異質な他者や価値観と出あい、世界を根源から問い返していく力」には私は賛成だが、これを「国語」というのはおかしい。日本語だけで考えるのではなく、他言語を使って考えることこそ、ことばに酔いしれないために、有用である。
5年前に、古代ギリシア語の辞書を用例から自分で作成したとき、ことばのもつ概念が言語によって大きく異なるのに驚いた。ことばは、社会構造の反映でもある。1つの社会のことばに頼っていては、社会を変革する思想が生まれてこない。英語でもドイツ語でも用例を集めて、著作を批判的に読むようにしている。
教育とは、教育を受ける本人にとって有用でなければならない。就職に有利な教育だけでは、いつまでもたっても「自由人」にならず、心のいじけた「奴隷のしもべ」か残虐な「ご主人様」にしかならない。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます