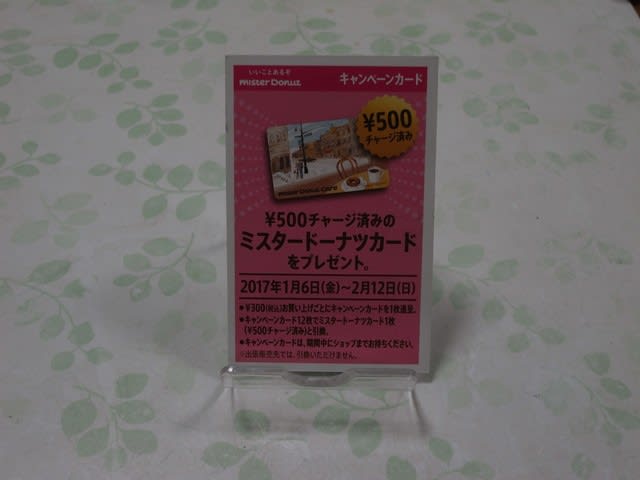昭和レトロ・はさみ
すぐに切れなくなる100均の鋏ではなくて、日本製のしっかりした鋼を使った鋏が欲しくて、手に入れました。博多鋏や種子島鋏が気になっていたのですがみつからなくて、結局昭和レトロの鋏2本です。


左から”ラシャハサミ”、右の2本、左は持っていた小さな洋ばさみ、右が手に入れたやや大きい文房具ハサミです。



ラシャバサミの刃です。キレイに研がれています。支点のリベットに何かマークが刻印されています。本来はラシャ(毛織物や布)切る洋ばさみで、これで「紙を切ってはいけない」と云われていました。でも布を切るくらいだから、紙を切っても支障はないと思うのですが・・・コピー用紙など特に切れ味が悪くなることもなく、ビシビシ切れてます。


左は、持っていた小型のハサミです。下(右)側の刃型は先端がまるくなっています。なので先端を使って細かな加工をするためのハサミではありません。右は、両方の刃先が尖っていて、先の部分まで使って切ることが出来ます。


ラシャハサミの刃の部分です。もともと刃にも錆が出ていたようですが、きれいに研がれています。現在の安価なステンレスのハサミと違って、錆の出る鋼が使われています。とにかく切れ味は、抜群です。
ただのハサミの話しですが、古いものは鋼が使われていて、切れ味が抜群です。使い続けて切れ味が落ちてきたら、砥石で研げば復活します。昔の道具は鋏も包丁も、こうして使い続けて一生ものだったんですね。
ちなみにハサミの刃を研ぐときは、上左の写真、刃の断面の部分を研ぎます。両方の刃のかみ合う面を研いでしまうと隙間ができて、切れなくなってしまいます。かみ合う面の刃先は、断面を研いで出来た刃折を軽く取る程度にします。
切れ味が落ちてきたときは、私はまずダイヤモンドヤスリの仕上げ面で軽く研いでいます。これでほとんど切れ味は復活しますが、時々は仕上げ砥石を使って研ぎ上げます。
~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~










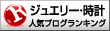









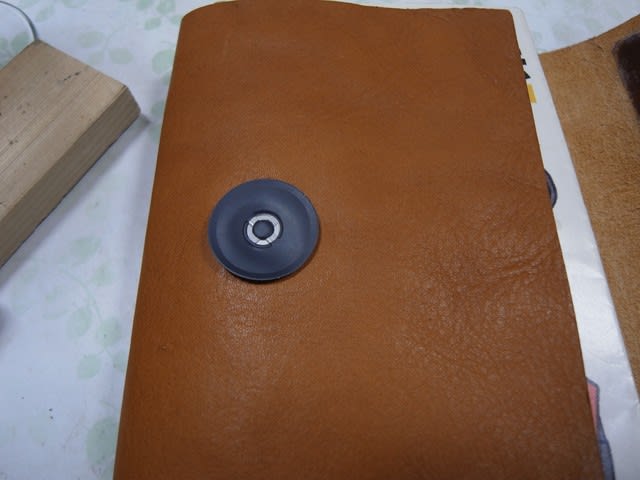







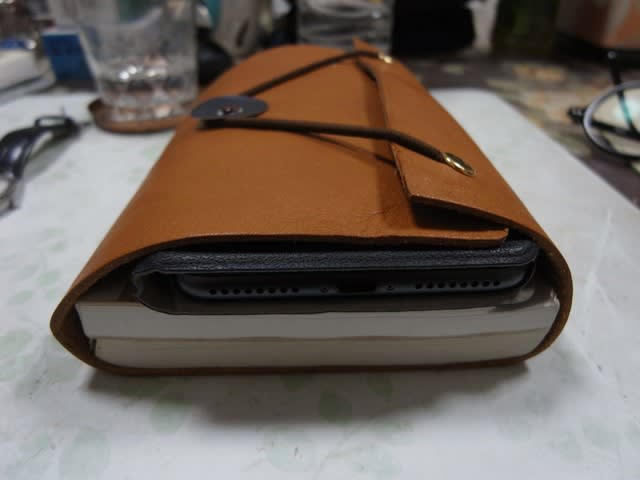
 ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~