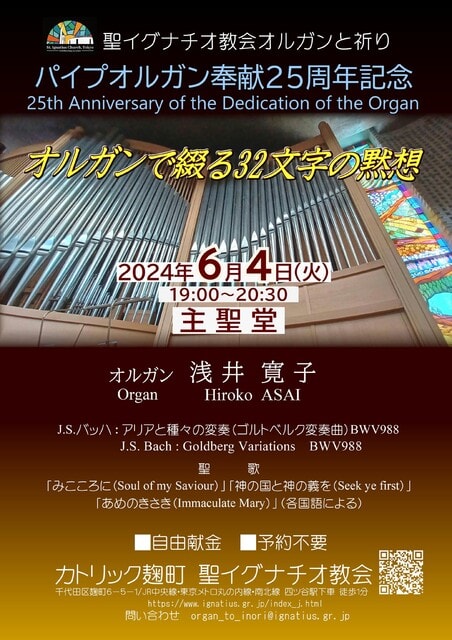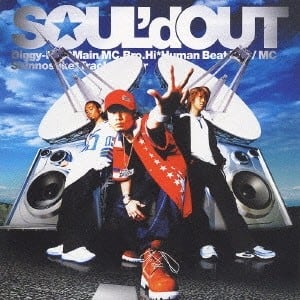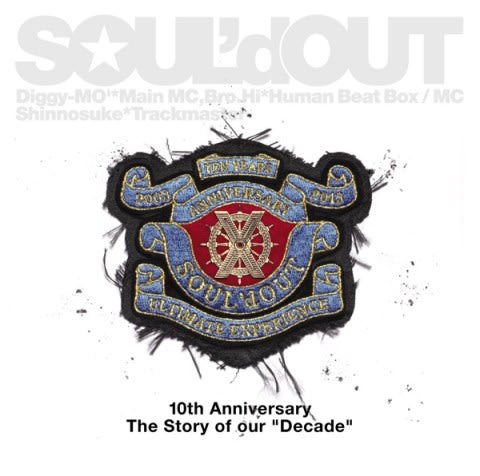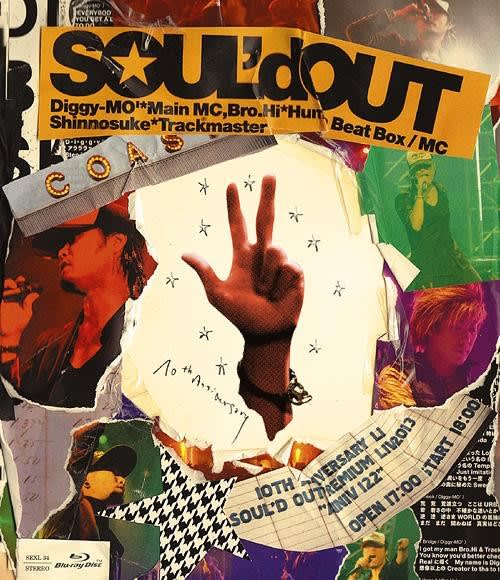「座右の銘」という言葉があります。意味を調べると
「いつも自分の座る場所のそばに書き記しておいて、戒めとする文句」
とあります。
恐らくそれから派生した造語だと思いますが
「いつも傍らにおいて何度も読み返したくなる本」のことを
「座右の書」などといいます。
哲学者、永井均さんの本は何冊か読んでいますが
最初に読んだのが『ウィトゲンシュタイン入門』です。
もう25年くらい前になるでしょうか。
人に貸したりあげたりして、その度に何度か買い直していますが
常に側にある本でした。

(永井均著/筑摩書房)
永井さんの著作の面白さを問われたら
「(立ち読みでもいいので)巻頭(通常「はじめに」と題された部分)もしくは「第一章」の冒頭数頁を読んでみてください」
と応えます。
そこに永井さんの魅力(永井節)が凝縮されており
その部分を読んでもピンとこなかったら
恐らく全編を読んでも面白いと思わないかもしれません。
「こう言うと、読者の皆さんは驚かれるかも知れないが、哲学にとって、その結論(つまり思想)に
賛成できるか否かは、実はどうでもよいことなのである。
重要なことはむしろ、問題をその真髄において共有できるか否か、にある。
優れた哲学者とは、すでに知られている問題に、新しい答えを出した人ではない。
誰もが人生において突き当たる問題に、ある解答を与えた人ではない。
これまで誰も、問題があることに気づかなかった領域に、実は問題がることを最初に発見し、
最初にそれにこだわり続けた人なのである。」
(ウィトゲンシュタイン入門「はじめに」9頁)
「いろいろな機会に何度か見かけ、あいさつ程度の会話はかわすようになっても、それほど深く気にとめはしなかった人物が、
ある日突然、自分の人生を決定するほどの重要性もって立ち現れる、そういう体験はないだろうか。
私とウィトゲンシュタインとの出会いは、そういう体験に似ていた。」
(同著「序章~出会い~」14頁)
すでに後半戦に入った人生。
「あいさつ程度の会話をかわす」誰かが、もしかしたら自分のこれからの人生に重要な何かを与えてくれる誰かかもしれません。
「いつも自分の座る場所のそばに書き記しておいて、戒めとする文句」
とあります。
恐らくそれから派生した造語だと思いますが
「いつも傍らにおいて何度も読み返したくなる本」のことを
「座右の書」などといいます。
哲学者、永井均さんの本は何冊か読んでいますが
最初に読んだのが『ウィトゲンシュタイン入門』です。
もう25年くらい前になるでしょうか。
人に貸したりあげたりして、その度に何度か買い直していますが
常に側にある本でした。

(永井均著/筑摩書房)
永井さんの著作の面白さを問われたら
「(立ち読みでもいいので)巻頭(通常「はじめに」と題された部分)もしくは「第一章」の冒頭数頁を読んでみてください」
と応えます。
そこに永井さんの魅力(永井節)が凝縮されており
その部分を読んでもピンとこなかったら
恐らく全編を読んでも面白いと思わないかもしれません。
「こう言うと、読者の皆さんは驚かれるかも知れないが、哲学にとって、その結論(つまり思想)に
賛成できるか否かは、実はどうでもよいことなのである。
重要なことはむしろ、問題をその真髄において共有できるか否か、にある。
優れた哲学者とは、すでに知られている問題に、新しい答えを出した人ではない。
誰もが人生において突き当たる問題に、ある解答を与えた人ではない。
これまで誰も、問題があることに気づかなかった領域に、実は問題がることを最初に発見し、
最初にそれにこだわり続けた人なのである。」
(ウィトゲンシュタイン入門「はじめに」9頁)
「いろいろな機会に何度か見かけ、あいさつ程度の会話はかわすようになっても、それほど深く気にとめはしなかった人物が、
ある日突然、自分の人生を決定するほどの重要性もって立ち現れる、そういう体験はないだろうか。
私とウィトゲンシュタインとの出会いは、そういう体験に似ていた。」
(同著「序章~出会い~」14頁)
すでに後半戦に入った人生。
「あいさつ程度の会話をかわす」誰かが、もしかしたら自分のこれからの人生に重要な何かを与えてくれる誰かかもしれません。