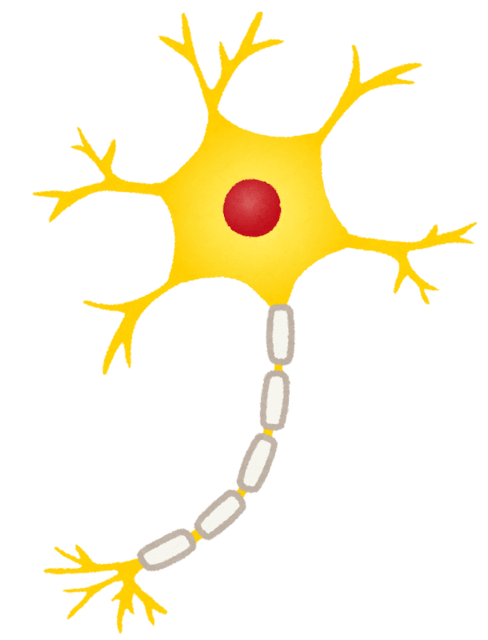2025.3.23(ヴィオラ練習30日目)
本日3回目のレッスンに行ってきました。
ヴィオラの練習を始めてから約1ヶ月が経ちました。
初日の何もわからない状態からみれば確実に"進歩"はしているとは思いますが
"一歩一歩前進"とはいかず"一進0.9退"くらいの進み方です。
前回のレッスンからの二週間、ロングトーンとニ長調の音階練習をしてきました。
ボウイングもまだまだ安定しないのですが意識すれば何とか真っ直ぐ弾けるようになってきました。
音(音量や音色)はまだちょっと安定しないのですが。
弓をきちんと持つことが基本中の基本なのですが、これもなかなか安定しません。
大きく間違ってはおらず変な癖がついているわけではないのですが
長くてそれなりに重い"棒"を摘まむように持っているので弾いているうちに"楽な握り方"にズレていってしまいます。
弾いている弦(D線かA線か)や弓の位置(根本か先端の方か)で微妙に指の角度も変わっていくようなのですが
強く持ちすぎていると柔軟性がなくなって逆に弾き辛くなるとのこと。
何事も力を抜く(余計な力を入れない)ことが大切なのですが難しいです。
音階を弾くために左指で順に弦を押さえていくのは相変わらず苦戦しています。
レ(開放弦)
ミ(人差指)
ファ(中指)
ソ(薬指)
と押さえますが、ミとファの間は全音なので結構間が空くというか中指で押さえる位置が遠いんです。
人差指でミの位置を押さえたままで中指がファの位置に届かない!
加えて人差指を固定したまま中指・薬指を独立して自由に動かすのもままならないので。
指が固く指と指(人差指と中指)の間が開かないのが原因かとも思いましたが
先生曰く「指を横に広げるのではなく前に持っていく(伸ばす)感じ」とのこと。
ピアノのように鍵盤に対して手を垂直に置くのであれば遠くの音(鍵盤)を弾くには
手(指)を広げなくてはなりませんが、
ヴァイオリン・ヴィオラの場合は指を手前(自分の方)に伸ばすような感じでしょうか。
なるほど~とは思いましたが頭でわかるのと身体がその通り動くかどうかはまた別の問題。
ですが練習する際に気を付ける点(方向性)がなんとなくわかったような気がします。
まあ、初めてやる動きなので「固い・思い通りに動かない」のは当然なので指の運動も少し教えてもらいました。
左右の手で別々の動きを同時にきちんと行うのは難しいので
・左手の音程は多少悪くても右手のボウイングに気を付けて音階を弾く練習
・右手のボウイングは多少ぶれても左手の運指に気を付けて引く練習
をそれぞれやった方がよいみたいです。
それ以外にも
・力をいれて弓を弦に押し付けるのではなく「弓の重さを弦に伝える(弓をしっかりと弦に置く)」感覚
(これは妻にも同じことを言われました)
・D線からA線に移るときは右手首の角度だけを変えるのではなく右肘を下げる
などなど。
まだまだ先は長い。

Gérard Caussé(ジェラール・コーセ)
好きなピアニスト、ヴァイオリニストを問われれば何人か挙げることはできますが好きなソロ・ヴィオリストというと難しいです。
自分が持っているCDの中でパッと思いつくのがジェラール・コーセです。
バッハ:ゴルトベルグ変奏曲(弦楽三重奏版)
フランク:弦楽四重奏曲(パレナン四重奏団)
フォーレ:ピアノ五重奏曲(ヴィア・ノヴァ四重奏団)
などの愛聴盤でヴィオラを担当しています。
本日3回目のレッスンに行ってきました。
ヴィオラの練習を始めてから約1ヶ月が経ちました。
初日の何もわからない状態からみれば確実に"進歩"はしているとは思いますが
"一歩一歩前進"とはいかず"一進0.9退"くらいの進み方です。
前回のレッスンからの二週間、ロングトーンとニ長調の音階練習をしてきました。
ボウイングもまだまだ安定しないのですが意識すれば何とか真っ直ぐ弾けるようになってきました。
音(音量や音色)はまだちょっと安定しないのですが。
弓をきちんと持つことが基本中の基本なのですが、これもなかなか安定しません。
大きく間違ってはおらず変な癖がついているわけではないのですが
長くてそれなりに重い"棒"を摘まむように持っているので弾いているうちに"楽な握り方"にズレていってしまいます。
弾いている弦(D線かA線か)や弓の位置(根本か先端の方か)で微妙に指の角度も変わっていくようなのですが
強く持ちすぎていると柔軟性がなくなって逆に弾き辛くなるとのこと。
何事も力を抜く(余計な力を入れない)ことが大切なのですが難しいです。
音階を弾くために左指で順に弦を押さえていくのは相変わらず苦戦しています。
レ(開放弦)
ミ(人差指)
ファ(中指)
ソ(薬指)
と押さえますが、ミとファの間は全音なので結構間が空くというか中指で押さえる位置が遠いんです。
人差指でミの位置を押さえたままで中指がファの位置に届かない!
加えて人差指を固定したまま中指・薬指を独立して自由に動かすのもままならないので。
指が固く指と指(人差指と中指)の間が開かないのが原因かとも思いましたが
先生曰く「指を横に広げるのではなく前に持っていく(伸ばす)感じ」とのこと。
ピアノのように鍵盤に対して手を垂直に置くのであれば遠くの音(鍵盤)を弾くには
手(指)を広げなくてはなりませんが、
ヴァイオリン・ヴィオラの場合は指を手前(自分の方)に伸ばすような感じでしょうか。
なるほど~とは思いましたが頭でわかるのと身体がその通り動くかどうかはまた別の問題。
ですが練習する際に気を付ける点(方向性)がなんとなくわかったような気がします。
まあ、初めてやる動きなので「固い・思い通りに動かない」のは当然なので指の運動も少し教えてもらいました。
左右の手で別々の動きを同時にきちんと行うのは難しいので
・左手の音程は多少悪くても右手のボウイングに気を付けて音階を弾く練習
・右手のボウイングは多少ぶれても左手の運指に気を付けて引く練習
をそれぞれやった方がよいみたいです。
それ以外にも
・力をいれて弓を弦に押し付けるのではなく「弓の重さを弦に伝える(弓をしっかりと弦に置く)」感覚
(これは妻にも同じことを言われました)
・D線からA線に移るときは右手首の角度だけを変えるのではなく右肘を下げる
などなど。
まだまだ先は長い。

Gérard Caussé(ジェラール・コーセ)
好きなピアニスト、ヴァイオリニストを問われれば何人か挙げることはできますが好きなソロ・ヴィオリストというと難しいです。
自分が持っているCDの中でパッと思いつくのがジェラール・コーセです。
バッハ:ゴルトベルグ変奏曲(弦楽三重奏版)
フランク:弦楽四重奏曲(パレナン四重奏団)
フォーレ:ピアノ五重奏曲(ヴィア・ノヴァ四重奏団)
などの愛聴盤でヴィオラを担当しています。