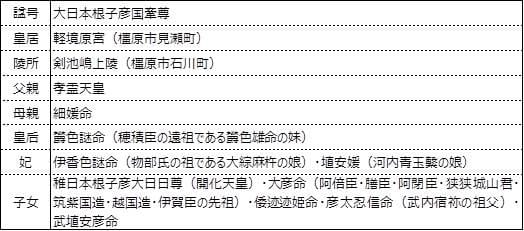さて、「古代日本国成立の物語」もいよいよ大詰めにきた。記紀を始めとする日本の史料、魏志倭人伝などの中国の史料、そして考古学の成果として明らかになっていること、これら3つの材料をもとに最も無理なく合理的に説明ができ、加えて自ら現地を訪問して見て聴いて感じたことがその説明に納得感を与えるような答を導き出す、という考え方で取り組んで神武王朝の時代まで論証を進めてきた。まだまだ解明すべき課題がたくさん残っているが、中国大陸や朝鮮半島からやって来たいくつもの渡来人集団が主役となって様々な紆余曲折を経ながら、この日本列島をひとつのまとまりある形にしようとする、その入り口までやってきた。ここまで、それなりに筋道の通った物語として成り立たせることができたのではないか、と考える。
日本書紀では神武王朝のあとに崇神王朝が成立したことになっているが、私の考えでは出雲から大和にやってきた少彦名命が纒向で崇神王朝(邪馬台国)を成立させた後、日向から東征してきた神日本磐余彦尊(狗奴国王の卑弥狗呼)が大和で饒速日命の勢力を取り込み、葛城で神武天皇として神武王朝を成立させ、この2つの王朝が並立、対立する状況(邪馬台国vs狗奴国)になった。そのため、神武も崇神も「ハツクニシラススメラノミコト」と呼ばれることになった。神武王朝は中国大陸の江南から渡来した集団に由来する政権であり、崇神王朝は朝鮮半島から渡来した集団に由来する政権であったが、記紀編纂を命じた天武天皇は神武王朝と同様に中国江南系であったために、万世一系を演出する記紀においては神武天皇が天皇家の開祖として先に王朝を成立させたことになった。神武王朝は大和で勢力基盤を整えて崇神王朝に対して攻勢をしかけるも、四道将軍の派遣や熊襲征伐などを敢行した崇神王朝の勢力に押し返され、神武王朝と同系の応神天皇が登場するまで忍耐を余儀なくされた。このあたりについては機会をあらためて「古代日本国成立の物語(第二部)」として発信していきたい。
最後に私の仮説をもとに中国史書(主に魏志倭人伝)と日本の史書(主に日本書紀)を合体させた年表を示して締め括りとしたい。
<仮説「古代日本国成立」年表>

黒字:中国史書より、青字:日本史書より、赤字:私の仮説
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。
日本書紀では神武王朝のあとに崇神王朝が成立したことになっているが、私の考えでは出雲から大和にやってきた少彦名命が纒向で崇神王朝(邪馬台国)を成立させた後、日向から東征してきた神日本磐余彦尊(狗奴国王の卑弥狗呼)が大和で饒速日命の勢力を取り込み、葛城で神武天皇として神武王朝を成立させ、この2つの王朝が並立、対立する状況(邪馬台国vs狗奴国)になった。そのため、神武も崇神も「ハツクニシラススメラノミコト」と呼ばれることになった。神武王朝は中国大陸の江南から渡来した集団に由来する政権であり、崇神王朝は朝鮮半島から渡来した集団に由来する政権であったが、記紀編纂を命じた天武天皇は神武王朝と同様に中国江南系であったために、万世一系を演出する記紀においては神武天皇が天皇家の開祖として先に王朝を成立させたことになった。神武王朝は大和で勢力基盤を整えて崇神王朝に対して攻勢をしかけるも、四道将軍の派遣や熊襲征伐などを敢行した崇神王朝の勢力に押し返され、神武王朝と同系の応神天皇が登場するまで忍耐を余儀なくされた。このあたりについては機会をあらためて「古代日本国成立の物語(第二部)」として発信していきたい。
最後に私の仮説をもとに中国史書(主に魏志倭人伝)と日本の史書(主に日本書紀)を合体させた年表を示して締め括りとしたい。
<仮説「古代日本国成立」年表>

黒字:中国史書より、青字:日本史書より、赤字:私の仮説
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。