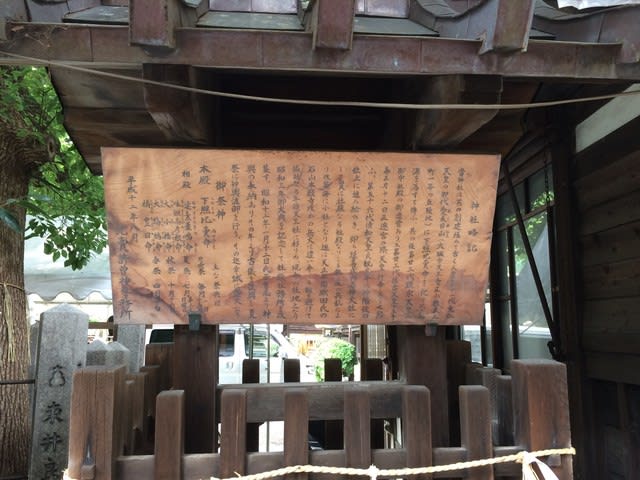天日槍の渡来ルートを考えることでその後裔一族が建設した王国の姿が見えてきたが、その拠点が但馬であった。ここで思い出すのが「丹後王国」あるいは「大丹波王国」であり、丹後に降臨したとされる饒速日命である。物部氏による先代旧事本紀に描かれた饒速日命は天日槍と似た点がいくつかある。たとえば、天日槍は渡来時に七種あるいは八種の神宝を持参し、饒速日命は天神御祖(あまつかみのみおや)から授けられた十種神宝とともに降臨した。なかでも息津鏡・辺津鏡の二面の鏡は古事記と旧事本紀で一致する。また、それらの神宝はいずれも最終的には石上神宮に収められたとされる。さらに饒速日命は東征してきた神武天皇と争うとともに、私の考えでは神武に帰順した後は崇神王朝に敵対する勢力となった。一方、天日槍は渡来時に居所をめぐって垂仁天皇に反抗の意を表したが、垂仁天皇はもちろん崇神王朝の二代目である。このように天日槍と饒速日命は重なる部分が多い。但馬を拠点にした天日槍の王国、丹後を拠点にした饒速日命の王国。和銅6年(713年)に旧丹波国から5郡が分離されて丹後国となったが、伴とし子氏はこの丹後および丹波の勢力は隣接する但馬、若狭にまで及んでいたとしてこの勢力範囲を大丹波王国と呼んでいる。
丹波が歴史に初めて登場するのは第9代開化天皇の時である。書紀では開化天皇が丹波竹野媛を妃として彦湯産隅命(ひこゆむすみのみこと)を設けたとある。古事記ではこの竹野媛は丹波の大県主である由碁理(ゆごり)の娘となっている。丹波大県主は神武王朝最後の天皇の外戚となったのだ。
また開化天皇は和珥臣の遠祖の姥津命(ははつのみこと)の妹の姥津媛(ははつひめ)を妃として彦坐王(ひこいますのみこ)を設けたともあり、この彦坐王の子が丹波道主命となる(ただし丹波道主命は彦湯産隅王の子という別伝もある)。そして垂仁天皇のとき、狭穂彦の反乱において后であり狭穂彦の妹である狭穂姫が亡くなったあと、天皇は丹波国にいた丹波道主命の5人の娘を後宮に迎え、その中の日葉酢媛が后となって景行天皇を生んだ。もしも丹波道主命が別伝のとおり彦湯産隅王の子であるなら、開化天皇の外戚となった丹波大県主の系譜が、由碁理→竹野媛→彦湯産隅王→丹波道主命→日葉酢媛→景行天皇となり、丹波大県主一族は崇神王朝の外戚にもなったということになる。ただしこの場合、崇神天皇の時に丹波道主命が四道将軍として丹波に派遣されたことと辻褄があわなくなるが、いずれが事実であるかは定かではない。
丹波が歴史に登場した開化天皇、あるいは崇神天皇や垂仁天皇のときと言えば3世紀、弥生時代の末期にあたる。この地域にはそれ以前からの繁栄を示す遺跡や遺物が多数出ている。京丹後市弥栄町の奈具岡遺跡は弥生時代中期に水晶玉の加工が行われた工房跡で、おそらく工具と思われる鉄器の生産も行われていた。同じく京丹後市の弥栄町と峰山町の境にある大田南古墳群からは青龍三年(235年)の銘が入った鏡が発掘された。峰山町には2世紀末から3世紀初めの王墓とみられる赤坂今井墳丘墓があり、数十個のガラス玉を使った頭飾りなどが出土した。また古墳時代前期には大型の前方後円墳が築かれ、網野銚子山古墳(全長198m)、神明山古墳(全長190m)、蛭子山古墳(全長140m)は日本海三大古墳と言われる。
天日槍はまさにこのような時期に渡来し、その後裔一族は近畿北部のほぼ全域にわたる一大勢力圏を築いたのだが、その範囲は前述の大丹波王国と重なるのだ。天日槍と饒速日命、あるいは但馬と丹後、両者の関係を明確に示すことはできないが間違いなく存在したであろう大丹波王国は大和の政権とは一線を画した勢力であったということは言えるだろう。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。
丹波が歴史に初めて登場するのは第9代開化天皇の時である。書紀では開化天皇が丹波竹野媛を妃として彦湯産隅命(ひこゆむすみのみこと)を設けたとある。古事記ではこの竹野媛は丹波の大県主である由碁理(ゆごり)の娘となっている。丹波大県主は神武王朝最後の天皇の外戚となったのだ。
また開化天皇は和珥臣の遠祖の姥津命(ははつのみこと)の妹の姥津媛(ははつひめ)を妃として彦坐王(ひこいますのみこ)を設けたともあり、この彦坐王の子が丹波道主命となる(ただし丹波道主命は彦湯産隅王の子という別伝もある)。そして垂仁天皇のとき、狭穂彦の反乱において后であり狭穂彦の妹である狭穂姫が亡くなったあと、天皇は丹波国にいた丹波道主命の5人の娘を後宮に迎え、その中の日葉酢媛が后となって景行天皇を生んだ。もしも丹波道主命が別伝のとおり彦湯産隅王の子であるなら、開化天皇の外戚となった丹波大県主の系譜が、由碁理→竹野媛→彦湯産隅王→丹波道主命→日葉酢媛→景行天皇となり、丹波大県主一族は崇神王朝の外戚にもなったということになる。ただしこの場合、崇神天皇の時に丹波道主命が四道将軍として丹波に派遣されたことと辻褄があわなくなるが、いずれが事実であるかは定かではない。
丹波が歴史に登場した開化天皇、あるいは崇神天皇や垂仁天皇のときと言えば3世紀、弥生時代の末期にあたる。この地域にはそれ以前からの繁栄を示す遺跡や遺物が多数出ている。京丹後市弥栄町の奈具岡遺跡は弥生時代中期に水晶玉の加工が行われた工房跡で、おそらく工具と思われる鉄器の生産も行われていた。同じく京丹後市の弥栄町と峰山町の境にある大田南古墳群からは青龍三年(235年)の銘が入った鏡が発掘された。峰山町には2世紀末から3世紀初めの王墓とみられる赤坂今井墳丘墓があり、数十個のガラス玉を使った頭飾りなどが出土した。また古墳時代前期には大型の前方後円墳が築かれ、網野銚子山古墳(全長198m)、神明山古墳(全長190m)、蛭子山古墳(全長140m)は日本海三大古墳と言われる。
天日槍はまさにこのような時期に渡来し、その後裔一族は近畿北部のほぼ全域にわたる一大勢力圏を築いたのだが、その範囲は前述の大丹波王国と重なるのだ。天日槍と饒速日命、あるいは但馬と丹後、両者の関係を明確に示すことはできないが間違いなく存在したであろう大丹波王国は大和の政権とは一線を画した勢力であったということは言えるだろう。
 | ヤマト政権誕生と大丹波王国 (中経出版) |
| 伴とし子 | |
| KADOKAWA / 中経出版 |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。