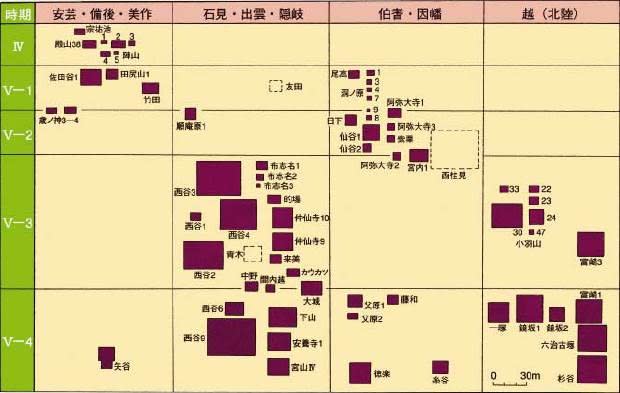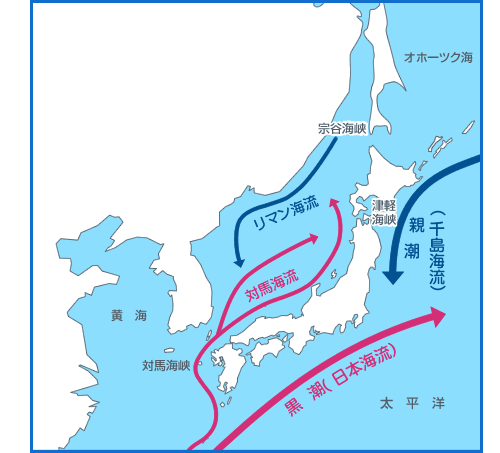日本書紀第8段の一書(第6)はさらに続く。少彦名命と別れた大己貴神はまだ未完成であった国を一人で回り、出雲の国に辿り着いたとき「葦原中国は元々は荒れ果てていた。岩から草木まで何もかも荒々しかった。しかし私が砕き伏せて従わないものはいなくなった」と言った。そしてさらに続けた。「今、この国を治めるのは私だけである。私と共に天下を治めるものが果たしているだろうか」と。その時、神々しい光が海を照らして忽然と浮かんで来る神があり「もし、私がいなければ、おまえはどうしてこの国を平定することができたと云えようか。私がいたからこそ、おまえはその大きな功績を立てることができたのだ」と言った。大己貴神が「それならばあなたは誰ですか」と尋ねると「私はおまえの幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)である」と答えた。大己貴神が「そのとおりです。判りました。あなたは私の幸魂奇魂です。今からどこに住むおつもりですか」と尋ねると、「私は日本国の三諸山に住もうと思う」と答えた。そこで宮をその地に造り、そこに坐しまされた。これが大三輪之神である。
このシーンによって大己貴神が二人に分割されることになる。一人は出雲に残って国譲りを迫られる神で、もう一人は幸魂奇魂として三輪山に移り住んだ神。前者は自らが国譲りの条件とした通りに出雲大社に祀られ、後者はこれまた自らの希望通りに三輪山に遷り住んだ。これは明らかに別の神をあたかも同一であるかのように装った話である。ここまでの流れから、出雲大社に祀られているのが素戔嗚尊の後裔で出雲の王であった本物の大己貴神であろう。とすると、三輪山に祀られているのは大己貴神ではない別の神ということになる。書紀には大三輪之神とされているので、大三輪氏が祀っていた神のことであろう。もともと三輪山には大三輪氏が祀っていた神がいて、それを大己貴神(幸魂奇魂)に置き換える意図があった。出雲からきた集団(崇神一族)が三輪の地(纒向)を支配するための手段として三輪山信仰を利用したのではないだろうか。書紀編纂を企てた天武天皇は崇神の対立勢力であった神武の系列であり、その立場からすると三輪山に出雲の神が祀られていることなど書く必要のないことであったが、書紀編纂時にその事実は周知となっていた、すなわち、三輪山は出雲の神の山と考えられるようになっていた。
古事記の同じシーンを見ると少し趣が違っている。少彦名命が常世の国に去ってしまったあと、大国主神は「どうして一人で国を作れようか。誰か一緒に作ってくれないだろうか」と気弱なところを見せる。そのときに海を照らしてやってきた神が「私をきちんと祀れば私が一緒に国を作ろう」「大和を囲む山々の東の山に祀りなさい」と言った。そして書紀では「おまえの幸魂奇魂」と名乗った神は古事記では自ら名乗ることはなく、御諸山にいる神と記されるのみである。
さて、大三輪氏あるいは三輪氏は何者であろうか。書紀の一書(第6)では、三諸山(三輪山)に住もうと言った大三輪之神の子として、甘茂君、大三輪君、姫蹈鞴五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)が挙げられている。さらに崇神天皇のとき、疫病で人民の多くが亡くなり、農民の流浪が絶えない状況になった理由を占ったときに、倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)に憑いた大物主神の言葉に従って大田田根子に大物主神を祀らせたが、この大田田根子は大物主神の子であり、三輪君の始祖となっている。これらにより書紀では「大物主神(大三輪之神)→大田田根子→三輪君(大三輪君)」というつながりがわかる。
古事記ではどうであろうか。書紀と同様、崇神天皇のときに疫病が流行した際に意富多々泥古(おおたたねこ)に大三輪大神を祀らせようとしたが、このときに意富多々泥古は大物主大神の4世孫であると答えている。書紀と世代数は違うものの、意富多々泥古は大物主大神の直系であるとされている。また、この場面では、大物主大神が夢に出て意富多々泥古に自分を祀らせよと言ったが、意富多々泥古は大三輪大神を祀ったとなっており、神武天皇の段では「美和の大物主神」と書かれていることからも大物主大神と大三輪大神は同一神であることがわかる。さらには、三輪の由来を記した場面では「意富多々泥古命は神君(みわのきみ)、鴨君の祖である」とされている。以上より古事記においては「大物主神(大三輪大神)→(3世代)→意富多々泥古→神君(三輪君)」ということになる。
記紀によれば、大三輪氏(三輪氏)は大物主神の子孫である、ということだ。では、この大物主神は何者だろうか。一般的には大物主神と大国主神は同一であると言われており、書紀一書(第6)には明示的に書かれているが、書紀本編や古事記には書かれていない。また、出雲国風土記においては大国主神が「天の下造らしし大神」や「大穴持命」として頻繁に登場する一方で、大物主神は一度たりとも登場していない。崇神天皇が祀るほどの神で大国主神と同じ神であるなら出雲国風土記が触れないはずがない。やはり大物主神は大国主神とは同一ではなく出雲の神でもなかったと考えるのが妥当であろう。
三輪山(御諸山、美和山、三諸岳ともいう)は大神神社のご神体で、大神神社の公式サイトによれば、祭神は大物主大神であり大己貴神と少彦名命が配祀されており、神社の古い縁起書によると、頂上の磐座に大物主大神、中腹の磐座に大己貴神、麓の磐座に少彦名命が鎮まる、とされている、とある。大物主大神と大己貴神が明らかに別の神として祀られているのである。大己貴神は出雲の神であるが、大物主神は出雲の神ではなく、それ以前から三輪山で祀られていた土着の神であった。だからこそ、頂上に祀られているのである。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。
このシーンによって大己貴神が二人に分割されることになる。一人は出雲に残って国譲りを迫られる神で、もう一人は幸魂奇魂として三輪山に移り住んだ神。前者は自らが国譲りの条件とした通りに出雲大社に祀られ、後者はこれまた自らの希望通りに三輪山に遷り住んだ。これは明らかに別の神をあたかも同一であるかのように装った話である。ここまでの流れから、出雲大社に祀られているのが素戔嗚尊の後裔で出雲の王であった本物の大己貴神であろう。とすると、三輪山に祀られているのは大己貴神ではない別の神ということになる。書紀には大三輪之神とされているので、大三輪氏が祀っていた神のことであろう。もともと三輪山には大三輪氏が祀っていた神がいて、それを大己貴神(幸魂奇魂)に置き換える意図があった。出雲からきた集団(崇神一族)が三輪の地(纒向)を支配するための手段として三輪山信仰を利用したのではないだろうか。書紀編纂を企てた天武天皇は崇神の対立勢力であった神武の系列であり、その立場からすると三輪山に出雲の神が祀られていることなど書く必要のないことであったが、書紀編纂時にその事実は周知となっていた、すなわち、三輪山は出雲の神の山と考えられるようになっていた。
古事記の同じシーンを見ると少し趣が違っている。少彦名命が常世の国に去ってしまったあと、大国主神は「どうして一人で国を作れようか。誰か一緒に作ってくれないだろうか」と気弱なところを見せる。そのときに海を照らしてやってきた神が「私をきちんと祀れば私が一緒に国を作ろう」「大和を囲む山々の東の山に祀りなさい」と言った。そして書紀では「おまえの幸魂奇魂」と名乗った神は古事記では自ら名乗ることはなく、御諸山にいる神と記されるのみである。
さて、大三輪氏あるいは三輪氏は何者であろうか。書紀の一書(第6)では、三諸山(三輪山)に住もうと言った大三輪之神の子として、甘茂君、大三輪君、姫蹈鞴五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)が挙げられている。さらに崇神天皇のとき、疫病で人民の多くが亡くなり、農民の流浪が絶えない状況になった理由を占ったときに、倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)に憑いた大物主神の言葉に従って大田田根子に大物主神を祀らせたが、この大田田根子は大物主神の子であり、三輪君の始祖となっている。これらにより書紀では「大物主神(大三輪之神)→大田田根子→三輪君(大三輪君)」というつながりがわかる。
古事記ではどうであろうか。書紀と同様、崇神天皇のときに疫病が流行した際に意富多々泥古(おおたたねこ)に大三輪大神を祀らせようとしたが、このときに意富多々泥古は大物主大神の4世孫であると答えている。書紀と世代数は違うものの、意富多々泥古は大物主大神の直系であるとされている。また、この場面では、大物主大神が夢に出て意富多々泥古に自分を祀らせよと言ったが、意富多々泥古は大三輪大神を祀ったとなっており、神武天皇の段では「美和の大物主神」と書かれていることからも大物主大神と大三輪大神は同一神であることがわかる。さらには、三輪の由来を記した場面では「意富多々泥古命は神君(みわのきみ)、鴨君の祖である」とされている。以上より古事記においては「大物主神(大三輪大神)→(3世代)→意富多々泥古→神君(三輪君)」ということになる。
記紀によれば、大三輪氏(三輪氏)は大物主神の子孫である、ということだ。では、この大物主神は何者だろうか。一般的には大物主神と大国主神は同一であると言われており、書紀一書(第6)には明示的に書かれているが、書紀本編や古事記には書かれていない。また、出雲国風土記においては大国主神が「天の下造らしし大神」や「大穴持命」として頻繁に登場する一方で、大物主神は一度たりとも登場していない。崇神天皇が祀るほどの神で大国主神と同じ神であるなら出雲国風土記が触れないはずがない。やはり大物主神は大国主神とは同一ではなく出雲の神でもなかったと考えるのが妥当であろう。
三輪山(御諸山、美和山、三諸岳ともいう)は大神神社のご神体で、大神神社の公式サイトによれば、祭神は大物主大神であり大己貴神と少彦名命が配祀されており、神社の古い縁起書によると、頂上の磐座に大物主大神、中腹の磐座に大己貴神、麓の磐座に少彦名命が鎮まる、とされている、とある。大物主大神と大己貴神が明らかに別の神として祀られているのである。大己貴神は出雲の神であるが、大物主神は出雲の神ではなく、それ以前から三輪山で祀られていた土着の神であった。だからこそ、頂上に祀られているのである。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました。