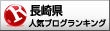25.1.22(水) 天気;晴れ 気温;3℃
朝晩は冷えるものの、日中はずいぶん暖かくなりました。 昨日は出かける際に車のエアコンを切り、少し窓を開けて運転していました。
さて、お次は布津町にある「熊野神社」です。 実は国道から見える場所にあったのですが、私は今回初めて知りました。よく見れば鳥居はありますし、こんもりした森は「鎮守の森」か。(大盛りで有名な『実吉』や布津テニスコートの近くです。)
※観察会の写真は良いのがなかったので、下見に行った時に撮影した写真を使います。

中に入っていくと境内の前に狛犬が鎮座しています。これは・・・肥前狛犬か。昨年の観察会で勉強したことが活きています。
「この狛犬には享保二十年(1735年)9月15日貝崎名 井上市兵衛と刻されています。(貝崎は地名) 享保二十年は悪疫がこの地方一帯で大流行したと言われていることから、市兵衛さんが悪疫退散を願って奉納したものと思われます。」 また、現地の看板には「寛政四年(1792年)四月朔日に起こった島原大変の大津波にも流されることがなかったことから、後世津波の守り神と伝えられた。」とあります。

境内には立派な「手水鉢」がありました。
「この手水鉢は天保六年(1835年)十二月、中通地区の青年30名が島原半島を一周して喜捨を仰ぎ、その浄財をもって奉納されたものである。ちなみにこの石は南有馬の菖蒲田石である。
石工は菖蒲田兵左衛門である。昔参拝人が手水鉢の龍が今にも襲いかかって来るようで、目をつむりながら手を洗ったということである。」
確かに見事な彫刻です。今年の干支である「蛇」が左側に彫られています。(辰・巳だ!)
布津町の有形民俗文化財に指定されていましたが、南島原市に合併する際に指定から外れたようです。

境内にはこのようなものもありました。鳥居の残骸?でしょうか。
「平成二十四年十一月十二日午前十時十五分ごろ(詳しいなw)、農家の人が過って農耕用トラクターを鳥居に接触して倒壊させるものである。
人身や付近の建物に損傷を与えなかったことが不幸中の幸いであった。
この鳥居は江戸時代の万延元年(1860年)九月、当時の庄屋 田浦長平治氏より奉納されたもので、152年になる。
大正十一年(1922年)十二月二十七日の大地震にも耐えてきたものであって、住民に親しまれた鳥居である。
ここに写真を掲げ、永遠に記念して往時を偲ぶものである。」
近くには「天満宮」もありました。

国道から熊野神社へ向かう道の手前にあったので、寄ってみました。

しめ縄は新しくなっているようですが、中はほとんど手入れされていないらしく、かなり荒れていました。