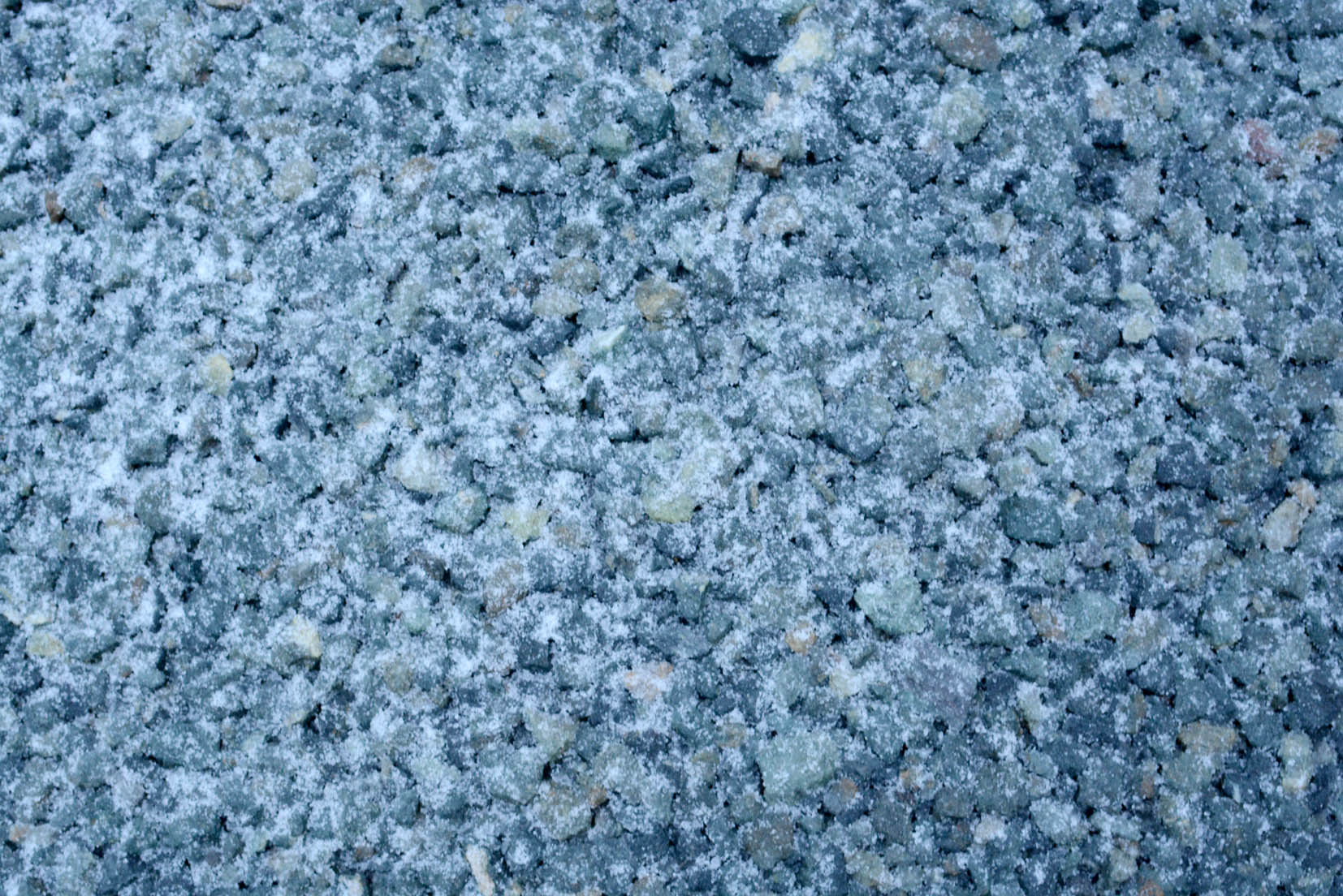ふきのとうが出ていると、あちこちで聞く。そこで探してみるとうちの近所にも出ていた。ちょうど食べ頃だ。あまり寒くなってしなびてしまう前に食べてしまおうか。

まだタンポポが咲いている。昨年と比べれば、12月の平均気温で4度高かった。1月はどうなるのだろうか。週間予報を見る限り月の半ばまで真冬日はなさそうだ。雪もない。
どうなることか。

ユキヤナギが狂い咲きしていた。バラ科の植物は剪定とかでも往々にしてあることなので、暖冬が原因かはわからない。ただ12月半ばから狂い咲いていたものがまだ咲いているということは、やはり暖かいのだ。
さてサウジアラビアについてだが、ニューズウイークで冷泉氏が「サウジ・イラン国交断絶は原油価格上昇を狙った一種のヤラセ」という記事を書いていた。あまりにも両国の対応が早すぎるというものだ。考えられるのは両国とも原油価格の上昇を狙ったものだとすればつじつまが合うというものだ。確かにそうなのだが、両国とも60ドルオーバーを狙わなければいけないのに、先物は2%程度しか上がっていない。冷泉氏にしてはセンセーショナルなタイトルだったが、後半戦そんなの狙ってどうする?といった論調になってムニャムニャしている。いずれプリンストン大学近辺ではまことしやかに言われているのだろう。
同じニューズウイーク/ロイターの記事で「サウジ=イラン関係は悪化の一途をたどる恐れ」という記事がある。なかなかにいい解説だが、問題はある。
「しかしその後サウジは潤沢な石油収入を背景に、厳格なイスラム信仰を主張してシーア派を異端とみなすスンニ派「サラフィー主義」の守護者に任じ始めた。逆にイランは1979年の革命を経て、「ヴェラーヤテ・ファギーフ(法学者の統治)」という教義を採択し、同国の最高指導者がシーア派の頂点に君臨することになった。」
この前半のサウジだが、建国以来サラフィー主義のワッハーブなのだ。建国当初石油資本をイギリスにおさえられていたからできなかったことが、鷹揚なアメリカと手を組むことで出来るようになった。特に1973年のオイルショック以降は、潤沢な資金を得てワッハーブを輸出するようになった。メッカの太守の宗派という権威だけではなく、金をかけた伝道を行った。この動きが間違いなくパキスタンやエジプトでの問題です。
とりあえずロイターの記者ですら歴史を間違えるほど、この辺りはわかりにくい所がある。

遠くで雪が降っている。
この辺りわかりやすいのはBBCのニュースだ。「イランとサウジアラビア 対立の理由は宗教なのかそれとも」はわかりやすい。宗教よりも歴史的地政学的に対立しやすい、というのがポイントだ。まず歴史から行けばペルシャ帝国はとても古いということだ。そして大シリアからインド国境まで制覇した国家の末裔だ。今でも大国であるし、文明を編み出し文化を発展させてきた自負はある。独自の言語を持ち、現在でも科学技術は見るものがある。それではサウジアラビアはといえば、石油資源以外は大きいとは言えない国だ。その上歴史がペルシャ起源のイランに比べると完璧に見劣りする。真面目にいうとイランから見たサウジアラビアは成金の田舎者で、小国なのだ。それでいてサウジアラビアはメッカの太守なのだ。トルコが田舎者のくせになかなかに偉そうなのは、両方押さえていた時期が長かったからだ。
ということでニューズウイークの酒井啓子氏のコラムが、冷泉氏のコラムの次の日に出てくるのが痛快だ。冷泉氏はどうかしていた。
「サウディ・イラン対立の深刻度」これが現時点で最も正しい。
「日本のメディアには、イラン=シーア派、サウディ=スンナ派の宗派対立との論調が相次ぐ。だが、英インディペンデント紙にロンドン大学比較哲学の教授が書いているように、「イランとサウディ間の緊張関係は宗教とほとんど関係ない」。むしろ「両国関係は地域覇権をめぐるもの」であり、「神なき世界政治の現実」だと、ムガッダム教授は言う。サウディのシーア派について2014年にThe Other Saudiを出版して、いまや世界中で売れっ子の英オクスフォード大若手研究員、トビー・マシューセンは、「ニムル師の処刑はもっぱら国内世論向けの行動」と指摘している。」
だから深刻なのだ。サウド家は今現在評判が悪い。何しろ、サウド家に近かったビン・ラディンが過激派に走って棟梁になったほどだ。ある意味身勝手な王家だ。そこがイラン革命以降慎重になっていた。だが代替わりして、革命への恐怖がもたげているというのだ。まあ当然だ。己の行いはよくわかっているのだろう。
このため宗教を盾に使っているのだろうが、自分たちでは戦いたくないので人にやらせてきた。その結果がISISではないのか。
確かに神はサウド家の盾だ。だが盾を剣と使った時から、狂ってきた。サウド家はそこの正当性を求めている可能性はある。冷泉氏の分析は、極めて甘い。

そうして昼前に北朝鮮が地下核実験をした。マグネチュードは今までで最大だが、盛岡まで伝わってくるほどのエネルギーではない。そして今回の地下核実験は成功したようで、今の所盛岡市では放射線量は上昇していない。
水爆と北朝鮮は言っているが、韓国政府のいう重水素添加のものではないのかと思う。重水素や3重水素の分離は結構めんどくさいし、液化以外で濃縮して、核爆弾を使って超高圧高温を発生して重水素と三重水素の核融合を発生させるのは、これまた古い技術とは言え、結構困難だ。ミサイル搭載型の超小型水爆というのはできるのだろうが、コストで作られていないのではないのか。水爆にしては力が少ないというのはある。
技術的にどうかというのはわからないが、北朝鮮の核実験が回を追うごとに進歩しているのは間違いがない。北朝鮮が水素添加で威力を強化する技術を持ったというのが、実は大きいかもしれない。
冷泉氏ではないが、この事件に関してマスコミの対応が異常に早い。つまり予測していたということだ。確かに今までの核実験はイベント直前だった。そして今回も金正恩将軍の誕生日の前だ。例外は一回しかないようだ。ただそれは切羽詰まった時だけのようだ。あとは予定調和的に行われる。なので2ヶ月後かその辺りにミサイルが打たれる。報道もそう言っている。
将軍様の花火なのだが、それもなんかと思う。
ただこの形式さはにはウラがある。形式的であればいいという考え方だ。儒教的なね。対中国のスケージュリングだと思う。
あれは花火なんだよ。

韓国の核装備議論が活発化するのだろうな。
ただ日本のように、核を持っていなくとも米軍が使う、核の傘という話もある。韓国もそうだったが、それを拒否した経緯がある。
そう、核の議論は自由に核を使う権利という議論だというのを、忘れてはいけない。持つことではないのだ。韓国も日本も不自由ながら核を使うことができるのが、核の傘なのだ。
でも戦略的核兵器の使用というのが、現実的になったと思う。
東証も円も、これであんまり動かないという現実を、北朝鮮はわかっているのだろうか。
じつはここがオソロシイ。