
第22回日本クリニカルパス学会学術集会(2022年11月11~12日、岐阜市)での報告

まずは背景について述べます。当地区の特徴として、大腿骨近位部骨折患者のほとんどは、管理病院である市立荘内病院へ搬送され、そのほとんどは地域にある2つのリハビリテーション病院へ転院となります。この地域的特徴を利用し、当地区ではパス協議会を設立し、大腿骨近位部骨折患者の全例登録を原則とした電子化パスを運用してきました。

マトリックス分類とは、骨折前のBIと認知症の有無で、骨折患者を6群に分類したものです。BI損失量とは、骨折前BIから観察時BIを引いた点数ですが、各群のBI損失量の推移には一定の特徴があることを先の論文で報告しました。

退院時のBI損失量を利用し、AC,BD,EF群に退院時アウトカムを図のごとく設定しました。バリアンス群と非バリアンス群を各種観察項目で比較、検定したところ、バリアンス発生と早期のBI損失量に有意差があり、術後早期のBI損失量が予後を左右するクリティカルインディケーターと考えられました。
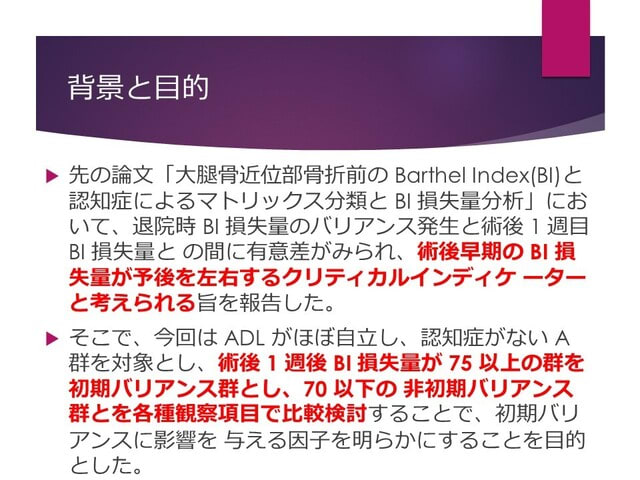
そこで、今回は ADL がほぼ自立し、認知症がない A 群を対象とし、術後 1 週後 BI 損失量が 75 以上の群を初期バリアンス群とし、70 以下の 非初期バリアンス群とを各種観察項目で比較検定することで、初期バリアンスに影響を 与える因子を明らかにすることを目的としました。

分析対象の母集団は図の通りです。2018~2019年の2年間にパスに登録された患者286例中、マトリックス分類でA群、すなわち「自立で認知症のない群」、128例を対象としました。性別、年齢、受傷前、退院時BI、急性期・回復期在院日数、術式は図のごとくです。

1 週後 BI 損失量が 75 以上を初期バリアンス群(32例)、70 以下を 非初期バリアンス群(96例)とし、急性期病院における各種観察項目で比較検定してみました。さらに、移乗開始時期が術後3日以内の群と 4 日以上の群とに分類し、術後1週目のBI損失量を比較検定しました。

結果です。非バリアンス群とバリアンス群との各種観察項目の比較検定では、術後移乗開始時期、非荷重指示、フォーレ抜去時期、輸血に有意差がみられました。

移乗開始時期3日以内と4日以上の2群間での術後1WのBI損失量の比較検定においても移乗開始時期の遅れと術後1WのBI損失量に有意差がみられました。































