
富山の二大祭りは 『おわら風の盆』と『麦や・こきりこ』



* むぎや * おわら * こきりこ *
―春の祭―
4月20日/世界遺産・五箇山相倉合掌造り集落春祭
「越中五箇山」は 平家の落人伝説と世界遺産で知られ 民謡の宝庫
蜃気楼 と ホタルイカ
4月17・18日/ごんごん祭(氷見)
雨ごいの満願成就を祝う奇祭
5月1日/御車山祭(高岡)
太閤秀吉が、御陽成天皇を京都聚楽第に迎えた時の山車を加賀藩祖前田利家が拝受。利長が京都祇園祭に倣って鉾山に改造させ、曳き回したのがはじまり。高岡名工の技術の粋を結晶させた華麗な七本の御車山がみもの。
前田家の菩提寺端龍寺は、仏殿、法堂、山門が国宝。

5月1・2日/夜高祭(福野)
慶安の昔、神明社創建の際、伊勢神宮から御分霊を奉迎したとき、夜に入ったことから各家があんどんを持ち出して倶利伽羅峠まで迎えたという故事による。世にケンカ夜高として知られ深夜に引き合い(ケンカ)がある。

5月3日/よいやさ祭(井波)
京都伏見稲荷祭の形式を伝え、金色に輝く豪華絢爛たる六基のみこしを揃いのはっぴ姿も勇ましい若衆がかつぎまわる。一基48人の担ぎ手が必要。井波彫刻の技を示す獅子頭をつけた「むかで獅子舞」もくりだす。

5月3日/曳山祭(八尾)
八尾曳山は、江戸時代の町人文化の粋を集めた彫刻山で、囃子は笛・太鼓・三味線を用いて典雅な調子を整えている。夜は、1,000余個の提灯をつける提灯山にかわる。

5月4日/奇祭牛乗式、流鏑馬式(下村・加茂神社)
五穀豊穣を祈って若者が牛を押し伏せる祭礼で、さらに除魔招福を祈って流鏑馬式<やんさんま>の行事がおこなわれる。


5月4・5日/城端曳山祭(城端)
剣鉾・傘鉾と独特の庵屋台、京都祇園祭の山車、飛騨高山祭の屋台と並び称される。豪華絢爛たる六本の曳山が御神輿を先導する古い神迎え神事を今に伝える祭礼行事。庵を所望する家ごとに山車を止め、粋な端唄を披露し、しっとりとした情緒をいまに伝える。

5月14・15日/伏木曳山祭(高岡市伏木)
別名「けんか山」「勇み山」「かっちゃい」とも呼ばれ、夜遅くまで勇ましい山鹿流出陣の太鼓ばやしとともに500個の提灯をつけた山車が町を曳きまわり、ぶつかりあう。

5月17~18日/岩瀬曳山「喧嘩山」(富山市岩瀬)
その年の世相・ニュースを判事物で表現する曳山祭。深夜、山車の曳き綱を引いて山車同士をぶつけると、土ほこりとどよめきが湧きあがり祭はクライマックス。荒っぽさは富山一。

―夏の祭―
6月・第一土・日曜日/庄川町観光祭
県内のトップをきって庄川河畔での花火大会や庄川小唄・庄川音頭の街練り、夜高あんどんなど、さまざまな行事がくりひろげられる。

六月第一金・土曜日/津沢夜高祭り
螢火が川面にうつるころ、五殻豊穣を祈って高さ7メートル、長さ12メートルにも及ぶ夜高あんどんが繰り出す。
この祭りのメインイベントは双方の夜高あんどんが2度ぶつかり合う「喧嘩夜高あんどん引き廻し」。

6月2・3日/国泰寺開山忌(高岡市)
読経とともに虚無僧の尺八大合奏は日本でも珍しい行事

6月第二金・土曜日/夜高行燈(砺波市)
散居村の砺波では田植えも終えたころ、拍子木や歌や太鼓に包まれて続く極彩色の夜高の行列は初夏の風物詩。
7月中旬~下旬/ねつおくり七夕まつり(福光)
土用の三番の日に行われるねつおくりは、「ネツ」稲のいもち病を、「ネツオクルバイ、ネツオクルバイ」と子供達が歌いはやしながら五色の短冊で飾った笹竹で稲田をはらって回り、太鼓を打ち鳴らして紙張子の舟形をかつぎ回る奇祭。

7月22~28日/虫干法会(城端町善徳寺)
年一回の虫干しで900余点の国宝級の寺宝、法宝物が一般に公開される。この期間中に奇習磐持講や蓮如太鼓曲打共演会等の催しがある。

7月22~28日/太子伝会(井波町瑞泉寺)
年に一度、国の重要美術品指定の「聖徳太子御絵伝」の絵解きが行われる。
8月上旬/富山まつり
富山市内で納涼花火大会等各種のまつりが催うされる。
8月7・8日/たてもん祭り(魚津市諏訪神社)
80余りの提灯を吊るした「たてもん」を曳き回し、海上安全と豊漁を祈願する勇壮なまつり。たてもん祭りをメインに花火大会、灯ろう流し、せり込み蝶六街流しなどがある。

8月20~30日/風の盆前夜祭(八尾町)
―秋の祭―
9月1~3日/おわら風の盆(八尾町)
二百十日の風が吹く1・2・3日、坂の町八尾は哀調をおびた胡弓の音が、夜の白むまで響き渡り、人々は踊りに酔い痴れ、小さな町はおわら一色になる。

9月4日/稚児舞(下村)
五穀豊穣を感謝して加茂神社に稚児舞を古式ゆかしく奉納する。ほほ、額に紅をさし、宝冠と平安の装束をまとった稚児は「土を踏んではいけない」の禁忌に従い、氏子に肩車されて加茂地区を一巡。笛と太鼓に合わせて「鉾の舞」「胡蝶の舞」「天の舞」など九曲を優雅に舞う。

9月14~16日/城端むぎや祭(城端)
平家の落人が唄い伝えたといわれ、国の指定無形文化財である麦屋節、コキリコ節、古代神等が唄い踊られる善徳寺境内が好い。

9月23・24日/奇祭つくりもんまつり(福岡町)
三百年前から地蔵祭が盛んで町内約20体のお地蔵さんを供養し、野菜中心に様々なものをお供えとして作り出すユーモラスな祭。H13年キ゛ャラリー

9月23~26日/こきりこ祭り(五箇山平村上梨・白山宮)
後醍醐天皇の霊祭りとして、こきりこ踊りが白山宮に奉納される。108枚の板を重ねて編んだササラは、108つの煩悩が救われるといい、信仰につながる祭りでもある。民謡の宝庫だ。
こきりこ

 むぎや
むぎや10月1日新湊曳山まつり
13本の曳山は、典雅な曳山囃子を奏でつつ荘重な軋みを響かせ、神輿渡御に供奉して曳かれ、昼は「花山」、夜は「提灯山」にしつらえ町中を練り廻る姿は、絢爛豪華そのものであり、築山が素型とされる。勢揃いすると圧巻。

―冬の祭―
・
・
・
紙芝居マンカ゛
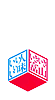
富山歩きモデル




















ご訪問下さりありがとうございます(^ ^)
残念ながら私が知っているのは「おわら風の盆」だけです。
石川さゆりがが「風の盆恋歌」を歌っていたので、余計に記憶にあったのかも知れませんが、今回読ませていただいて「おわら風の盆」の始まりがよく分かりました。
富山には賑やかなチンドン祭りもあるのですね。
昔は、私の田舎町でもチンドン屋が時々練り歩いていましたが、最近では町中で見かけることは全くありません。
この業界も時代の嵐に淘汰されて、お祭りのイベントとして披露するくらいの存在となったようですね。
「ブリ起こし」と勢いよく勇ましく筆が走っています。冬のはじまりに、雷が轟くと鰤が大漁になります。冬に雷な荒々しい字体でした。
笠を目深にかぶった女性は、まさに艶姿ですね。
(らいちゃん) へ
いま何故おわらや富山の祭なのかといいますと、ホームページ「もののはじめ」に網羅した内容を転載しているためです。もうひと踏ん張りで脱しますのでご容赦ください。m(_ _)m
「牝牡驪黄(ひんぼれいおう)」も知らぬ四字熟語でした。
今回の参院選挙は、巷では牝牡ではなく雌雄を決するほど勢力が伯仲しているわけではない風です。
若いころは政治に関心が薄かったのですが、それでもいまでいう批評票でK党に入れようかと姉に話したら止めたがいいといわれ、元々投票に行ってなかったので、その時も放棄しました。
前々回は、明らかに民主が勝つと思われたので、このときを思い起し民主以外で自民でもK党でもない党にして、その後に多くの方が後悔しているような思いにならずに済みました。(^^ゞ
先の都議選では、考えは正反対だが指示する党がないからと、今回に躍進した党にあえて批評票を投じたとインタビューに応じた選挙民がいましたが、こんな選挙姿勢はどんなものなのでしょう。
日本人は基本的にお祭りが好きな様です。
私が(井の中の蛙ですが)知っているの、「富山の二大祭りは 『おわら風の盆』と『麦や・こきりこ』
もちろん現地で拝見したわけではありませんが・・・
おわら風の盆は一度は拝見したいと思ってます。
iinaさまは、富山時代にはよくお祭りの見学や、時には参加されたことでしょう。
宮崎のビーチで・・・
グンバイヒルガオは、赤道圏に生息する熱帯性の植物が、海流に乗り
はるか北の延岡市の海岸に流れ着いて、今花開いていることに
果てしないロマンを感じます。
♪~名も知らぬ 遠き島より流れ寄る 椰子の実一つ・・・
ボクの故郷はお隣の石川県ですが、数えればお祭りはたくさんあるはずです。
今度数えてみようかな。
山にリラクゼーションを求め、それをブログに途切らさずにアップしつづけていることから、本物の山男の心意気
を感じます。
沼地や人が這入りこむのを嫌う地に、板や丸太で保護する道もこのように散見すると、その昔は尾瀬沼しか記憶
にありませんから、ずいぶんと保護が進んでいることを思い重ねます。
富山の主要な祭は、ほぼ総て体験しました。
某団体の青年部に所属したため8月の市の祭の一部をになう「おらっちゃ祭」を見直す委員会が、祭を見学しました。
たまたま同道したことから、家族にもわかちあおうと富山時代の柱に据えた次第です。
(昭和のマロ) さん へ
昭和のマロさん宅も、「レロレロ姫の警告」を85も連載しイラストを多用するなど、ずいぶんと凝っていますね。
小説を幾編も並走させ詩歌とカテゴリーを拝見すると文学系のご出身でしょうか。連載を読むのは物憂いです
が、「言葉」なら小コラム風ですから面白そうです。
太宰治の「富士山と月見草」については、きのうの新聞「日曜版」で取り上げていました。富士山が世界遺産に
登録される前の登載ですから、話題先行型でした。
富山は、祭の宝庫といわれるほどたくさんあります。中でも五箇山は平家の落人の里といわれ豪快な唄と舞が
残っています。これは能登から伝わったともいわれます。
また、東北のねだたに代表される行燈祭も、能登のあんどんが富山を経て伝承されていったとする説もあります。
石川県の祭を調べていくと、とても面白いであろうと思われます。
富山のゴールデンウィークは、由緒あるお祭りが毎日続くみたいで、地元の人は混み具合もよく把握出来て、理想的なGWが過ごせますね、羨ましい。