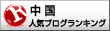←ブログランキングに参加しています。よろしかったら一日一回押してください。
←ブログランキングに参加しています。よろしかったら一日一回押してください。身体均整・木村 柔らかくソフトな整体です 整体のホームページは、こちら → ■
-------------------------------------------------
次の松山出張は12月8日(水)9日(木)です。
呉市広の整体院は通常通り営業しています。
整体予約、整体教室体験希望など0823-73-6879へどうぞ。
--------------------------------------------------
階段を歩くこと、又は走ることで体を鍛えるという場合に、その動作について体の状態を確認しましょう。
効率の良い体の使い方は、楽で長く歩ける、ストライドが広くなって早く走れるなどメリットがあります。
下の写真はよくある失敗例です。

階段を上がろうとした場合に、前にあげた足を踏み込もうとしてしまいます。緑の〇に負担がかかります。
これが一般的に多いです。そうすると大腿四頭筋(太ももの上の部分)に力をいれて、膝に無理がかかりながら
踏み込みをしてしまいます。後ろの足は前に出にくいのです。
赤が力を入れたところ。体の重さは青いライン。負担のかかっているところは緑色の〇です。

上の写真だと、後ろの足が前に行きにくいのがわかりやすいと思います。実際に試してみてください。
後ろの足が膝を曲げて前に出ません。足がそろうぐらいで止まろうとします。← ここが間違いのポイント。
重心が前に移動してくれないのです。

僕が提案していることをやってみます。上の写真がスタート。一段上に足を軽く乗せます。
踏み込もうとしません。そっと乗せます。

次に後の足を膝を前に曲げます。(膝蹴りのようなイメージ)
下の段(後ろにある足)の膝を曲げる。
膝を柔らかくまげて出すと、股関節が良く動くのです。

それによって、最初に一段上に乗せが足の膝は、力を入れなくても勝手にまっすにぐ伸びるのです。
重心も後ろの足の膝を曲げたことで前に移動しています。
歩く時の後ろ足で蹴って前に進むのではありません。自然に重心移動です。
後ろの残った足を速く膝を曲げて引き戻します。
あとは、この繰り返し。
階段上りは、後ろに残った足を曲げる、一段上の置いた足は踏ん張らず置いただけ、
後ろの足を曲げる曲げると交互にしていくと楽に登れるのです。

次に下りの間違いです。階段を下るときに頭が上下に動いている人をみませんか。
一段降りるごとにひょこひょこ跳ね上がりながら降ります。
これは、先ほどの上りと同じ理屈です。前に出した足に意識があるために後ろに残った足に体重が居着いてしまい、
膝の負担が大変で、曲げたくないというは反応を膝がするのです。

これも逆に、前に出した足よりも、後ろにある足の
かかとと 坐骨を 近づける。 これだけを意識して降りてみます。
そうすると膝が柔らかく曲がり、体重を乗せる前の足もまっすぐ立てるようになるのです。
この階段の上りと下りがうまくできるようになることが、歩くフォーム、走るフォーム、
楽で速い、疲れないということに繋がります。
痛みが出るかどうかも、フォーム次第で痛まなくなります。

もうひとつ、マラソンをするような人には、腕ふりの練習もすると思います。
止まって腕だけ降っても効果は上がりません。通常は腰幅に平行に立って、体幹が揺れ腰が揺れるように軽く
短い時間でいいと思います。
今回のは、別の意味で、腕の振りと足の動きと受信を意識するための腕ふりです。
少し腕の伸ばして降ってみます。その時に、おろした手が足のところに来たら体にパン!と触れます。
足を前後に開きます。後ろの足が膝をまげて両方の大腿がそろった瞬間におろした手が足の付け根をパンとたたきます。
右足後ろで5回、左足に変えて5回、そんな感じでタイミングを慣らします。
腕ふりの下に降りて大腿の部分を通るときに
体重がかかるように足と腕の動きがぴったりあって重心移動の楽な歩き、走りになるのです。
このポンンとを足の付け根をたたいて覚えた後は、実際の腕ふりは、早く振るために肘をたたんで振りましょう。
練習としては、すぐ上の写真の姿勢になり、下の写真のように太腿を揃う瞬間に
足の付け根をたたきます。
これは、その瞬間に体感がしっかりして
丹田に力が集まるとです。
腕振りで、拳がどこにある時が体感に力が集まるか試してみましょう。

僕が人間の体の動きとして研究して感じていることなので、一般理論とは違うかもしれませんが、
階段や、山登りもこれでするといいと思います。のぼりも下りも楽です。
最後の腕ふりも、ストライドが伸びて、足が体より前でブレーキになりにくく体感で体重を受け止めやすくなります。
 ←ブログランキングに参加しています。よろしかったら一日一回押してください。
←ブログランキングに参加しています。よろしかったら一日一回押してください。