
◆~本と歩こう㉜~◆
こんにちは。市民レポーターの 杉浦玲子 (すぎうら れいこ)です。
今回は1月27日(木)に中道公民館で行われた、歴史講座のご報告です★
講師は、市教育委員会・歴史文化財課の林部 光(はやしべ あきら)さん。
戦国~江戸時代の日記や文献などの資料から、中道地域の地名や歴史を学ぶこちらの講座には、20~70代の30名が参加しました。
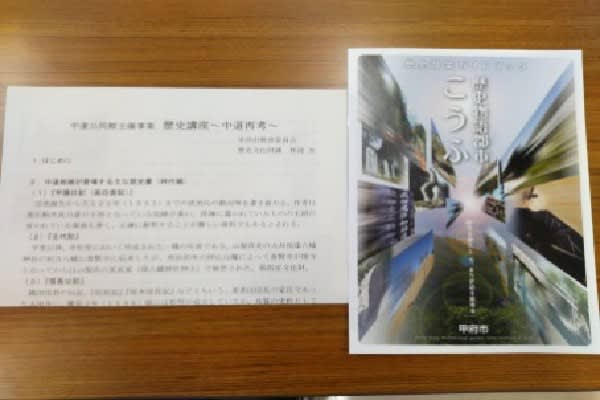
古来より、甲斐国(山梨)と駿河国(静岡)を結んでいた三つの道路。その若彦路と河内路の中間にあることから中道と言われた「中道往還(なかみちおうかん)」は、東海道から甲府盆地に至る文化の主要ルートとして栄え、戦国時代から軍道としても使用されていました。
講座では、中道地域が登場する5つの歴史書(『甲陽日記』・『王代記』・『信長日記』・『甲斐国誌』・『甲斐叢記』)から、記述部分の内容を解説。
当時の地理的な状況や、戦国武将の趨勢(すうせい)もふまえて、幅広い視点で中道の様子を知ることができました。


講座終了後、講師の林部さんは、
「県下最大の古墳や、最古の遺跡がある中道は、まさに甲斐文化の発祥の地。戦国時代から江戸、そして現代につながる中道の歴史と魅力を、たくさんの人に知ってもらいたいです」と語ってくれました。
参加者の20代の女性は、「小学校の授業で、林部さんの話を聞きました。今回、何年かぶりに中道の歴史の話を聞けてよかったです」と感想を聞かせてくれました。
戦国時代、信長の甲斐国進攻のときに家康が整備したという中道往還。江戸時代に「魚の道」、「塩の道」として山梨の文化を支えてきた中道は、現代の私たちの暮らしにもつながっているのだと感じました。
見慣れた景色も、いままでと違って見えるような。今後の歴史講座にも期待しています♪♪
~本と歩こう(32)~

※出版社の許諾を得て書影を使用しています
『縄文王国やまなし』(展覧会公式カタログ) 監修:九州国立博物館 求龍堂(2019年)
山梨県の古墳文化の原点であり、「遺跡の宝庫」ともいわれる中道地域では、数多くの土器や土偶が出土しています。
永遠に流れるような水煙紋の美しさ。さまざまな文様で表された生命のたくましさと不可思議さ。
豊富な写真と解説で、眺めるだけでも楽しめます。縄文王国やまなしへのロマンあふれる一冊です。
―取材へのご協力、ありがとうございました―
























