学校の内玄関においてある外ズック、 運動場用のくつなのですが、 サイズがちいさくなってきついというので、 次サイズのズックと入れ替えるために 一度もって帰っておいでよ、 と毎朝のように言い聞かせたり メモにしてもたせたりしてたんですが、 なかなか持ち帰ってこず。
まあたしかに いちど学校へ行っちゃったら そういうことってなかなか思い出せないかなと こんどは 次サイズの外ズックをもたせて 入れ替えておいでと送り出したんですが、 何度も そのまま もって帰ってくる・・・・
スニーカーなので けっこうかさばるし重たいし、 なんのためにもって行ってもって帰ってくるの!? そういう修行なの? 試練なの? 重いこんだらなの?
本人が言うには 入れ替えにいくタイミングがわからないらしいですが・・・・ そんなの朝登校したときに さっと内玄関行って 入れ替えればいいだけのことでしょーが!
今日またそのままもって帰ってきたら (つまり まだやっている) つぎこそは連絡帳に書いて 先生におねがいするつもりです。 もうムスメはあてにしない
とまあ こんなことでしょっちゅう親をいらいらさせるムスメ6歳。
わたしの場合、 同族嫌悪かな? まちがいなく わたしもそういう子だったので。
オットもそのあたり じぶんとちがいすぎて 反対の立場から共感するようで、 夏休み前に 登校班の男の子にムスメが叩かれるというちょっとしたことがあり 相談すると
 「・・・・どうしても ボク、 その叩く子にしか感情移入できない・・・・・ おかあさん、 はぼはそのうちかならず いじめ か 不登校 に悩むタイプな気がする。 わるいけど、 仕事についてないいまのうちに いじめと不登校の初期の対応だけでも 見聞を広めておいてくれない?」
「・・・・どうしても ボク、 その叩く子にしか感情移入できない・・・・・ おかあさん、 はぼはそのうちかならず いじめ か 不登校 に悩むタイプな気がする。 わるいけど、 仕事についてないいまのうちに いじめと不登校の初期の対応だけでも 見聞を広めておいてくれない?」
 くらいね~・・・・・
くらいね~・・・・・
 「だって ほっといたら、 おかあさんはまずはぼに 『どうしたいの?』 とか聞くだろ! ボクは そういう子どもまかせな対応が いちばんキライなんだ!」
「だって ほっといたら、 おかあさんはまずはぼに 『どうしたいの?』 とか聞くだろ! ボクは そういう子どもまかせな対応が いちばんキライなんだ!」
 ・・・・たしかに わたしはそう聞くとおもうけど・・・・・
・・・・たしかに わたしはそう聞くとおもうけど・・・・・
起こってないうちから そんなことを気にするほうがどうかとおもいますが、 ものはためしにと
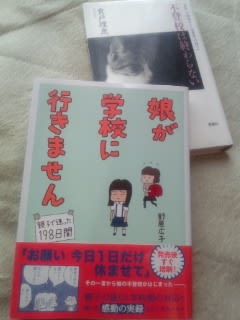
『娘が学校に行きません』 野原広子
『不登校は終わらない』 貴戸理恵
を読んでみました。
『娘が学校に行きません』 はコミックエッセイで読みやすく、 不登校になった小5の娘さんがうちのムスメにかぶりました。
たしかに、 いつどの子に起こってもおかしくないことなんだなあ~
あとがきで 学校に行けるようになった娘さんが 「学校に行けなかったころは幸せだったなぁー」 と言った、 と書いてありました。 現状が良好で 当時のことが心の中で整理できたからでるセリフですよね~
でも、 そんなに整理できていても 「なぜ不登校になったのか?」 は 本人にもわからないものなんですね。 それが 今回ちょっとおどろいたこと。
そういえば、 むかーし英会話学校で働いていたとき、 昼間よく不登校の子が通ってきていました。
親もどこか外にでられるというだけで安心するし、 レッスン中はひさしぶりにこどもから解放されてじぶんの時間をもてるし、 スクール側から見ても ふつうに仕事したり学校行ったりしてる人を呼び込めないお昼間時間に お金を落としていってくれるので、 とてもいいお客さんでした。 英語はどうでもいいので、 上達しないと文句言ったりもしないし。
慣れてくると おかあさんの解放時間を増やしてあげるために レッスンの終わった子とお茶しながら 配布用のチラシを折らせたり (お菓子がバイト料)。
それでつれづれに話をするんですが、 ある子が
「みんな 『なんで学校に行けなくなったの?』 って聞くんだけど、 とくに理由ってないんだよねえ」
って言っていて、 理由もないのに 学校に行けなくなることもあるんだ、 とフシギでした。
そうは言ってるけど ホントはいじめかなにかの気配を感じて 学校に行けなくなったのに、 その事実に向き合いたくないだけなんじゃないの? ともおもっていました。
本人が認めないうちは いじめはいじめというモンダイにならないですしね。
理由もわからず 学校へ行けなくなった子が、 理由がわからないまま ふたたび学校 (や家以外のべつの場所)へ行くことができるようになるんだろうか?
「不登校は終わらない」では、
「『不登校の理由』を語ることを拒否することは、不登校を『理解してもらう』ことへの拒絶でもある。 『心理』や『社会』の言葉で語ることで、自己の不登校を理解可能な共通の回路に落としてゆくならば、子どもにとって自己の不登校というユニークな体験は、いつか誰かが用意したストーリーの定型のなかへと、回収されてしまうだろう。 そのようにならないために、『分からない』という言葉や、端的な沈黙によって、〈当事者〉は『不登校を語ることを通して自己を語れ』とする強迫を宙づりにする。」
「このように、不登校の理由を要求するのは常に〈当事者〉ではなく周囲の大人たちである。」
だって やっぱり理由がないと こーゆー普遍化する目的をもつ論文や職業なんかは商売あがったりでしょうしねえ~
「『しかたがないですよね、ひきこもってしまったんだったら。もう、そういう天賦のものを持ってしまってる・・・・・そういうもんだってあるがままに受け入れてゆくしかないのかもしれない』」
「『もともと、そういうパーソナリティなんじゃないかな』」
う~ん、 たしかにそれが本人の実感なんだろうな~とおもいます。
そのいっぽうで 本人も 『理解したい』 とはおもっているんですよね。
「不登校が自分にとって重要なんだなと感じます。変なたとえになってしまうけれど不登校がハエ取り紙になっているんです。そして、いろいろな種類の苦しさを引き寄せているんですね。・・・・・不登校を理解することが自分をわかりやすくするように思います。なんだかずっと不登校を理由に自分を傷つけたり、苦しめたり、可能性を押しつぶしたりしてきたんだけれど、結果的にそういった苦しさは不登校に集中していて、だから、自分の中に残りつづけている不登校をきちんと理解することができれば、一気にラクになるような気がします。」
どういう落とし穴にじぶんがはまりがちなのか理解しないと こわくておちおちそのへんも歩けない、 というカンジなんでしょうか。
なんだかどんどん 不登校の 「初期の対応を知りたい」 という目的からははなれていってしまってますが、 どうも原因を根掘り葉掘りすることには あまりイミはないようだということは理解できました。
「娘が学校に・・」 の娘さんが語ったエピソードだったとおもうんですが、 みにくいアヒルの子のお話で、 いくらまわりが 「お前はじつは白鳥だったんだ! だからもう アヒルの子の群れにはもどらなくていいんだよ」 と言っても その子がアヒルにもどりたいとおもってるうちは アヒルの群れに返そうとしてやることが その子の 「ありのまま」 なのかな。
「『淵』とは、『これ以上無理をさせたら子どもがだめになる』という一線のことであると言う。『いったん淵を見ちゃったら、もうね』というその母親の言葉に、『見た見た』『私も見た』と周囲の母親たちがいっせいに同意を示したのが印象的であった。『やっぱり180度の転換を迫られるよね」と母親の一人は言った。
あらゆる手を尽くして子どもを学校に行かせようとし、『淵』のぎりぎりまで子どもを追いつめ、奈落を見てはっと気づき、踵を返す。〈親〉にとって翻身とはそうした経験である。翻身は、学校をめぐる価値について『不登校の否定』から『肯定』へと移行する意味での転換ではなく、学校をめぐる価値から目の前の子どもをめぐる価値へと、思慮の対象そのものを転換させることによって起こっている。そこにあるのは『不登校は悪くない』というよりもむしろ、『うちの子は悪くない』という転換である。」
そして 「淵」 が見えたら あわてて引き返しても まだ間に合う・・・・・ のかもしれません。
・・・・・・が、 そこまでに手を打つのが初期対応かな。
(てゆーか やっぱりこどもに 『どうしたいの?』 って聞くのが いちばんいい方法なんじゃないかって気がしてきた)
なんだか オットにおもい宿題を背負わされた気分ですが、 まあなんだ、 あらかじめ勉強してても その場になったら どうせテンパるだろうな~ って想像はつくようになったので いまから深くかんがえなくてもいいということがわかりました。
まあたしかに いちど学校へ行っちゃったら そういうことってなかなか思い出せないかなと こんどは 次サイズの外ズックをもたせて 入れ替えておいでと送り出したんですが、 何度も そのまま もって帰ってくる・・・・
スニーカーなので けっこうかさばるし重たいし、 なんのためにもって行ってもって帰ってくるの!? そういう修行なの? 試練なの? 重いこんだらなの?
本人が言うには 入れ替えにいくタイミングがわからないらしいですが・・・・ そんなの朝登校したときに さっと内玄関行って 入れ替えればいいだけのことでしょーが!
今日またそのままもって帰ってきたら (つまり まだやっている) つぎこそは連絡帳に書いて 先生におねがいするつもりです。 もうムスメはあてにしない

とまあ こんなことでしょっちゅう親をいらいらさせるムスメ6歳。
わたしの場合、 同族嫌悪かな? まちがいなく わたしもそういう子だったので。
オットもそのあたり じぶんとちがいすぎて 反対の立場から共感するようで、 夏休み前に 登校班の男の子にムスメが叩かれるというちょっとしたことがあり 相談すると
 「・・・・どうしても ボク、 その叩く子にしか感情移入できない・・・・・ おかあさん、 はぼはそのうちかならず いじめ か 不登校 に悩むタイプな気がする。 わるいけど、 仕事についてないいまのうちに いじめと不登校の初期の対応だけでも 見聞を広めておいてくれない?」
「・・・・どうしても ボク、 その叩く子にしか感情移入できない・・・・・ おかあさん、 はぼはそのうちかならず いじめ か 不登校 に悩むタイプな気がする。 わるいけど、 仕事についてないいまのうちに いじめと不登校の初期の対応だけでも 見聞を広めておいてくれない?」 くらいね~・・・・・
くらいね~・・・・・ 「だって ほっといたら、 おかあさんはまずはぼに 『どうしたいの?』 とか聞くだろ! ボクは そういう子どもまかせな対応が いちばんキライなんだ!」
「だって ほっといたら、 おかあさんはまずはぼに 『どうしたいの?』 とか聞くだろ! ボクは そういう子どもまかせな対応が いちばんキライなんだ!」 ・・・・たしかに わたしはそう聞くとおもうけど・・・・・
・・・・たしかに わたしはそう聞くとおもうけど・・・・・起こってないうちから そんなことを気にするほうがどうかとおもいますが、 ものはためしにと
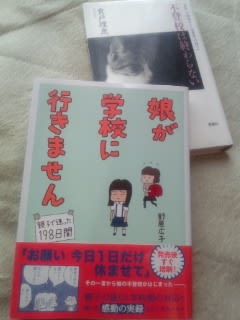
『娘が学校に行きません』 野原広子
『不登校は終わらない』 貴戸理恵
を読んでみました。
『娘が学校に行きません』 はコミックエッセイで読みやすく、 不登校になった小5の娘さんがうちのムスメにかぶりました。
たしかに、 いつどの子に起こってもおかしくないことなんだなあ~
あとがきで 学校に行けるようになった娘さんが 「学校に行けなかったころは幸せだったなぁー」 と言った、 と書いてありました。 現状が良好で 当時のことが心の中で整理できたからでるセリフですよね~
でも、 そんなに整理できていても 「なぜ不登校になったのか?」 は 本人にもわからないものなんですね。 それが 今回ちょっとおどろいたこと。
そういえば、 むかーし英会話学校で働いていたとき、 昼間よく不登校の子が通ってきていました。
親もどこか外にでられるというだけで安心するし、 レッスン中はひさしぶりにこどもから解放されてじぶんの時間をもてるし、 スクール側から見ても ふつうに仕事したり学校行ったりしてる人を呼び込めないお昼間時間に お金を落としていってくれるので、 とてもいいお客さんでした。 英語はどうでもいいので、 上達しないと文句言ったりもしないし。
慣れてくると おかあさんの解放時間を増やしてあげるために レッスンの終わった子とお茶しながら 配布用のチラシを折らせたり (お菓子がバイト料)。
それでつれづれに話をするんですが、 ある子が
「みんな 『なんで学校に行けなくなったの?』 って聞くんだけど、 とくに理由ってないんだよねえ」
って言っていて、 理由もないのに 学校に行けなくなることもあるんだ、 とフシギでした。
そうは言ってるけど ホントはいじめかなにかの気配を感じて 学校に行けなくなったのに、 その事実に向き合いたくないだけなんじゃないの? ともおもっていました。
本人が認めないうちは いじめはいじめというモンダイにならないですしね。
理由もわからず 学校へ行けなくなった子が、 理由がわからないまま ふたたび学校 (や家以外のべつの場所)へ行くことができるようになるんだろうか?
「不登校は終わらない」では、
「『不登校の理由』を語ることを拒否することは、不登校を『理解してもらう』ことへの拒絶でもある。 『心理』や『社会』の言葉で語ることで、自己の不登校を理解可能な共通の回路に落としてゆくならば、子どもにとって自己の不登校というユニークな体験は、いつか誰かが用意したストーリーの定型のなかへと、回収されてしまうだろう。 そのようにならないために、『分からない』という言葉や、端的な沈黙によって、〈当事者〉は『不登校を語ることを通して自己を語れ』とする強迫を宙づりにする。」
「このように、不登校の理由を要求するのは常に〈当事者〉ではなく周囲の大人たちである。」
だって やっぱり理由がないと こーゆー普遍化する目的をもつ論文や職業なんかは商売あがったりでしょうしねえ~

「『しかたがないですよね、ひきこもってしまったんだったら。もう、そういう天賦のものを持ってしまってる・・・・・そういうもんだってあるがままに受け入れてゆくしかないのかもしれない』」
「『もともと、そういうパーソナリティなんじゃないかな』」
う~ん、 たしかにそれが本人の実感なんだろうな~とおもいます。
そのいっぽうで 本人も 『理解したい』 とはおもっているんですよね。
「不登校が自分にとって重要なんだなと感じます。変なたとえになってしまうけれど不登校がハエ取り紙になっているんです。そして、いろいろな種類の苦しさを引き寄せているんですね。・・・・・不登校を理解することが自分をわかりやすくするように思います。なんだかずっと不登校を理由に自分を傷つけたり、苦しめたり、可能性を押しつぶしたりしてきたんだけれど、結果的にそういった苦しさは不登校に集中していて、だから、自分の中に残りつづけている不登校をきちんと理解することができれば、一気にラクになるような気がします。」
どういう落とし穴にじぶんがはまりがちなのか理解しないと こわくておちおちそのへんも歩けない、 というカンジなんでしょうか。
なんだかどんどん 不登校の 「初期の対応を知りたい」 という目的からははなれていってしまってますが、 どうも原因を根掘り葉掘りすることには あまりイミはないようだということは理解できました。
「娘が学校に・・」 の娘さんが語ったエピソードだったとおもうんですが、 みにくいアヒルの子のお話で、 いくらまわりが 「お前はじつは白鳥だったんだ! だからもう アヒルの子の群れにはもどらなくていいんだよ」 と言っても その子がアヒルにもどりたいとおもってるうちは アヒルの群れに返そうとしてやることが その子の 「ありのまま」 なのかな。
「『淵』とは、『これ以上無理をさせたら子どもがだめになる』という一線のことであると言う。『いったん淵を見ちゃったら、もうね』というその母親の言葉に、『見た見た』『私も見た』と周囲の母親たちがいっせいに同意を示したのが印象的であった。『やっぱり180度の転換を迫られるよね」と母親の一人は言った。
あらゆる手を尽くして子どもを学校に行かせようとし、『淵』のぎりぎりまで子どもを追いつめ、奈落を見てはっと気づき、踵を返す。〈親〉にとって翻身とはそうした経験である。翻身は、学校をめぐる価値について『不登校の否定』から『肯定』へと移行する意味での転換ではなく、学校をめぐる価値から目の前の子どもをめぐる価値へと、思慮の対象そのものを転換させることによって起こっている。そこにあるのは『不登校は悪くない』というよりもむしろ、『うちの子は悪くない』という転換である。」
そして 「淵」 が見えたら あわてて引き返しても まだ間に合う・・・・・ のかもしれません。
・・・・・・が、 そこまでに手を打つのが初期対応かな。
(てゆーか やっぱりこどもに 『どうしたいの?』 って聞くのが いちばんいい方法なんじゃないかって気がしてきた)
なんだか オットにおもい宿題を背負わされた気分ですが、 まあなんだ、 あらかじめ勉強してても その場になったら どうせテンパるだろうな~ って想像はつくようになったので いまから深くかんがえなくてもいいということがわかりました。


















