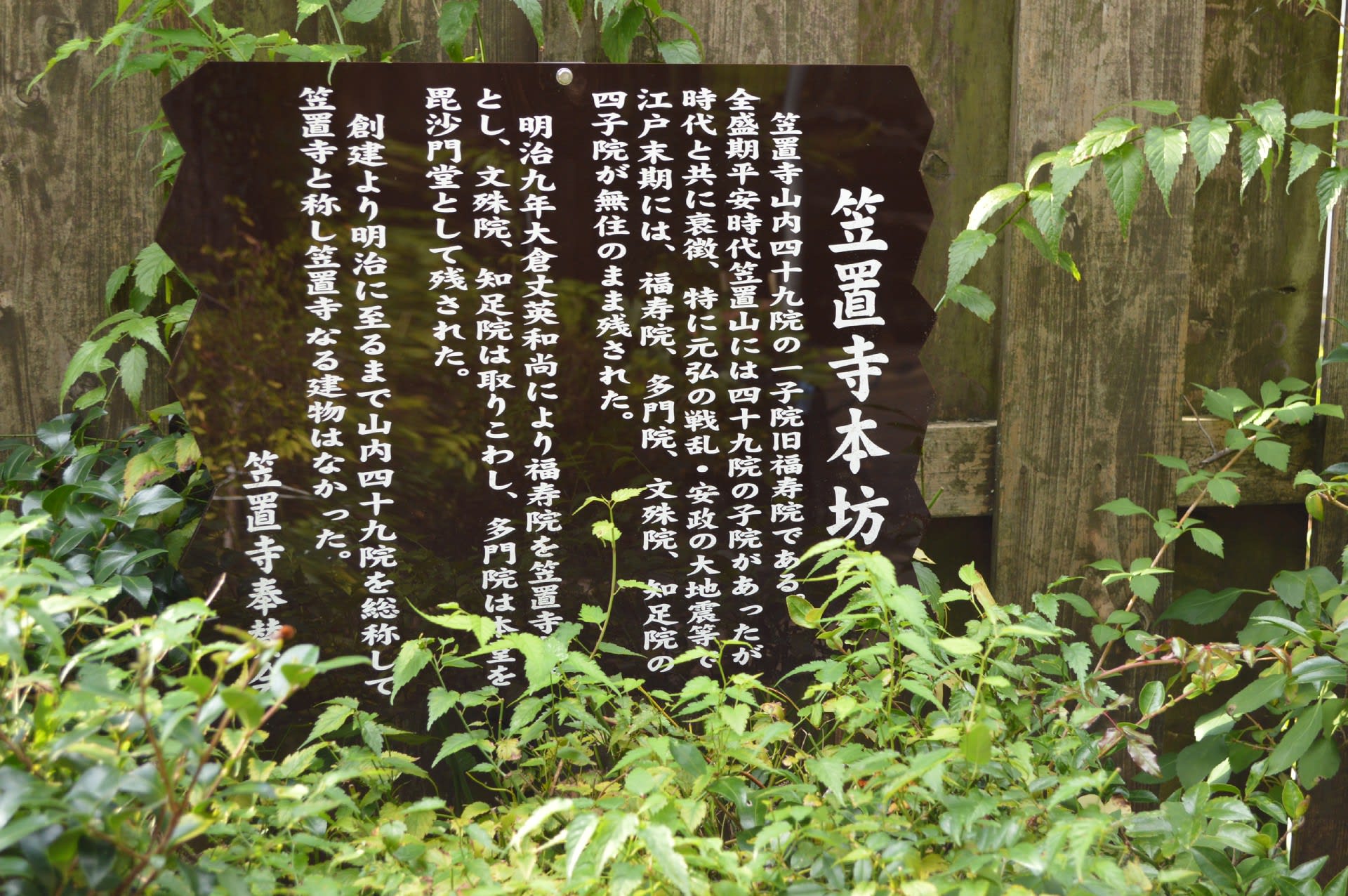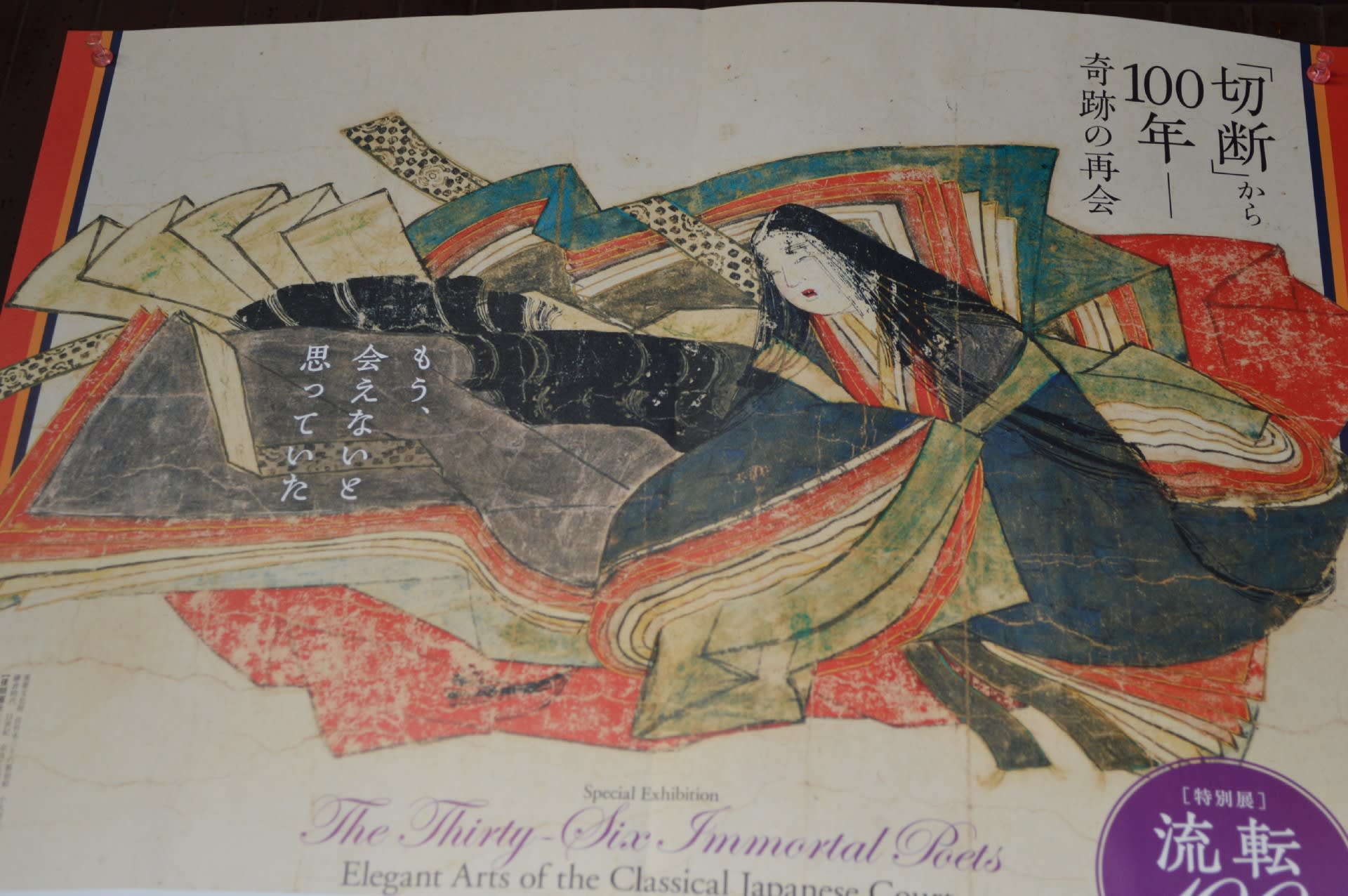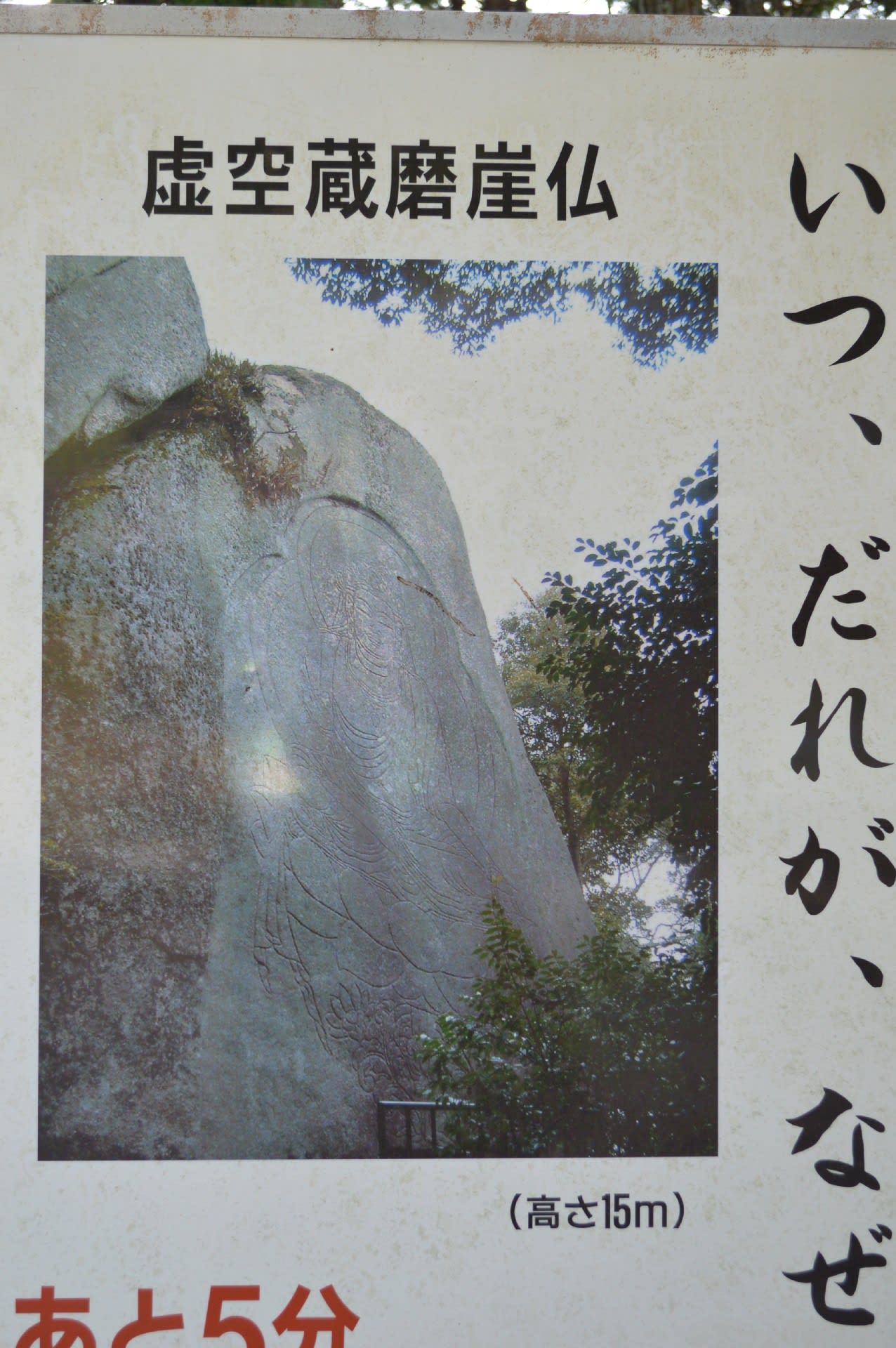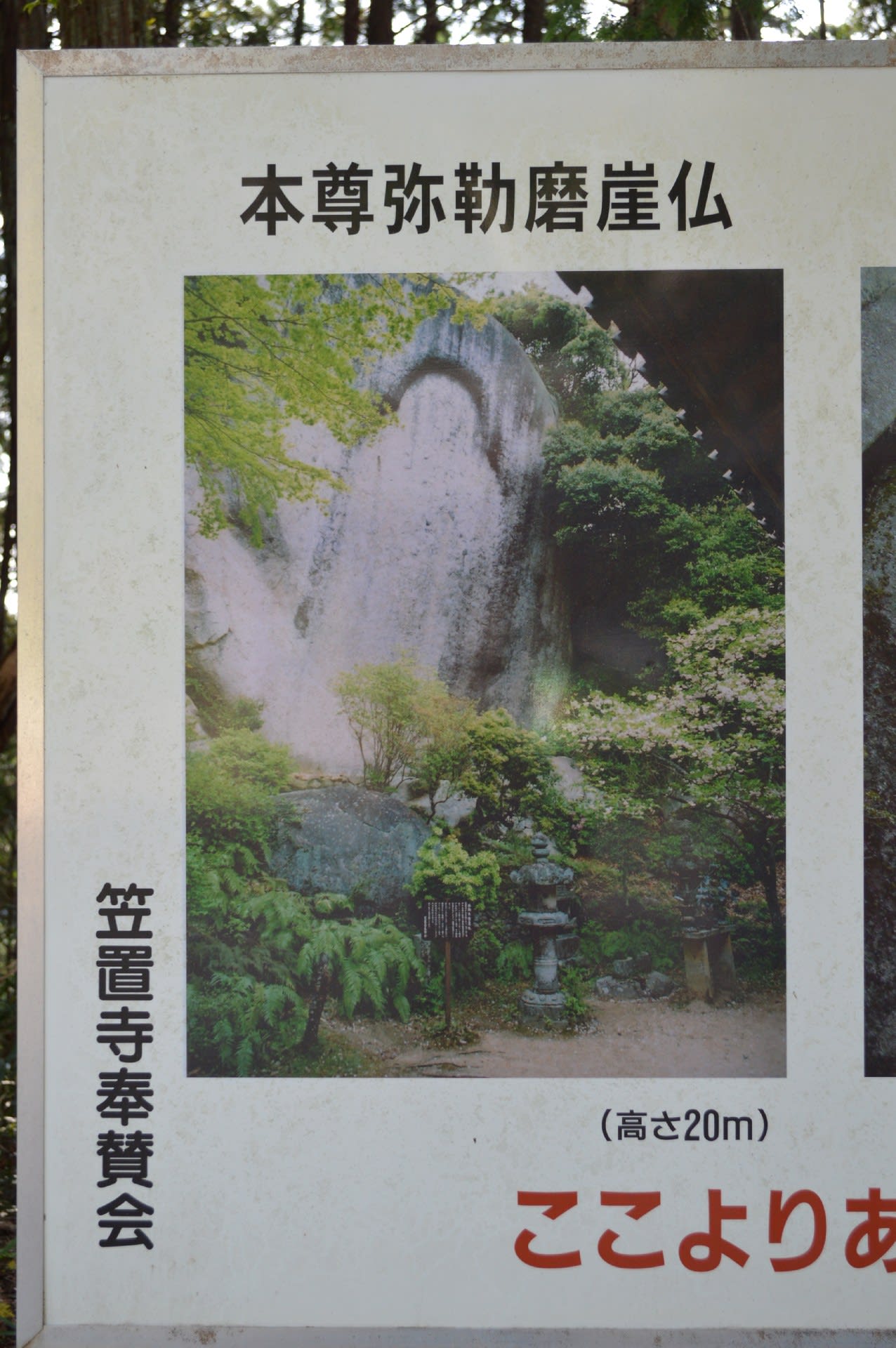- 公卿 三條実美(さんじょうさねとみ)
- 公卿 三條西季知(さんじょうにしすえとも)
安政5年(1858年)、権中納言となり重んじられるが、文久3年(1863年)八月十八日の政変により、三条実美らと長州へ下向、いわゆる七卿落ちの一人となる。その後さらに大宰府まで走り、やがて王政復古の大号令によって赦され、権大納言に復し帰洛。明治元年(1868年)には皇太后宮権大夫となった。
明治維新後、参与、教部省教導職の長官である大教正兼神宮祭主となった。
三条西家の当主だけあって歌道の宗匠として知られ、西四辻公業と共に明治天皇の歌道師範となった。季知自身は三条西家分家当主の高松公祐に師事した。 明治11年(1878年)、13年(1880年)出版の『開化新題歌集』第一編に三首、二編に二首、以下の通り歌が収められている。
- 公卿 東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)
天保4年(1833年)、東久世通徳(みちなる、1816年 - 1835年)の子として京都に生まれる。
幕末の朝廷で少壮の公家として尊王攘夷を唱え活躍した。しかし文久3年(1863年)、八月十八日の政変によって、朝廷の実権が尊皇攘夷派から公武合体派に移ると、長州藩兵に守られ、三条実美・三条西季知・澤宣嘉・壬生基修・四条隆謌・錦小路頼徳とともに船で長州へ逃れた。このことを世に「七卿落ち」という。元治元年(1864年)、長州から大宰府に移された。
慶応4年(1868年)、王政復古によって復権を果たす。1月17日に外国事務総督の1人となり、明治政府最初の外交問題・神戸事件の対応責任者となり伊藤博文と共に外国と協議。3月19日には横浜裁判所総督となった。通禧の在任した半年の間に神奈川裁判所総督・神奈川府知事と名称が変遷したこの職は現在の神奈川県知事に相当するものである。
明治2年(1869年)8月25日、第2代開拓長官に任命された。前任の鍋島直正が実務にとりかかる前に辞職したため、実質的に開拓使の事業を始動させたのは通禧である。9月21日、開拓使吏員、農工民約200人をともない、イギリスの雇船テールス号で品川を出帆。9月25日に箱館に着任した。なお、同月には王政復古の功績として賞典禄1000石を給されている。翌年、ガルトネル開墾条約事件の和解にこぎつける。
明治4年(1871年)10月15日、侍従長に転じる。この年、岩倉具視を全権とする岩倉使節団に随行し、見聞を広める。
明治15年(1882年)、元老院副議長。華族令施行に伴い、明治17年(1884年)に伯爵に叙されている。東久世家の家格は羽林家であり、本来は子爵相当であったが、明治維新における通禧の功が考慮されて伯爵とされた。叙爵の時点で功績が考慮された公家は、岩倉具視や三条実美など数少ない。
明治21年(1888年)に枢密顧問官、明治23年(1890年)に貴族院副議長、明治25年(1892年)に枢密院副議長を歴任した。墓所は中目黒の長泉院。
- 公卿 壬生基修(みぶもとおさ) 幕末・明治の公卿。庭田重基の三男、壬生道吉の養子。京都生、東京住。勤王七卿の一人。王政復古後は参与・東京府知事・元老院議員・貴族院議員・平安神宮宮司等を務めた。伯爵。明治39年(1906)没、72才。
- 公卿 四条隆謌(しじょうたかうた)
幕末期は攘夷派公卿として幕府に建言していたが、八月十八日の政変によって失脚し、長州藩、次いで太宰府に移った。このため一時官位を剥奪されている。1867年(慶応3年)12月の王政復古で討幕派が朝廷の実権を握ると京に戻って官位を復され、戊辰戦争では中国四国追討総督・大総督宮参謀・仙台追討総督・奥羽追討平潟口総督などを務め、1869年(明治2年)6月、維新の功績により永世禄300石を与えられ、同年7月に陸軍少将に任ぜられる。1872年(明治5年)1月には大阪鎮台司令長官に就任、1874年(明治7年)4月に名古屋鎮台司令長官に移るが、1877年(明治10年)5月には大阪鎮台司令長官を兼ねた(同年10月に兼職を免ぜられる)。1880年(明治13年)の仙台鎮台司令長官を経た後、1881年(明治14年)2月に陸軍中将に昇り元老院議官に就任する。1884年(明治17年)7月に伯爵、1891年(明治24年)4月に侯爵に陞爵し、貴族院議員となる。1893年(明治26年)12月、予備役。1898年(明治31年)11月薨去。
- 公卿 錦小路頼徳(にしきこうじよりのり)孝明天皇の攘夷祈願の為の石清水八幡宮行幸に随従した。同年の八月十八日の政変によって失脚し、三条実美、壬生基修、三条西季知、東久世通禧、四条隆謌、澤宣嘉と共に長州藩に落ち延びる(七卿落ち)。これによって官位剥奪の処分を受ける。
- 公卿 澤宣嘉(さわのぶよし)
慶応3年(1867年)の王政復古の後は、参与、九州鎮撫総督、長崎府知事などの要職を務め、明治2年(1869年)に外国官知事から外務卿になり、外交に携わる。外務卿として、日本とオーストリア=ハンガリー二重帝国との間に最初の条約(日墺修好通商航海条約)を締結し、国交を樹立する。 条約は、澤宣嘉外務卿、寺島宗則外務大輔とフォン・ペッツ全権公使との間で結ばれた。締結には駐日英国公使ハリー・パークスの支援があり、早期に調印されたが、片務規定が引用されており著しい不平等条約となった。 このため、明治政府の条約改正事業において、改正すべき内容の最終目標とされた。明治3年(1870年)、外務卿として各国公使に対して、条約改正について条約所定の交渉期日を待って商議を開始する旨を通告し、条約改正交渉の発端をつくった。ロシア公使として着任する前に38歳で病死した。このため、ロシア公使には急遽榎本武揚が着任することになった。

三条実美 内大臣三条実万(さねつむ)の子として京都で生まれました。
父は安政の大獄(あんせいのたいごく)で謹慎の身で死に、その後継ぎとなりました。父の志を継ぎ、攘夷の計画を遂げようと、尊王攘夷(そんのうじょうい)派の公卿として、岩倉具視(いわくらともみ)らを中心とする公武合体(こうぶがったい)派と対立しながら力を強めていきました。
しかし、1863年、26歳の時、八月十八日の政変で攘夷派が京都から追い出されると、蓑笠(みのかさ)にわらじで長州に落ち延びました。(七卿落ち)
その後、太宰府(だざいふ)に移されました。
関連記事 ⇒ 題字 寺院下0060 平等寺・因幡薬師 真言宗智山派 画像追加
まち歩き滋賀0265 明治時代の鉄道トンネル 鉄道記念物 近代化遺産

関連記事 ⇒ まち歩き上0517 京都御苑 堺町御門
時代祭 前回の記事 ⇒時代祭行列 明治維新時代 維新志士列 七卿落 先導 久坂玄瑞
次回の記事 ⇒ 時代祭行列 明治維新時代 維新志士列 吉村 寅太郎