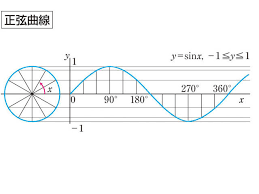米がなくなりそうだという妻からの声掛けは、買い物に付き合ってくれという合図。近頃は米を買う時だけでなく、家にこもりがちな私を連れ出して、散歩をかねての買い物とあいなる。気分転換になるし、行き帰りに思いがけない発見もあってよい。で、夫婦仲良く(?)連れ立っての散歩は、近所の評判を気にしているわけでもなく、日々のルーチンになった。この季節には他人様の庭先を眺めながら、珍しい花が咲いているのを見かけたりすると嬉しくなる。その程度の心もちの外歩きは清々しい。

▲フランネルフラワー、エーデルワイスの仲間らしい。
こんな小市民的な安穏たる平々凡々な生き方を、若いときには唾棄すべきものと軽蔑していたが、馬齢を重ねてみれば日常のありふれた安定こそが掛替えのないものになった。なるようにしかならない、それでいいのだと赤塚不二夫のように心でつぶやく。もしそこが聖と俗との分岐点かのように、真摯に思い詰めるような選択をすれば、鬱の病とか、精神の統合を失調するようなことになったかもしれない。差別しているのではなく、むしろ彼らは聖なる領域に棲む人々であり、俗なるものに堕ちたのは私のほうだ。それでも卑屈になることなく、自分なりに試行錯誤しながら、落ち着ちつける場を見出したのか・・。いや、人生なんて何が起きるか分からない。
私はこの歳になってから、小林秀雄のいうことが呑みこめるようになった。「他愛のない精神の動き、経験するときのリアルさを感じ取ることこそ大切だ」と、なんでもない言い草だが、私には至言の言葉だ。エビデンスとかデータを偏重し過ぎるな、計量できるものしか信じない現代の科学的精神の在りようこそ袋小路に入っているのだと、小林は口を酸っぱくするように語っていた。テレパシーとか第六感のようなものを信じている私は、彼の言葉はありがたいと心から思う。
こういうことを日常のさりげない言葉で、深遠な言語世界を構築する堀江敏幸ならどんなふうに表現するのだろうか。