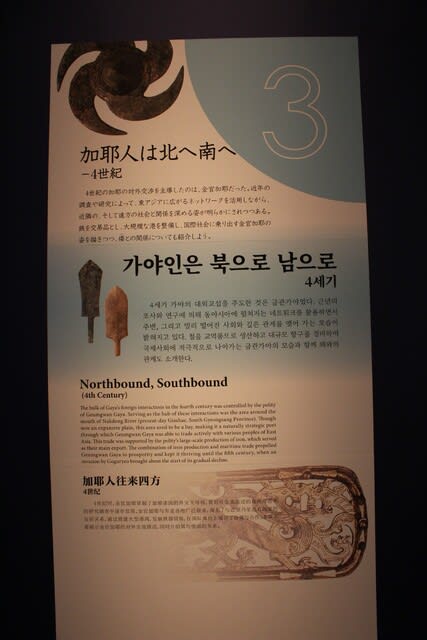第一部 伽耶の興亡
第4章 伽耶王と国際情勢
5世紀前半に、金官伽耶の王族墓地(金海大成洞古墳群)で大型墓の造営が中断する。背景は広開土王碑に刻まれた西暦400年の高句麗による金官國(金官伽耶)への侵攻の結果である。
金官伽耶と入れ替わるように伽耶の盟主となったのは、大伽耶であった。高句麗の南下により金官伽耶の王族や有力者は、大伽耶や倭へ移動したかと思われる。
大伽耶と倭の関係は、百済による大伽耶圏の一部(ソムジンガン流域)の領有を倭が認めたことによって、一時疎遠となったが、大伽耶は孤立を避けるために倭との関係を改善せざるを得なかった。この時期の大伽耶の周辺には、盛んに倭系古墳が築かれた。その被葬者は倭からの渡来人や倭と深い関係を持つ人だった。
5世紀後半に至ると、倭では大伽耶系のアクセサリー、装飾馬具、武器等の文物が古墳に副葬された。江田船山古墳はその事例の一つである。その頃に大伽耶は、洛東江より西側の地を統合するほど力をつけた。479年には伽耶で唯一、中国・南斉に遣使を果たし、輔国将軍・加羅王に冊封された。481年には高句麗の新羅侵攻に対して、百済ととに援軍を送っている。
今回は、やや順不同なるも『伽耶王と国際情勢』とのテーマで出品物を紹介する。

<伽耶王と倭>

帯金式甲冑 高霊池山洞32号墳 大伽耶 5世紀中頃
大伽耶の中心地、高霊や陜川には倭系の甲冑や須恵器がもたらされた。5世紀中頃の王陵級古墳である高霊池山洞32号墳では倭系甲冑が副葬されていた。大伽耶による対倭交渉は、新羅や百済と同様に、高句麗の南下対応策であったと考えられる。
<伽耶王と新羅>



蛍光X線による分析の結果ササン朝ペルシャのガラスであった



<伽耶王と中国、百済>


中国製の青磁鶏首壺が5世紀後半の南原月山里M5号墳から出土
大伽耶と百済の関係は、百済の海上交通にかかわる祭祀に大伽耶が参加したと云われている。






扶安竹幕洞祭祀遺跡 百済 5世紀後半
参考文献
アクセサリーの考古学 高田貫太 吉川弘文館
海の向こうから見た倭國 高田貫太 講談社現代新書
幻の伽耶と古代日本 文芸春秋編 文春文庫
古代倭と伽耶 時空旅人 2022年11月号
<続く>