第一部
第3章 伽耶人は北へ南へー4世紀
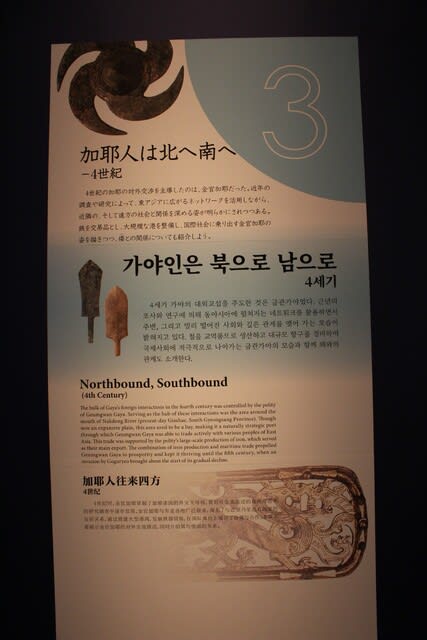
今回から2回に渡って『第3章・伽耶人は北へ南へ』とのテーマで、4世紀の出土遺物を紹介する。先ず伽耶地域で最初に台頭したのは、狗邪韓国の後継としての金官伽耶であった。その金官伽耶では北と南との交流を示す遺物が出土する。それが最初に紹介する帯金具(出品番号112~115)である。これは金官伽耶の中心・金海大成洞88号墳(4世紀中頃)から出土した晋式帯金具と呼ばれるもので、金官伽耶と倭の双方から出土する。

(晋式帯金具 金海大成洞88号墳出土 左より出品番号 112,113,114,115)
これらは、中国晋王朝の時に製作されたと云われている。そして晋だけではなく中国東北部、高句麗、百済、新羅、そして倭でみることができる。金海大成洞88号墳の被葬者が、この晋式帯金具をどのように入手したのか、その経緯は不詳ながら中国東北部や高句麗との折衝の結果であろう。
倭では奈良県新山古墳と兵庫県加古川市・行者塚古墳から出土しており、いずれも中国から朝鮮半島、つまり伽耶を経由して持ち込まれたと考えられている。

行者塚古墳出土 晋式帯金具(復元品)

行者塚古墳出土 馬具
行者塚古墳は4世紀後半から5世紀初めの築造である。晋式帯金具とともに馬具や鉄斧などが出土した。鉄斧は鋳造品で、朝鮮半島からの渡来と云われている。馬具は渡来ないし渡来人が倭で作った可能性が云々されている。このような馬具は金官伽耶でも出土しており、それらと晋式帯金具が一緒に副葬されていることから、行者塚古墳の晋式帯金具は、金官伽耶経由で倭に持ち込まれたものと考えられる。それは倭人が持ち帰ったものか、伽耶人が持ち込んだものか判然としないが播磨の地の同時代の住居跡には、渡来人の痕跡が多々確認できることから、伽耶人が持ち込んだものと考えられる。このように伽耶人は北へ南へと躍動していた。




<続く>




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます