”結核”と”伝染病”は、「地震・雷・火事親父」なんかより、ずっと恐れられていた。
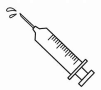
・・・・・
戦争中、国民はほとんど栄養失調になってしまっていた。
結核が感染しても無理をするもんじゃけえ、こじらせて本当の肺結核に移行してしまった。
ほとんどの家に一人や二人はいた。
結核にかかると、皆死んでいった。
病人は、納戸の隅に寝ている。
そうなったら、あと二、三か月たったら死ぬ。
その頃にならんと医者を呼びにこん。
「梶島山のくらし・戦前戦後編」福山市・梶島山のくらしを記録する会 2012年発行
・・・・・
瀧廉太郎の生涯
1901年(明治34年)4月、日本人の音楽家では2人目となるヨーロッパ留学生として、東部ドイツにあるライプツィヒ音楽院に留学。
わずか2ヶ月後に肺結核を発病し1年で帰国を余儀なくされ、
1903年(明治36年)6月29日大分市稲荷町の自宅で23歳という若さで亡くなりました。
「~府内に息づく魅惑の世界~ 瀧廉太郎の生涯/瀧廉太郎と作曲」
・・・・・
「日本医療史」 新村拓著 吉川弘文館 2006年発行
結核
江戸時代に労咳などと呼ばれた結核の多くは肺結核であった。
空気感染であったので都市化と共に流行した。
一種の伝染毒であり、書生・奉公人・処女のままの人に多く、看病人・医者・針医・按摩にも伝染する。
女工と結核
結核は20世紀半ばまで、死病として恐れられてきた。
明治期の近代化の過程で、産業の発展と共に「国民病」となった。
女工
約7割が寄宿舎に入り、一日14~16時間労働 徹夜作業が状態
体重低下、発育不全。
石原は、劣悪な労働環境、長時間労働、寝具の共同利用と不衛生な寝室について記述し、これらが結核伝染の温床となったことを明らかにした。
問題は工場の外にも広がった。
結核に罹患し解雇された女工は、転々と職業を変えつつ都市で生活するか、帰郷することになる。
いずれの場合も治療を受けられないまま、辛い療養生活を送り、そのまま死に至るものも少なくなかった。
・・・・・
「昭和③非常時日本」 講談社 平成元年発行
猛威をふるう「亡国病」
昭和11年から結核予防国民運動が始まった。
結核は、前年の昭和10年から死因の1位になっていた。
農村での結核患者急増は、兵士の供給を農村に依存している軍部にとっては深刻な問題だった。
しかも10代後半から20代の若者たちに結核による死亡率が高かったことが、政府にその予防対策を急がせた。
明治・大正は都会の工場労働者やスラム居住者たちに多い病気であり「貧民病」と呼ばれるほどだった。
ところが昭和になると、結核は農村にも広がり、やがて「亡国病」と呼ばれるまでになった。
特に繊維産業で働く女性たちは1.000人中23人が結核で死んでいったという。
帰郷した出稼ぎ青少年による二次感染が深刻化していたのである。
昭和12年には「結核予防法」が改訂された。
また、保健所法公布、結核療養所の官制化と政府は次々に対策を打ち出したが事態はなかなか好転せず、
昭和12年以降も死亡者は年々増加し、
昭和18年には人口100.000人に対し235人の死亡率に達した。
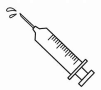
「生きることの近世史」 塚本学 平凡社 2001年発行
肺結核
明治以後20世紀前半の作家や詩人で、この病気に苦しみ死んだ人の多さは目をみはらせるほどである。
1918年には、結核の死者は、人口10万当たり257.1人で死亡順位の1位を占め、
以後30年近くにわたって他の病気に比べて圧倒的に高い死亡率を示した。
不治の病とされたこの病気の悩みと死の恐怖とは、社会の諸階層に通有のもので、
転地療養などの機会を得た人々に比べて特に悲惨でまた数も多かったのは、
村から都会に出て、きびしい労働条件と衛生環境のなかで労働者となった若者である。
慢性的な栄養欠乏状態にあるとき、結核菌はとくに猛威をふるった。
伝染する病気は不治とみなされ、しばしば遺伝するかにみられていた。
青白い顔の病人になって帰ってきた少女に、故郷の目は冷たかった。
貧と病は一体になっていた。
多くの青年をむしばむ結核は、「国の命」の観点からも恐るべき災厄であり、
1919年に結核予防法の制定以来、国による予防対策も試みらていった。
国が国民の生命の庇護者としてはたらこうとしたのである。
その効果は、この世紀後半に顕著になっていく。
・・・・

(笠岡市小平井 結核療養所施設跡 2022.2.28)
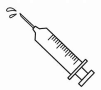
・・・・・
戦争中、国民はほとんど栄養失調になってしまっていた。
結核が感染しても無理をするもんじゃけえ、こじらせて本当の肺結核に移行してしまった。
ほとんどの家に一人や二人はいた。
結核にかかると、皆死んでいった。
病人は、納戸の隅に寝ている。
そうなったら、あと二、三か月たったら死ぬ。
その頃にならんと医者を呼びにこん。
「梶島山のくらし・戦前戦後編」福山市・梶島山のくらしを記録する会 2012年発行
・・・・・
瀧廉太郎の生涯
1901年(明治34年)4月、日本人の音楽家では2人目となるヨーロッパ留学生として、東部ドイツにあるライプツィヒ音楽院に留学。
わずか2ヶ月後に肺結核を発病し1年で帰国を余儀なくされ、
1903年(明治36年)6月29日大分市稲荷町の自宅で23歳という若さで亡くなりました。
「~府内に息づく魅惑の世界~ 瀧廉太郎の生涯/瀧廉太郎と作曲」
・・・・・
「日本医療史」 新村拓著 吉川弘文館 2006年発行
結核
江戸時代に労咳などと呼ばれた結核の多くは肺結核であった。
空気感染であったので都市化と共に流行した。
一種の伝染毒であり、書生・奉公人・処女のままの人に多く、看病人・医者・針医・按摩にも伝染する。
女工と結核
結核は20世紀半ばまで、死病として恐れられてきた。
明治期の近代化の過程で、産業の発展と共に「国民病」となった。
女工
約7割が寄宿舎に入り、一日14~16時間労働 徹夜作業が状態
体重低下、発育不全。
石原は、劣悪な労働環境、長時間労働、寝具の共同利用と不衛生な寝室について記述し、これらが結核伝染の温床となったことを明らかにした。
問題は工場の外にも広がった。
結核に罹患し解雇された女工は、転々と職業を変えつつ都市で生活するか、帰郷することになる。
いずれの場合も治療を受けられないまま、辛い療養生活を送り、そのまま死に至るものも少なくなかった。
・・・・・
「昭和③非常時日本」 講談社 平成元年発行
猛威をふるう「亡国病」
昭和11年から結核予防国民運動が始まった。
結核は、前年の昭和10年から死因の1位になっていた。
農村での結核患者急増は、兵士の供給を農村に依存している軍部にとっては深刻な問題だった。
しかも10代後半から20代の若者たちに結核による死亡率が高かったことが、政府にその予防対策を急がせた。
明治・大正は都会の工場労働者やスラム居住者たちに多い病気であり「貧民病」と呼ばれるほどだった。
ところが昭和になると、結核は農村にも広がり、やがて「亡国病」と呼ばれるまでになった。
特に繊維産業で働く女性たちは1.000人中23人が結核で死んでいったという。
帰郷した出稼ぎ青少年による二次感染が深刻化していたのである。
昭和12年には「結核予防法」が改訂された。
また、保健所法公布、結核療養所の官制化と政府は次々に対策を打ち出したが事態はなかなか好転せず、
昭和12年以降も死亡者は年々増加し、
昭和18年には人口100.000人に対し235人の死亡率に達した。
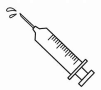
「生きることの近世史」 塚本学 平凡社 2001年発行
肺結核
明治以後20世紀前半の作家や詩人で、この病気に苦しみ死んだ人の多さは目をみはらせるほどである。
1918年には、結核の死者は、人口10万当たり257.1人で死亡順位の1位を占め、
以後30年近くにわたって他の病気に比べて圧倒的に高い死亡率を示した。
不治の病とされたこの病気の悩みと死の恐怖とは、社会の諸階層に通有のもので、
転地療養などの機会を得た人々に比べて特に悲惨でまた数も多かったのは、
村から都会に出て、きびしい労働条件と衛生環境のなかで労働者となった若者である。
慢性的な栄養欠乏状態にあるとき、結核菌はとくに猛威をふるった。
伝染する病気は不治とみなされ、しばしば遺伝するかにみられていた。
青白い顔の病人になって帰ってきた少女に、故郷の目は冷たかった。
貧と病は一体になっていた。
多くの青年をむしばむ結核は、「国の命」の観点からも恐るべき災厄であり、
1919年に結核予防法の制定以来、国による予防対策も試みらていった。
国が国民の生命の庇護者としてはたらこうとしたのである。
その効果は、この世紀後半に顕著になっていく。
・・・・

(笠岡市小平井 結核療養所施設跡 2022.2.28)

















