大分市美術館で開催中の

春耕 1924年

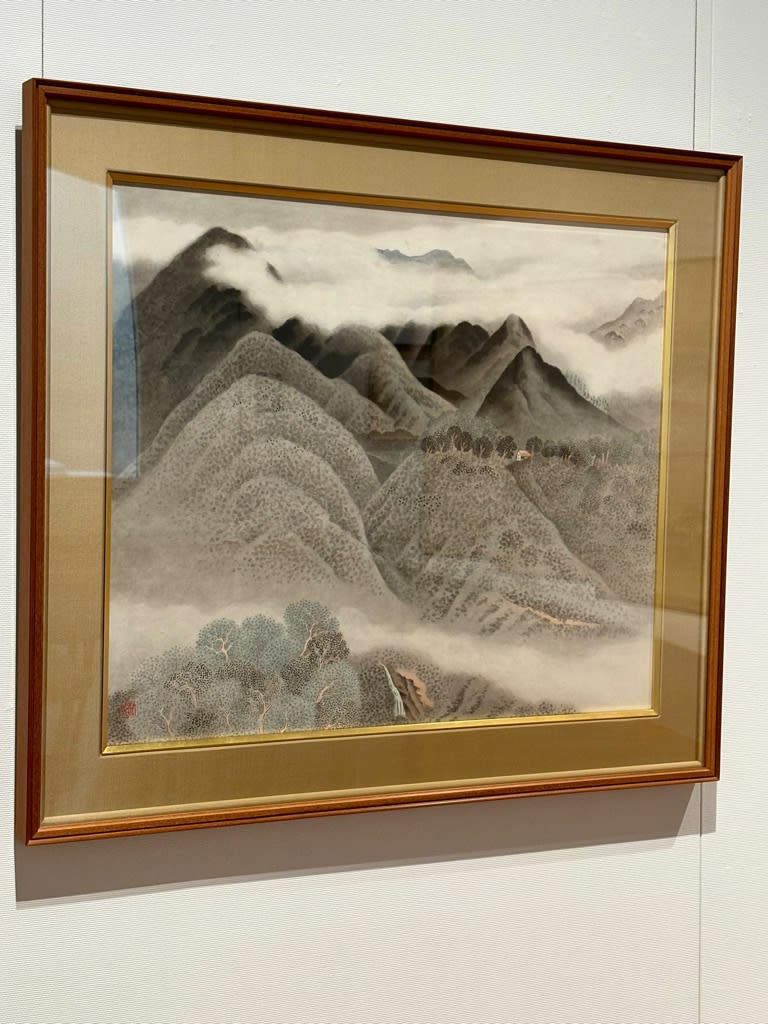
山 1929年


あかあかと日は難面もあきの風<習作>

暑き日を海に入れたり最上川<習作>

月 1944年
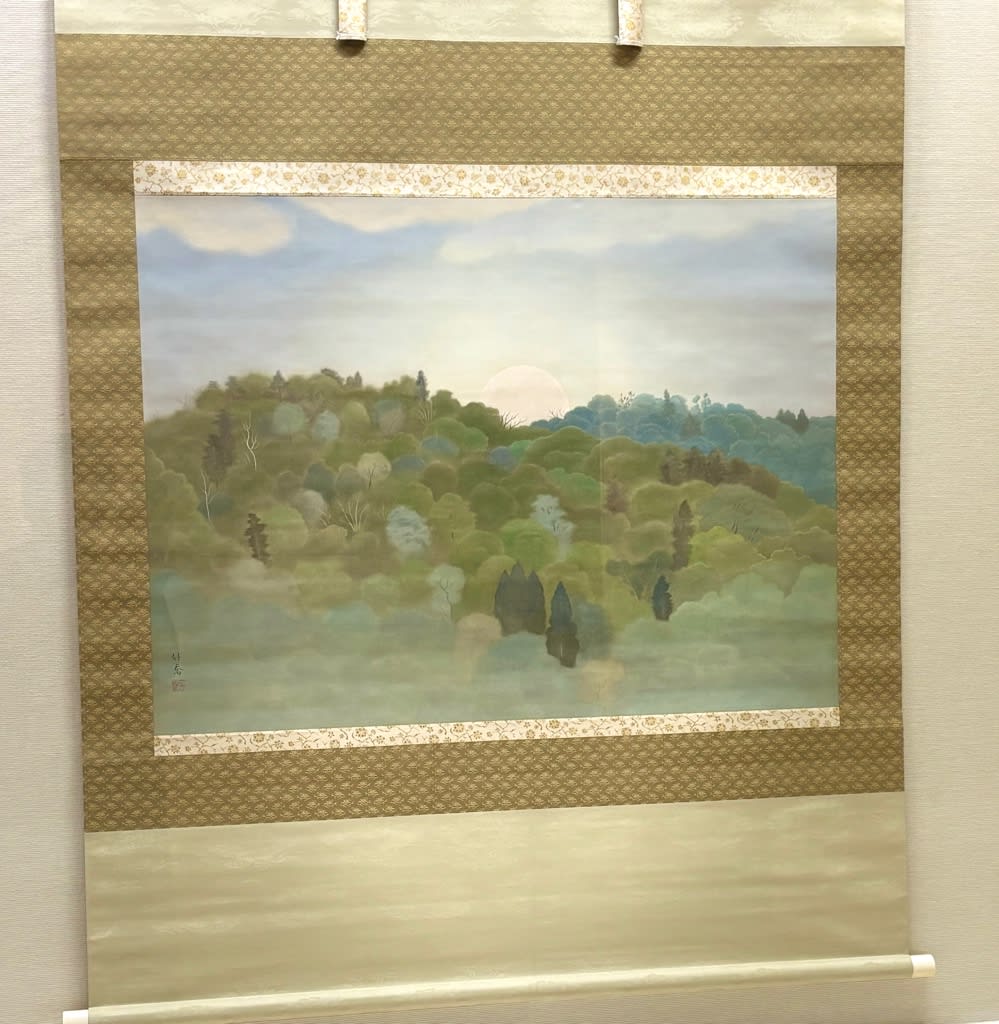
仲秋の月 1947年
「小野竹喬の世界」展へ、

春耕 1924年
重要文化財の「波切村」後の展示が気に掛かっていたところ、
友人に誘われたこともあり、
また水曜日は学芸員さんの説明も聞けるということで、行ってきました。

八瀬村頭 1926年
いずれも、渡欧体験を経て、
従来の日本画に囚われない写実に迫ろうとした作品だそうです。
欧州の風景を描いた小品もいくつか展示されていましたが、思うようにいかなかったのか、
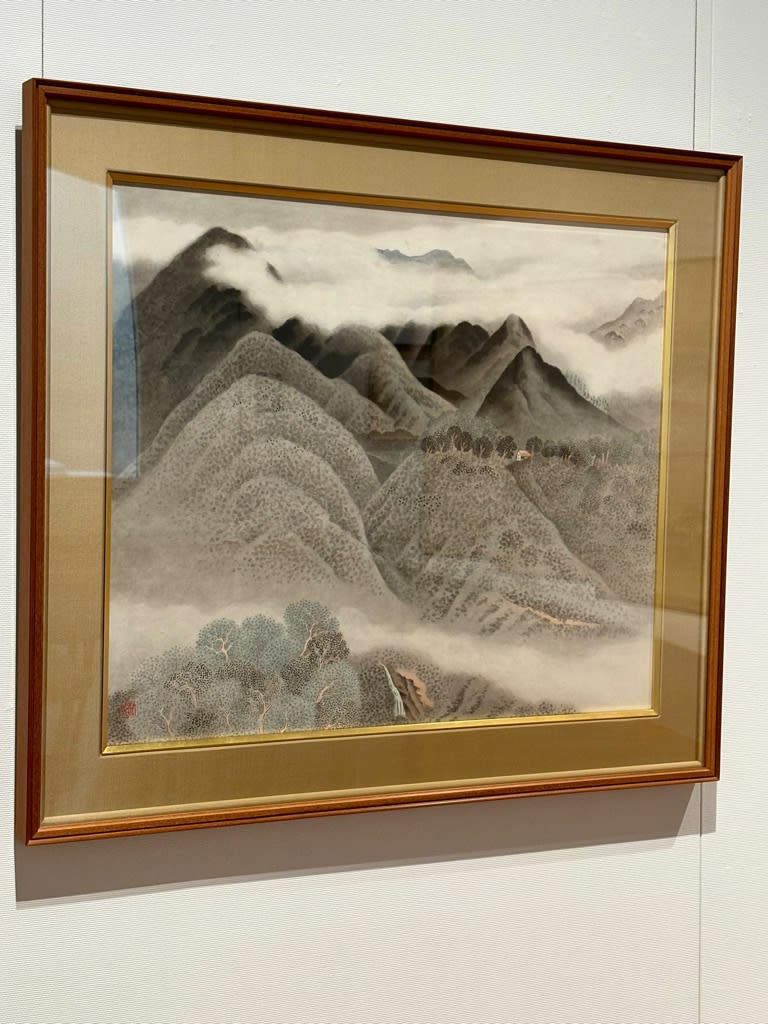
山 1929年
この作品では、東洋の古典絵画を見直す、
点描表現が見直されています。

🔹🔹
前回、撮ろうとしてうまく行かなかった作品を、ここからは紹介したいと思います。
一人で見て回るのとは違って、
絵の説明など詳しくしていただき、
同時期、同じ京都にいた竹喬と福田平八郎との交流話なども聞かれ、
また疑問に思っていたことの解答なども得ることが出来ました。😊

あかあかと日は難面もあきの風<習作>
1976年
この作品は、俳句を題材にした句抄絵シリーズの中の一点ですが、
もっとも多くの習作が残っていて、
試作を重ねたことが分かっているそうです。
私などはこれが完成品だと思ってみていたので、習作??と前回は疑問符がついたままでした。
発表作は、日輪の左右の青色の帯が、
茜一色になっているそうです。
福田平八郎さんも、デッサンをよくしていましたが、竹喬さんも負けていないようです。

暑き日を海に入れたり最上川<習作>
1976年
上と似たような作品に思いますが、
日本海への落日を描き、
これも習作となっています。
最後に、

月 1944年
悲しみの宿る作品になってしまいますが、
1944年末、長男の戦死を受けた竹喬の悲痛が、空に反映されているようです。
子どもの死を乗り越えるのは容易ではなかったことでしょう。
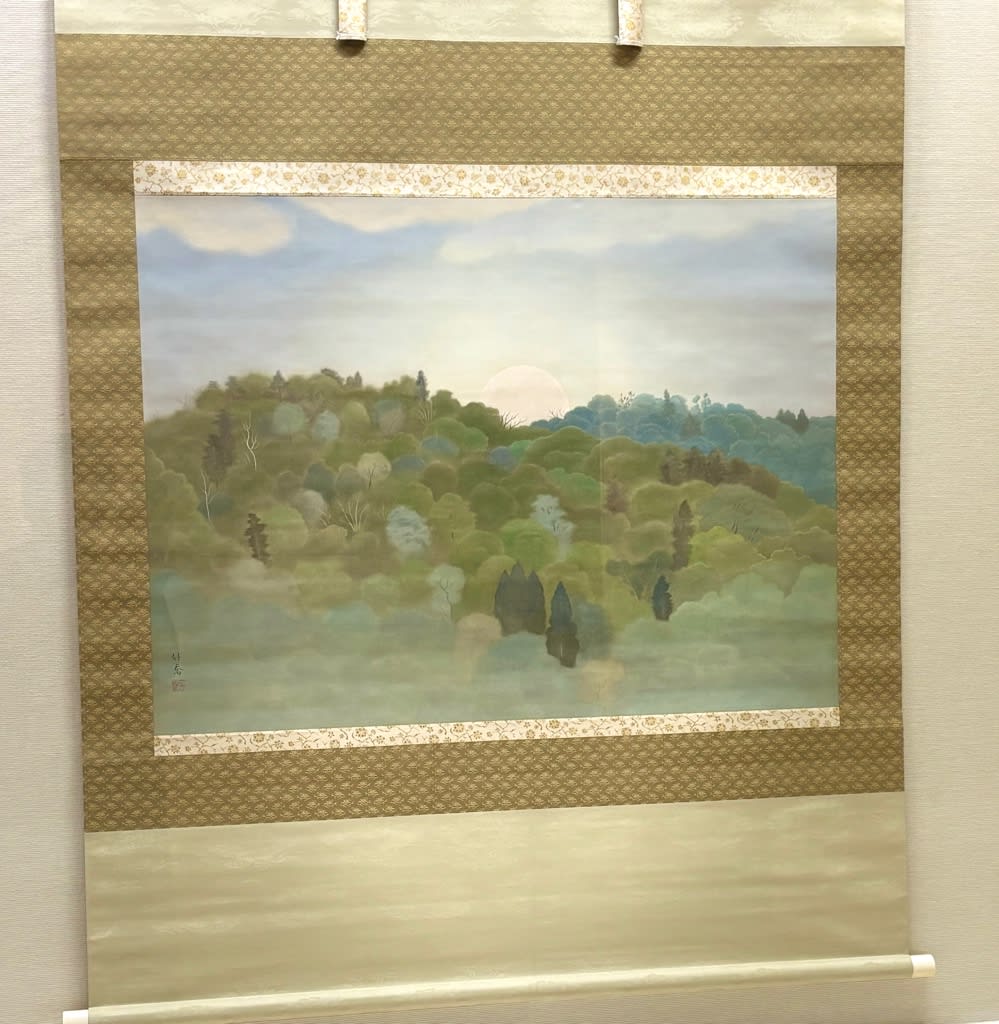
仲秋の月 1947年
戦後に創設された日展への初出品作
神々しい山の端から満月が現れ、
空と樹林は清光に包まれる、、
戦後における自らの無心の再出発と捉えられる作品です。
竹喬は、晩年、
1976年に文化勲章を受賞しています。
🔹🔹
この後、友人と美術館内にある喫茶店へ、
面白い作品に出会いましたので、
明日に続きます。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます