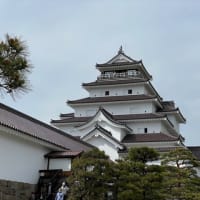銀色の雨を見つめていた君
帰ってからすぐ、ユニットバスへ入ってシャワーを浴びた。
まるでどす黒い廃油を頭からかぶったようで、どうにも気持ち悪い。肌がぬめる。心までがべとつく。
この感覚はいったいなんなのだろう。
遥の父親と激しいやりとりをして嫌なことをずいぶん口にしたから、その自己嫌悪もあった。遥を守るために必死だったし、いくらそうするのが遥のためだとわかっていても、家族関係を断ち切ってしまうのは、やはり胸の奥が疼く。だけど、そればかりでもない。
考えあぐねているうちに、遥が時々口にする「死んだ愛情が腐っているのよ」という言葉を想い起こした。穢されたような気がするのは、きっと、あの男の心のなかで腐敗してしまったものが、言葉になって僕の心へ流れこんだからだろう。彼の腐った心に触れて、僕の心までが腐り始めたのだ。ちょうど、木箱のなかの腐ったりんごがほかのりんごもだめにしてしまうように。強欲と傲慢に心を乗っ取られた人間は始末が悪い。それを自分自身で自覚していなければなおさらだ。心が化膿して、膿だらけになってしまったようなものだから。
遥が自分の欲望を抑えようとあれほどまでにこだわるのは、きっと自分の父親を反面教師としたからだろう。あの男の驕慢《きょうまん》がどれだけ家族を損なったのか骨身にしみてわかっているから、自分の強欲さに対しても過敏になってしまったのに違いない。
僕は全身にせっけんを塗りたくり、体のすみずみまで力をこめて垢すりタオルでこすった。穢れをすべて落としたかった。
バスタブをざっと流して栓をした。シャワーを壁にかけ、バスタブの底で三角坐りしながら熱い湯を浴びた。
シャワーの音が雨のように響く。
バスタブにすこしずつ湯がたまる。
その音が呼び水になって、中三の頃のなんでもない日の光景が脳裡に甦った。
たしか、秋の長雨が続いていた頃だった。教師たちは、夏休み前までは部活さえしっかりやっていればいいという態度だったけど、いざ引退試合を終えてクラブの運営を後輩たちへ譲り渡すと、今度は掌を返したように成績のことばかり言い始めた。進路相談や受験勉強で慌しい日々を送っていた。
なにかの用事で帰るのが遅くなった。がらんとした放課後の下足室に、遥がぽつんと立っている。外は銀色の雨が降っていた。雨を眺める遥のうなじが白い。
「天草」
僕が呼びかけると、遥はぼんやり振り返る。制服の肩がさびしそうだった。
「どうしたの? 傘は?」
遥は黙って首を振るだけだ。
「僕の傘に入りなよ。送っていくよ」
僕は遥を元気づけようと思ってわざと明るく言ったのだけど、遥はなにも言わずに瞳を翳《かげ》らせる。
「なにかあったの?」
「なんでもないわ。――いっしょに傘を差したら、瀬戸君はまたからかわれるわよ」
「べつにそんなのかまわないよ。言わせておけばいいんだから」
僕は遥を見つめた。遥はずっと雨を見ている。
――ひとりぼっちなんだ。
胸が締めつけられるようで、目頭が熱くなった。遥の孤独が痛いほど心にしみた。それが僕の心のなかで魔法の森の調べのように透き通った和音を奏でる。さみしいのは僕も同じだった。
――遥の孤独を抱きとめてあげたい。
震えるような想いでそう願った。
あの時、相合傘をしていっしょに帰ったような気がするけど、よく覚えていない。ただ、降りしきる雨を見つめる遥の横顔だけが、心のアルバムに焼きついている。
僕はシャワーをとめた。
熱い湯にじっとつかりながら、遥を想った。
昼からふたコマぶんの授業を受けて、サークルの部屋にも寄らずにさっさと帰ってきた。遥の父親がマンションの近くで張りこんでいるのではないかと疑って近所を探してみたけど、彼の姿は見当たらない。僕はほっと息をつき、ワンルームマンションの狭い階段をのぼった。
「おかえりなさい」
遥は、ドアのすぐそばにある流し台に立っていた。ペンギンのエプロンをつけて、にんじんを切っている。換気扇のファンが鈍くうなり、玉葱の匂いがかすかに漂っていた。
「ただいま」
僕は遥の顔色をうかがった。
「どうしたの?」
遥は不思議そうに首を傾げる。
「な、なんでも」
僕は、首を振ってスニーカーを脱いだ。
「今日はカレーにするから」
「わかった」
「ゆうちゃん、なんかへんよ」
「ほんとになんでもないんだよ。手伝おうか?」
「いいわよ」
遥はプラスチックの薄いまな板を持ち上げて、切り終えたにんじんをボールへ移す。僕は遥の後ろを忍び足でそっと通って部屋へ入り、テレビをつけてその前に坐った。
彼女の父親がきたことを話そうかどうか、まだ迷っていた。授業も上の空で、帰り道もそればかり考えていた。
あの男の言い分を突っぱねられるだけ突っぱねてどうにか追い払うことができたけど、あれですんなり引き下がるかどうかはわからない。遥に聞いていたとおり、彼はすべて自分の思うようにしないと気の済まない性格だ。またやってくるかもしれない。
今日は、遥がいなくて不幸中の幸いだった。彼がきたことを言えば、遥は傷つくに決まっている。ようやく元気になってくれたばかりなのに、負担をかけるようなことは言いたくなかった。でも、もし彼がもう一度現れるのだとしたら、今ほんとうのことを言って、心の準備をしておいたほうがいい。たとえつらくても、いきなり父親が目の前に現れるよりは、ショックもやわらぐはずだから。どちらが、遥のためになるのだろう。
じゅっとカレー肉が爆ぜる。遥はみじん切りにした玉葱を手際よく鍋へ放りこみ、にんじんとじゃがいもを炒めてから鍋に水を入れてぐつぐつ煮込む。遥は手を休めることなくレタスを洗った。野菜サラダも作るようだ。
炊飯器から湯気があがる。遥はS&Bのルーを割り、おたまで溶かす。僕は、折り畳みのちゃぶ台を広げて布巾で拭いた。
「いただきます」
僕たちは手を合わせて食べ始めた。
――やっぱり、ほんとうのことを言っておいたほうがいいんだろうな。
スプーンでカレーライスをすくいながら、なんとなく思った。
「ゆうちゃん、たまごは?」
「あ、そうだね。遥は?」
「わたしはいらないわ」
僕は、カレーに生卵をかけるのが好きだった。冷蔵庫から一つ取ってカレーへ落とすと、黄身と白身がカレーライスのうえを滑り落ちて皿の端からこぼれそうになる。僕は慌ててスプーンでかきまぜた。カレーライスの真ん中に穴を掘っておくのを忘れていた。
「ゆうちゃん、ほんとうにどうしたの? ぼんやりしちゃって、元気ないわよ」
「ちょっとね。いきなり先生にレポートを出せって言われてさ、どうしようかなって考えているんだよ」
僕はとっさに嘘をついた。
「そうなの。急に言われても困るわね」
遥は、なんとなく納得したような面持ちだった。
ふたりとも黙ったまま食べた。僕はいつものように遥の作ったカレーライスをお替りした。
遥が洗い物を終えた後、いっしょにお茶を飲んだ。遥は、今日授業で習ったことや街角で見かけたことをとりとめもなく話す。僕は、遥の話が途切れたら切り出そうとタイミングを計っていた。
突然、チャイムが鳴る。
思わずどきりとする。
遥がインターフォンへ出ようしたのをとめて、僕が受話器を取った。
あの男かと思って身構えたのだけど、相手は宅配便だった。僕は胸をなでおろした。
僕の祖父が小包を送ってくれた。
ダンボールを開けると、箱一杯にみかんがつまっていた。蓋の裏側に白い封書が貼り付けてあったので封を切った。祖父の直筆の手紙だった。学業に励むように、それから、正月に帰ってくるのを楽しみにしていると万年筆で書いてある。あたたかい励ましだった。
「いい香りね」
遥は、みかんを鼻先にあてて匂いをかぐ。
「おいしそうだね。食べきれるかな」
僕は、摑んだみかんをボール遊びでもするように手の甲に乗せ、
「ねえ、遥――」
と、遥の父親のことを話そうとした。
「ゆうちゃん、今度の週末に教会のボランティアで施設へ行くんだけど、すこし持っていっておすそわけしてあげていいかな」
遥は楽しそうに肩を揺らし、少女のようにくすくす笑う。
「いいよ。子供たちも喜んでくれるだろうね」
「ありがとう。いっしょに食べながら絵本でも読んであげようかしら」
遥は、さっそくみかんをむき始めた。遥の嬉しげな姿を見ると、切り出せなくなってしまった。
「ちょっと、コンビニで立ち読みしてくるよ」
僕は遥に言って部屋を出た。外の空気を吸って、気持ちを入れ換えたかった。
セブンイレブンで週刊誌やコミック雑誌をぱらぱらめくってみたけど、あのことが気懸かりで落ち着かない。お菓子の棚をぶらぶら眺めると、新発売になったという油で揚げないポテトチップスが目に留まったので一袋買ってみた。金色のゴージャスなパッケージだ。ノンフライだから太らないと書いてある。目新しいものでも口にすれば、気分転換になるかもしれない。僕は一袋買うことにした。
帰り道、ふと思い立ってオカマさんに電話した。彼ならどう考えるのだろう。意見を聞いてみたかった。だけど、オカマさんの携帯電話は話し中で通じない。道端で立ったまま五分ほど待ってかけ直してみたのだけど、やはり話し中だった。メールを打とうかとも考えたけど、あきらめて帰ることにした。
街灯のともった住宅街の道を歩く。なんとなくあやふやで頼りない気分だ。中学校の下足室で銀色の雨を見つめていた遥の姿がまた脳裏に浮かぶ。
これまでずっと、僕は遥の孤独を抱きしめようとしてきた。
遥は僕の想いに応え、幸せになろうとがんばってくれた。現実と向かい合い、自分と向かい合い、神さまと向かい合い、なんとか折り合いをつけようと努力してくれた。もちろん、大切なことは忘れずに。
――ほんとうのことを言おう。
ようやく、きちんと決心がついた。
現実を見つめなければ、なにもはじまらない。遥が落ちこんだとしても、僕が支えてあげればいい。遥になにがあっても、僕はそばにいるのだから。遥のことが心配だと言いながら、逃げていたのは、実は僕自身なのかもしれない。
近道の路地を抜けて、児童公園のそばを通りかかった。ブランコとジャングルジムとシーソーがあるだけの小さな公園だ。横目でなかを見た僕は、ふとなにかがひっかかった。
僕は足をとめ、水銀灯に照らされた公園を見渡した。
コートを羽織った中年男がベンチに坐っている。その背格好は遥の父親によく似ていた。
帰ってからすぐ、ユニットバスへ入ってシャワーを浴びた。
まるでどす黒い廃油を頭からかぶったようで、どうにも気持ち悪い。肌がぬめる。心までがべとつく。
この感覚はいったいなんなのだろう。
遥の父親と激しいやりとりをして嫌なことをずいぶん口にしたから、その自己嫌悪もあった。遥を守るために必死だったし、いくらそうするのが遥のためだとわかっていても、家族関係を断ち切ってしまうのは、やはり胸の奥が疼く。だけど、そればかりでもない。
考えあぐねているうちに、遥が時々口にする「死んだ愛情が腐っているのよ」という言葉を想い起こした。穢されたような気がするのは、きっと、あの男の心のなかで腐敗してしまったものが、言葉になって僕の心へ流れこんだからだろう。彼の腐った心に触れて、僕の心までが腐り始めたのだ。ちょうど、木箱のなかの腐ったりんごがほかのりんごもだめにしてしまうように。強欲と傲慢に心を乗っ取られた人間は始末が悪い。それを自分自身で自覚していなければなおさらだ。心が化膿して、膿だらけになってしまったようなものだから。
遥が自分の欲望を抑えようとあれほどまでにこだわるのは、きっと自分の父親を反面教師としたからだろう。あの男の驕慢《きょうまん》がどれだけ家族を損なったのか骨身にしみてわかっているから、自分の強欲さに対しても過敏になってしまったのに違いない。
僕は全身にせっけんを塗りたくり、体のすみずみまで力をこめて垢すりタオルでこすった。穢れをすべて落としたかった。
バスタブをざっと流して栓をした。シャワーを壁にかけ、バスタブの底で三角坐りしながら熱い湯を浴びた。
シャワーの音が雨のように響く。
バスタブにすこしずつ湯がたまる。
その音が呼び水になって、中三の頃のなんでもない日の光景が脳裡に甦った。
たしか、秋の長雨が続いていた頃だった。教師たちは、夏休み前までは部活さえしっかりやっていればいいという態度だったけど、いざ引退試合を終えてクラブの運営を後輩たちへ譲り渡すと、今度は掌を返したように成績のことばかり言い始めた。進路相談や受験勉強で慌しい日々を送っていた。
なにかの用事で帰るのが遅くなった。がらんとした放課後の下足室に、遥がぽつんと立っている。外は銀色の雨が降っていた。雨を眺める遥のうなじが白い。
「天草」
僕が呼びかけると、遥はぼんやり振り返る。制服の肩がさびしそうだった。
「どうしたの? 傘は?」
遥は黙って首を振るだけだ。
「僕の傘に入りなよ。送っていくよ」
僕は遥を元気づけようと思ってわざと明るく言ったのだけど、遥はなにも言わずに瞳を翳《かげ》らせる。
「なにかあったの?」
「なんでもないわ。――いっしょに傘を差したら、瀬戸君はまたからかわれるわよ」
「べつにそんなのかまわないよ。言わせておけばいいんだから」
僕は遥を見つめた。遥はずっと雨を見ている。
――ひとりぼっちなんだ。
胸が締めつけられるようで、目頭が熱くなった。遥の孤独が痛いほど心にしみた。それが僕の心のなかで魔法の森の調べのように透き通った和音を奏でる。さみしいのは僕も同じだった。
――遥の孤独を抱きとめてあげたい。
震えるような想いでそう願った。
あの時、相合傘をしていっしょに帰ったような気がするけど、よく覚えていない。ただ、降りしきる雨を見つめる遥の横顔だけが、心のアルバムに焼きついている。
僕はシャワーをとめた。
熱い湯にじっとつかりながら、遥を想った。
昼からふたコマぶんの授業を受けて、サークルの部屋にも寄らずにさっさと帰ってきた。遥の父親がマンションの近くで張りこんでいるのではないかと疑って近所を探してみたけど、彼の姿は見当たらない。僕はほっと息をつき、ワンルームマンションの狭い階段をのぼった。
「おかえりなさい」
遥は、ドアのすぐそばにある流し台に立っていた。ペンギンのエプロンをつけて、にんじんを切っている。換気扇のファンが鈍くうなり、玉葱の匂いがかすかに漂っていた。
「ただいま」
僕は遥の顔色をうかがった。
「どうしたの?」
遥は不思議そうに首を傾げる。
「な、なんでも」
僕は、首を振ってスニーカーを脱いだ。
「今日はカレーにするから」
「わかった」
「ゆうちゃん、なんかへんよ」
「ほんとになんでもないんだよ。手伝おうか?」
「いいわよ」
遥はプラスチックの薄いまな板を持ち上げて、切り終えたにんじんをボールへ移す。僕は遥の後ろを忍び足でそっと通って部屋へ入り、テレビをつけてその前に坐った。
彼女の父親がきたことを話そうかどうか、まだ迷っていた。授業も上の空で、帰り道もそればかり考えていた。
あの男の言い分を突っぱねられるだけ突っぱねてどうにか追い払うことができたけど、あれですんなり引き下がるかどうかはわからない。遥に聞いていたとおり、彼はすべて自分の思うようにしないと気の済まない性格だ。またやってくるかもしれない。
今日は、遥がいなくて不幸中の幸いだった。彼がきたことを言えば、遥は傷つくに決まっている。ようやく元気になってくれたばかりなのに、負担をかけるようなことは言いたくなかった。でも、もし彼がもう一度現れるのだとしたら、今ほんとうのことを言って、心の準備をしておいたほうがいい。たとえつらくても、いきなり父親が目の前に現れるよりは、ショックもやわらぐはずだから。どちらが、遥のためになるのだろう。
じゅっとカレー肉が爆ぜる。遥はみじん切りにした玉葱を手際よく鍋へ放りこみ、にんじんとじゃがいもを炒めてから鍋に水を入れてぐつぐつ煮込む。遥は手を休めることなくレタスを洗った。野菜サラダも作るようだ。
炊飯器から湯気があがる。遥はS&Bのルーを割り、おたまで溶かす。僕は、折り畳みのちゃぶ台を広げて布巾で拭いた。
「いただきます」
僕たちは手を合わせて食べ始めた。
――やっぱり、ほんとうのことを言っておいたほうがいいんだろうな。
スプーンでカレーライスをすくいながら、なんとなく思った。
「ゆうちゃん、たまごは?」
「あ、そうだね。遥は?」
「わたしはいらないわ」
僕は、カレーに生卵をかけるのが好きだった。冷蔵庫から一つ取ってカレーへ落とすと、黄身と白身がカレーライスのうえを滑り落ちて皿の端からこぼれそうになる。僕は慌ててスプーンでかきまぜた。カレーライスの真ん中に穴を掘っておくのを忘れていた。
「ゆうちゃん、ほんとうにどうしたの? ぼんやりしちゃって、元気ないわよ」
「ちょっとね。いきなり先生にレポートを出せって言われてさ、どうしようかなって考えているんだよ」
僕はとっさに嘘をついた。
「そうなの。急に言われても困るわね」
遥は、なんとなく納得したような面持ちだった。
ふたりとも黙ったまま食べた。僕はいつものように遥の作ったカレーライスをお替りした。
遥が洗い物を終えた後、いっしょにお茶を飲んだ。遥は、今日授業で習ったことや街角で見かけたことをとりとめもなく話す。僕は、遥の話が途切れたら切り出そうとタイミングを計っていた。
突然、チャイムが鳴る。
思わずどきりとする。
遥がインターフォンへ出ようしたのをとめて、僕が受話器を取った。
あの男かと思って身構えたのだけど、相手は宅配便だった。僕は胸をなでおろした。
僕の祖父が小包を送ってくれた。
ダンボールを開けると、箱一杯にみかんがつまっていた。蓋の裏側に白い封書が貼り付けてあったので封を切った。祖父の直筆の手紙だった。学業に励むように、それから、正月に帰ってくるのを楽しみにしていると万年筆で書いてある。あたたかい励ましだった。
「いい香りね」
遥は、みかんを鼻先にあてて匂いをかぐ。
「おいしそうだね。食べきれるかな」
僕は、摑んだみかんをボール遊びでもするように手の甲に乗せ、
「ねえ、遥――」
と、遥の父親のことを話そうとした。
「ゆうちゃん、今度の週末に教会のボランティアで施設へ行くんだけど、すこし持っていっておすそわけしてあげていいかな」
遥は楽しそうに肩を揺らし、少女のようにくすくす笑う。
「いいよ。子供たちも喜んでくれるだろうね」
「ありがとう。いっしょに食べながら絵本でも読んであげようかしら」
遥は、さっそくみかんをむき始めた。遥の嬉しげな姿を見ると、切り出せなくなってしまった。
「ちょっと、コンビニで立ち読みしてくるよ」
僕は遥に言って部屋を出た。外の空気を吸って、気持ちを入れ換えたかった。
セブンイレブンで週刊誌やコミック雑誌をぱらぱらめくってみたけど、あのことが気懸かりで落ち着かない。お菓子の棚をぶらぶら眺めると、新発売になったという油で揚げないポテトチップスが目に留まったので一袋買ってみた。金色のゴージャスなパッケージだ。ノンフライだから太らないと書いてある。目新しいものでも口にすれば、気分転換になるかもしれない。僕は一袋買うことにした。
帰り道、ふと思い立ってオカマさんに電話した。彼ならどう考えるのだろう。意見を聞いてみたかった。だけど、オカマさんの携帯電話は話し中で通じない。道端で立ったまま五分ほど待ってかけ直してみたのだけど、やはり話し中だった。メールを打とうかとも考えたけど、あきらめて帰ることにした。
街灯のともった住宅街の道を歩く。なんとなくあやふやで頼りない気分だ。中学校の下足室で銀色の雨を見つめていた遥の姿がまた脳裏に浮かぶ。
これまでずっと、僕は遥の孤独を抱きしめようとしてきた。
遥は僕の想いに応え、幸せになろうとがんばってくれた。現実と向かい合い、自分と向かい合い、神さまと向かい合い、なんとか折り合いをつけようと努力してくれた。もちろん、大切なことは忘れずに。
――ほんとうのことを言おう。
ようやく、きちんと決心がついた。
現実を見つめなければ、なにもはじまらない。遥が落ちこんだとしても、僕が支えてあげればいい。遥になにがあっても、僕はそばにいるのだから。遥のことが心配だと言いながら、逃げていたのは、実は僕自身なのかもしれない。
近道の路地を抜けて、児童公園のそばを通りかかった。ブランコとジャングルジムとシーソーがあるだけの小さな公園だ。横目でなかを見た僕は、ふとなにかがひっかかった。
僕は足をとめ、水銀灯に照らされた公園を見渡した。
コートを羽織った中年男がベンチに坐っている。その背格好は遥の父親によく似ていた。