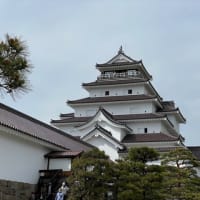許したくないもの、許したいもの
「どうだった? ずいぶん話しこんだようだけど」
部屋へ帰った僕はさっそく訊いた。
「お姉ちゃんは訴えなさいって勧めてくれたわ」
遥は、すこしばかり気の晴れた顔をする。
遥の姉はもう実家を出て、地元の県庁所在地の街で暮しているそうだ。勤め先で知り合った彼氏と同棲中で、来年の夏に結婚する予定なのだとか。
「でもね、お姉ちゃんの彼氏も、彼のご両親も複雑な事情はわかっているから、あの人が裁判にかけられたり牢屋へ入ったりしても大丈夫だって、万が一、婚約がご破算になってもかまわないし、自分のことは気にしなくていいから、ひどいことをされたぶんだけぎゃふんといわせてあげなさいって励ましてくれたの」
「そう、よかったね」
僕は遥の頭をなでた。遥は涙ぐむ。
「久しぶりだったからつい話しこんじゃったんだけど、お姉ちゃんもあの人がお母さんをいじめたことは許せないみたい。お母さんの仇を討ついい機会じゃないともいってたわ。お姉ちゃんは、あの人からお母さんを取り上げられたんだもの。うらむわよね。それから、自分が家を出て、あの人の相手をまったくしなくなったから、ゆがんだ愛情のはけ口がわたしへむかったのかもしない、わたしがあの人に振り回されるようなことになってごめんってあやまるの。お姉ちゃんせいじゃないのにね」
「遥のことを心配してくれているんだよ」
そう言いながら、エゴイストの親を持つと、いろんなことが自分の責任のような気にさせられて苦労するなと思わずにはいられなかった。
「お姉ちゃんはわたしが東京へ出てくるとき、あなたは好きなことをして、自分のしあわせをつかみなさいって送り出してくれたんだけど、さっきもその言葉をくりかえしてくれたわ。わたし、すごくうれしかった」
遥は指で涙をぬぐった。離ればなれの姉でも心は通いあっていた。自分のことを気にかけてくれる家族がいて、遥はさぞ気持ちが楽になっただろう。僕もほっとした。
ほうじ茶を淹れ、ふたりでいろいろ話し合った。といっても、遥の考えはもう固まっていたから、遥はそれでいいのかどうか僕に確認するだけだ。遥が軽はずみに物事を決めたりする女の子ではないとわかっている。悩みになやんだ末に出した結論なのだから、僕にも異論はない。誰かに答えを求めたり、投げ出したりせず、自分自身で答えを出した遥を誇りに思う。
お地蔵さんのような刑事に連絡を入れ、警察署へ向かった。
受付で名前と要件を告げ、制服を着た若い警官に二階へ案内してもらう。着替え用のロッカーがずらりと並んだ廊下の上には、剣道の防具や柔道着が渡したロープに干してあり、男くさい汗の匂いがこもっている。僕はふと、高校の部室を想い起こした。
換気扇のうなり声が遠く鈍く響く。どこそこでひったくりが発生したので付近のパトカーは急行せよだとか、変死体が見つかったなどという警察無線のアナウンスがスピーカーからひっきりなしに流れる。そんな放送を聞いていると、自分の知らないところでいろんな犯罪が起きていることがわかる。日本中の警察の放送を全部合わせれば、一日にどれくらいの数になるのだろう。目には見えないけど、この世は暴力に覆われているようだ。
殺風景な事務所の端を通り、その隅にある小さな取調べ室へ入った。ペンキの剥げた壁にかなり古ぼけた木目調のクーラーが取り付けられ、その下に風量を調整するための手回し式ダイヤルがついている。窓の下に銀色のスチーム暖房が置いてあったけど、まだスチームは通っていないようで、コンクリートの部屋は底冷えがした。
お地蔵顔の刑事と左腕を白布で吊るした遥の父親がスチール机を前にして坐っている。遥のやつれた頰が一瞬ひきつる。男は遥を横目で睨み、あからさまに不貞腐れる。僕と遥はパイプ椅子に坐った。
「それでは、さっそくですが、昨日《さくじつ》発生した件につきまして、瀬戸佑弥さんと天草遥さんの考えをお聞かせ願いたいと存じます」
刑事はあらたまった口調で言う。遥の父親は傲岸そうに腕を組み、
「私は仕事があるのでね、こんなところから早く出してもらいたいんだが」
と、ぶっきら棒に吐き捨てた。留置所で一晩過ごしたのだろうか、彼の額には汚れと脂がうっすら浮かんでいた。
「まずは、お二人の話を聞きましょう」
刑事は男を制し、
「どうぞ、ご遠慮なくおっしゃってください。彼が暴れたりすれば、私が押さえますから。私は小柄ですが、これでも柔道五段ですので」
と、穏やかだけどどこか凄みのきいた声で言った。
「聞き捨てなりませんな。それではまるで犯罪者扱いでしょ。それに、あばら骨が折れて左腕にひびが入っているのに暴れられるわけがない。私の骨を折ったやつを捕まえてほしいくらいだ。あべこべじゃないか」
遥の父親は口元に苦味を走らせる。
「あべこべってどういうことですか? あなたは立派な誘拐犯ですよ」
腹が立った僕は思わず立ち上がった。
「君も落ち着いて。怒鳴りあってもしょうがないから」
刑事は目で坐りなさいと合図する。僕はしぶしぶうなずき、
「遥、話しなよ」
と、遥の肩に手を置きながら坐った。
「きのうはびっくりしました」
遥は震える声で話し始めた。遥が膝のうえで揃えた両手を握りしめるから、僕は彼女の拳にそっと手を重ねた。心の震えなら、僕が受けとめてあげる。
「まさか、むりやりタクシーへ連れこまれたり、あなたが部屋へ押し入ってきたりするとは思いませんでした」
「話をしようと言っただけだ」
遥の父親は怒った。
「聞いてください。そうでなければ、わたしは帰ります」
遥は、勁《つよ》いまなざしで父を見据える。男は一瞬、不安そうな光を目に漂わせ、むっと黙りこんだ。
「とても悲しかったです。わたしの気持ちをほんとうに聞いてくれるのだったら、話をしてもいいかなと思いますけど、あなたは自分の都合を押し通そうとするだけだから、話す気にはとてもなれません。
あなたを訴えるべきかどうか、さんざん悩みました。わたしの考えをいってもあなたは否定するだけでしょうし、大切なゆうちゃんにすごい迷惑をかけてしまったので、もう二度とこんなことをしてもらわないためにも、訴えるべきじゃないかと思いました。たぶん、そうしたほうがいいのでしょう。そうするべきなのでしょう」
遥は、思いつめた表情でじっとうつむいた。遥の頰が紅潮したかと思うと、波が遠退くようにすっと血の気が引く。リップクリームを塗っただけの唇が紫色に蒼ざめる。遥は垂れた髪を指で耳の裏側にしまい、決心したように顔を上げた。
「ですけど、わたしの信じている神さまは汝の隣人を愛せよとおっしゃいました。あなたもわたしの隣人のひとりです。わたしは神さまを裏切りたくはありません。神さまの前では素直な子でいたいと思います。――あなたを許します。ですから、二度とわたしの前に現れないでください。わたしの暮らしを壊さないでください。お願いします」
遥は深々と頭を下げた。長い睫毛から涙がはらはらこぼれ、机の上にせつない水玉模様を描く。遥の父親はほっと息をついて安堵の表情を浮かべたかと思うとたちまち激高し、
「親に向かってなんて言い草だ。お前の神さまなんか知るもんか」
と言い放った。
「親の心、子知らずとは言うけど、親が子供の苦しみを理解してあげないとはねえ」
お地蔵さんはやれやれと掌で額をこすり、
「あなたは情けないと思わないんですか。自分の娘にこんなことを言わせて、恥ずかしいと思わないんですか。私は刑事である前に一人の人間として、一人の父親として呆れますよ。許せないけど、やっぱり実の父親だから許したい。刑務所送りにして苦しめたくない。彼女はそう思っているんですよ。なぜ、それがわからないんでしょうかねえ。自分の娘の苦衷を察してあげようとは思わないんですか。私にはさっぱりわかりません」
と、ぼやくように叱り飛ばすように言った。
「遥の前に現れないと約束してもらえますね」
僕は男に迫った。きちんと言質を取っておきたかった。
「わかったよ。訴えないでおいてもらえるのなら、そうさせていただきます」
男はそっぽを向き、ばかばかしいとでも言いたげに鼻を鳴らす。
「いい加減な答えでは困ります」
「はいはい、お約束いたします。身を粉にして働いて、自分の小遣いを削って養育費を送ってこのざまか。情けない。自分が情けない。娘も情けない」
「いいですか、約束は約束ですからね。あなたが約束を破ったら、すぐにでも訴えることにします」
僕は机を叩いた。男は横を向いたまま答えない。
「私が証人になりましょう。お二人さんはなにかあったら連絡しなさい。私がきちんと処理しますから。――お父さん、妙な真似は許しませんよ」
刑事が助太刀してくれた。
「あなたにお父さんなんて呼ばれる筋合いなんてないんだがね。ま、いいけど」
遥の父親は皮肉に唇をゆがめる。もしかしたら、こんなふうに強がってみせるのが精一杯なのかもしれない。
「遥、行こう。反省の色もないし、これ以上はむだだから。――刑事さん、お忙しいところをどうもありがとうございました」
僕は遥の手を牽いて立ち上がり、彼に一礼した。遥は、蒼ざめた顔で父親を見つめている。男は、いらだたしそうに貧乏ゆすりをしたまま遥の顔を見ようともしない。自分が不当な扱いを受けているとしか思っていないようだ。
ここへ来る前にたぶんこうなるよと言って心の準備をさせておいたのだけど、いざ目の前でそんな態度を取られると、やはりショックを受けたようだ。今度も、遥は父親に裏切られてしまった。傷つけられてしまった。遥の思いとやさしさは通じない。遥と父親の関係はその繰り返しだった。
「いつか、あなたをお父さんと心から呼べる日がくればいいなと思います」
遥の瞳が揺れる。卒業式で泣く女学生のようだ。これで遥は父親から卒業したのだと思いたかった。
「親だったら、なにか答えてやりなさい」
お地蔵さんは遥の父親に言った。男は絶対に口を利くものかときっと唇を結ぶ。僕は遥の背中を軽く叩き、取調べ室を出た。
「ゆうちゃん、あれでよかったのよね」
ふたりは、ひっきりなしに車が流れる国道沿いの歩道を歩いた。車が走る道と人が歩く道を隔てる背の低い常緑樹の植えこみは埃まみれになって汚れている。遥はなんでもないアスファルトの道につまづき、ふらりと体を傾ける。僕は腕を持って支えた。
「あれでいいんだよ。間違ったことはしていないから」
「あの人は、いつかわたしのいったことを理解してくれるかしら」
「わかってくれるといいけどね」
僕はため息をついた。これでは遥があまりにも可哀想だ。
「遥、わかってもらえなくてもともとだし、いつかわかってもらえると信じるしかないよ」
「そうね。信じることね。信じたいな」
遥はまたつまづいた。顔色は蒼いままだ。苦しそうな脂汗が額ににじんでいる。
「タクシーで帰ろうか。疲れただろ」
「歩けるわ。そんなの贅沢よ」
「いいから、タクシー代は僕が出すよ。ちょっと待ってて」
僕は遥の腕を離し、道端へ出て手をあげた。すぐにタクシーがとまり、後部座席の自動ドアが開いた。
「遥、乗るよ」
振り返ると、遥は歩道に体を投げ出して倒れていた。