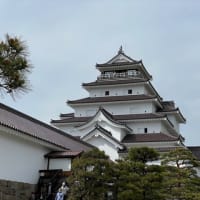穢れた神話
「ゆうちゃん、コンビニで氷を買ってかえろうね」
遥がぽつりと口を開く。
ふたりは夜中の道を歩いていた。警察署から帰るところだった。
階段から転げ落ちた後、僕は遥と巡査に付き添われて救急車で病院へ運ばれた。背中に青痣ができてしまったものの、幸い、打ち身とかすり傷だけの軽傷だった。遥の父親はあばら骨を折り、左腕の骨にひびが入ったそうだ。ざまあみろと言いたいところだけど、それだけの怪我ですんでよかった。いくら横暴な父親とはいえ、死なせたりしたら遥を傷つけてしまう。
手当てを受けてからパトカーに乗って警察署へ行き、薄汚れた壁の小部屋で事情聴取を受けた。
取り調べにあたった年嵩の刑事は、お地蔵さんを思わせるような人間のできあがった人だった。坊主頭になんともいえない温かい雰囲気が漂っている。小柄なお地蔵さんが僕に質問し、僕の答えをまとめてノートパソコンへ打ちこむ。調書が一通りできあがったところで、彼は声に出して読みあげた。
調書の文体は一人称で、彼が書いた文章なのに僕が告白した形になっている。自分に起きたできごとや自分の気持ちを他人が代わりに書くというのは、どうも違和感があるし、不安で落ち着かない。それを朗読されればなおさらだ。心配したとおり、あの男が部屋へ侵入してきた時に怖いと感じたなどと、話していないことも書かれていた。
「これで間違いないですかね?」
刑事は、僕の目をのぞきこむ。
「だいたいいいんですけど、僕は怖いとは思いませんでした。彼女を守らなきゃって必死だったので。むしろ、かっとして頭に血がのぼったような感じでした」
僕は、ちぐはぐなかゆさを隠しきれなかった。
「そうかあ、君は彼女思いなんだ。でも、これがお約束というか、パターンなんだよね」
刑事は人の好さそうな照れ笑いを浮かべ、坊主頭の後ろをかく。そんな彼の姿を見ると、自分の真実にこだわり過ぎるのも考え物かなと思ってしまう。
「そのほうが通りがいいということですか?」
「そんなところなんだけど」
「それじゃ、それでいいです」
調書には調書のスタイルがあって、それにそったほうが仕事がスムーズに流れるのだろう。真実は僕のなかにある。それでいい。
「ところで、あの男のしたことは不法住居侵入といつくかの罪にあたるんだけどね」
お地蔵さんは、調書を目で読み返しながらむずかしい顔をする。
「なんでしょうか?」
「不法住居侵入は親告罪といって、被害者が被害届を提出しないと事件にはできないんだ。暴行はそのまま事件にできるけどね」
「それだけじゃなくて、昼間、彼女を連れ去ろうとまでしたんですよ」
「あの男が悪いことをしたのはわかるよ。ただ、いくら法律上の親子関係はないとはいえ、やはり身内のことだからねえ」
「事件にならないということですか」
遥の父親はこのまま裁きを受けるものだとてっきり思いこんでいた僕は、驚いてしまった。
「もちろん、あなたたちが彼女のお父さんを訴えるというなら、警察は正式に事件として処理するよ。ただし、そうなると関係者にいっせいに事情を聞いてまわるから、彼女自身も、彼女のお父さんも、世間から白い目で見られることになるし、根も葉もない噂が飛び交って苦しい思いをすることにもなるんだ。警察沙汰にするのがいちばんいい解決方法なのかどうか、そのあたりのことも含めてよく考えてみてほしいんだよね」
訴えるのはあまり勧められないという口振りだ。
「ですけど――」
「あなたが怒る気持ちはよくわかるよ。あの男がしたことは言語道断だ。私もけしからんことだと思う。でもね、この仕事をしていると時々似たようなケースに出くわすんだけど、身内同士で警察沙汰にしてしまったがために、よけい不幸になってしまったということも得てしてあるものなんだよ。世間の嫌がらせを受けたり、罪悪感にさいなまれたりしてね。後になって、訴えた本人が自分の親を刑務所送りにしたことを苦にして自殺したことも過去にはあったしねえ」
「わかりました。彼女とよく話し合ってみます」
あの男を懲らしめてやりたいのはやまやまだけど、そこまで言われればこう答えるよりしかたない。もし、遥がこれ以上苦しむようなことがあっても困る。
「そうしてくれないかな。複雑な家庭事情だから、むずかしいところではあるんだけどね。さっきも言ったけど、訴えるなということでは決してないんだよ。それはあなたたちが決めることだから」
刑事は、どうしたものかといった顔をして坊主頭をつるりとなでた。
家に着いたのは、もう午前四時前だった。遥はコンビニで買った氷を氷枕に入れて、僕の背中に当ててくれた。つけたばかりのエアコンが低くうなっている。
「遥のお父さんのことだけど、どうしよう。訴える?」
僕は言った。
「そうね――」
遥は眉をひそませ、口をつぐんでしまう。遥も、お地蔵さんから同じ話を聞いていた。
「ゆうちゃんはどう思う?」
「あんなひどいことをしたんだから、ちゃんとお灸をすえておいたほうがいいと思うんだけど。遥だって、またあんなことをされたらたまらないだろう。むちゃくちゃしたら罰を受けるんだって、わかってもらわないと」
「わたしもあの人を許せない気持ちでいっぱいよ。訴えたいわ。でも、そうしたら、お姉ちゃんが困るかもしれない」
「刑事さんがそう言ってたの?」
「ううん、いってないけど」
「父親が手錠をかけられたら、お嫁にいけなくなるかもしれないね。お姉さんはどうしているの? たしか、地元の専門学校へ進学したんだっけ」
「学校はもう卒業しているはずだわ。今はどうしているか知らないの。わたしが東京へ出てくる時にちょっとだけ会って、それっきりなのよ。姉妹《きょうだい》っていっても、ずっと離ればなれで会うことなんてほとんどなかったし、お姉ちゃんはお姉ちゃんであの家でつらい思いをしていたから、連絡を取りづらいのよ。わたしのせいでお姉ちゃんに迷惑がかかったら、いやだな」
遥は肩を落とした。
「遥のせいじゃないよ。悪いのはお父さんのほうなんだから。遥を誘拐しようとしたり、部屋へ押し入ったり、あんなことはれっきとした犯罪だよ。――ごめん、言いすぎたよ。遥のお父さんを悪く言うつもりはなかったんだ」
「いいのよ。だって悪いことをしたんだもの。――ごめんね。ゆうちゃんに怪我させちゃって」
「これくらいどうってことないよ。遥、お姉さんに電話してみたら。今日のことを話してみて、もしお姉さんが困るって言うのなら、訴えるのはやめにすればいいじゃない。お姉さんに迷惑をかけたくないっていう遥の気持ちはわかるよ。僕は遥の気の済むようにすればいいと思うし、どっちでもいいから」
「電話してみる」
遥はこくりとうなずいた。
翌朝、僕は駅前の商店街へ出かけた。遥が外へ出て携帯電話をかけようとしたのだけど、僕のほうが部屋を出ることにした。
ログハウス風の喫茶店でモーニングを注文し、寝ぼけ眼のまま新聞に目を通した。店にはラフマニノフのピアノ協奏曲第二番が流れていた。
中学生が包丁で父親をめった刺しにした事件が社会面に載っている。記事を読むうちに、背中の痣が疼きだす。不幸な中学生は誰だかわからなくなるほど自分の父親の顔を切り刻んだそうだ。血の通わない興味本位の記事の片隅に評論家の無責任なコメントが載っていた。
僕はふと、昨日の取り調べを思い出した。一人称で書かれた父親殺しの中学生の調書に真実は載っているのだろうか。この記事は真実を伝えているのだろうか。おそらく、真実のいちばん肝心なところは載っていないはずだ。警察の調書も新聞記事も、誰かの言葉を聞き書きしたものに過ぎない。そんなものが真実を伝えられるだろうか。僕の調書に怖いと思ったなどと話してもいないことが書かれていたように、聞き手が理解したいように理解した文章しか載っていないはずだ。真実というものは、その人自身が自分の言葉で語ったものでしか表すことはできない。もちろん、人の心はあやふやなものだから、それだってほんとうに真実を述べているのかどうかといえば、あやしいものだけど。
壊れた家庭に育った子供が親へ抱く気持ちはアンビバレントだ。どんなにひどい親だったとしても、心の底では仲良くしたいという想いが必ずある。それは、まっさらな心で生きていた幼い頃に親から受けた愛情の残像なのかもしれないし、親の存在が心の神話として魂の奥に根を張っているからなのかもしれない。だけど、親への情愛をないがしろにされたり、自分の話を聞いてもらえなかったりすると、汚れた洗濯物がたまるようにわだかまりと諦めが心に積み重なってしまう。わかってほしい期待が強い分だけ、邪険な恨みつらみが心でとぐろを巻いてしまう。
夕べ、遥は姉について話すだけで、自分の父親のことは語らなかった。たぶん、正反対な気持ちが胸の内で綱引きして、言葉にできなかったのだと思う。僕もあえて尋ねなかった。遥はお姉さんのことばかりでなく、その矛盾とも闘っているのだろう。
お姉さんとの話が終わったら携帯のメールをくれることになっていたのだけど、まだこない。僕はもう新聞を読む気にもなれず、遥のことをぼんやり考えた。
中高生の頃から、僕たちはいろんなことを話し合った。楽しい話もたくさんしたけど、悩み事も話した。頭痛の種はいつも自分たちの親のことだった。親のわがままや欠点が見える年頃になったということもあるけど、いちばん厄介なことは、やはり親が家庭の問題を自分たちの手で解決できないどころか、それとまともに向かい合おうとすらしないことだった。
家族というものは彼らが考えているほど簡単なものではないし、子供を取り巻く世間も親が想像しているほど単純なものではない。親は子供に勝手な期待を抱いたり、自分の都合のいいように動くように求めるけど、子供は親のわがままや親自身が満たされなかったことを満足させるための下請けではない。遥の親も、僕の親も、人生にとってほんとうに大切なことはなにかということを忘れている。それが原因のすべてだ。そして、どうしようもない矛盾が遥のような立場の弱い子供に押しつけられてしまう。自分の娘に親を訴えさせるかどうかで悩ませる遥の父親なんて、最低だ。
僕は、ゆで卵の殻とサンドイッチのパン屑が散らばった皿をぼんやり見つめた。お姉さんとうまく話せているのだろうか。泣いたりしていないだろうか。それだけが気がかりだった。
少年ジャンプを見るともなくぱらぱらめくっていると、ようやくメールがきた。僕は勘定をすませ、足早に部屋へ戻った。
(つづく)