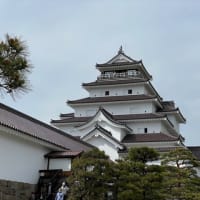作品と作者を切り離して考えてよいと教わった時、とても興奮した。
教授は「従来の文学研究は作家研究であって、かならずしも作品研究にはなっていない。作品は作者から切り離して考えるべき」と主張し、構造主義による文学研究を講義した。
それまで僕は、文学研究というものは作家の人生を調べ、その人生のなかからどのような小説が紡ぎだされたのかを解明するものだとばかり思っていた。たとえば、芥川の生い立ちが作品にどのような影を落としているだとか、太宰と誰それとの心中がどこの作品に描かれているといったことだ。
ファン心理というものがあるので、好きな作家のことはいろいろと知りたくなるものだし、それはそれで面白いのだけど、物足りなさも感じていた。作品の分析が作者の人生にとどまっていて、それ以上の広がりや深みがない。有名作家の人生は調べつくされているから、新しい事実も新しい角度からの見解もなかなか出てこない。
名作と呼ばれる作品には、人類の普遍的なテーマが描かれている。だからこそ、ドストエフスキーやトルストイといった十九世紀ロシアの作家が書いたものを読んでも感動するわけだし、同じ日本でも、漱石や芥川といった明治・大正の作家の作品を読んで共感を覚えもすれば、そこに自分の課題が描かれていると感じ入ったりもするのだ。とりわけ、漱石、芥川、中島敦、太宰といった作家が抱えた孤独感(孤立感)は、解消されるどころか、ますます広がっている。自傷(リストカット)の問題はまさにそうだろう。漱石は『こころ』のなかで、
自由と独立と己れとに充ちた現代に生まれた我々は、その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならないのでしょう
と書いている。この小説で漱石が「現代」と書いたのは大正時代の初め頃だが、二十一世紀の今でも充分通じる。現代的な課題だ。孤独感(孤立感)など感じず「この淋しみ」のない人はリストカットなどしたりしない。漱石が描いた課題は、今でもずっと続いている。「自由と独立と己れ」と「この淋しみ」は普遍的なテーマだ。
ところが、作家研究では、その普遍性に対する分析が甘くなってしまう。触れられていないわけではないが、往々にして通り一遍のものになってしまう。作家という一個人の人生物語にこだわるあまり、大きなものを見逃してしまっているような気がしてならなかった。
物事にはある一定の構造があるのだと教わった。
そして、物語にもある一定の構造がある。
一番解りやすかったのは「父親殺し」のテーマだ。これは文学作品のみならず、さまざまな物語で繰り返し表現される人類の普遍的なテーマの一つだ。
映画『スターウォーズ』には、ルーク・スカイウォーカーとダースベイダー親子の決闘シーンがある。教授がビデオでそのシーンを流した後、これは「父親殺し」のテーマだと解説し、ギリシャ神話の『オイディプス王』からオイディプスコンプレックスと名付けられているものだとも話した。
男は父親を乗り越えることで大人になる。
この課題を端的に表現したものが、オイディプス王の父親殺しなのだとか。
神話には物語の原型があり、神話を解明すれば人間の心に潜むある一定の構造がわかる。なんだか、人類の秘密が解き明かされるようでわくわくした。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』やファーストガンダムの最後のほうでもこのテーマが語られている。「父親殺し」の例をあげれは枚挙に暇がない。
『スターウォーズ』の「敵を倒して姫を獲得する」、逆に言えば「敵を倒さない限り姫を得ることはできない」というストーリーも、よくある物語の構造だ。身近な例で言えば、ゲームの『スーパーマリオブラザーズ』はクッパ大王を倒さなければ姫を獲得できない。『古事記』のスサノオノミコトはヤマタノオロチを退治した後で、大蛇《オロチ》の生贄になるはずだった少女クシナダヒメを獲得する。英雄《ヒーロー》の在り方を示したものと言えるだろう。
神話や物語だけではなく、近代文学にももちろん構造がある。
ドストエフスキーの『悪霊』は、帝政ロシアで実際に起きた社会主義の秘密サークルのリンチ事件を題材にして描いた作品だが、一九七二年の日本赤軍浅間山荘事件でも同様の事態が起きた。地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教でも、同じような事態が発生していたことがわかった。革命を志向する過激な秘密結社では、誰かをスケープゴートにして殺害し、メンバーがその秘密を共有することで結束の強化を図るものらしい。これも構造の一つだ。もっとも、ここまで極端な例でなくとも、秘密を共有することで絆が深めようとするのは日常生活でもよくあることだろう。
漱石の『こころ』は、己の心に地獄を見つけてしまった人間の自己との壮絶な戦いだ。そして、「自由と独立と己れ」という近代的自我を確立するための物語でもある。この作品に描かれているように、近代的自我とは罪の意識、それも全人類に対する罪の意識と人間全般に対する不信感を通じて、それと格闘することによって確立するもののようだ。これも構造の一つだろう。
歴史は繰り返すとよく言うが、物語も繰り返されている。人は時を超えて、民族を越えて、同じ構造の物語を繰り返し語るものらしい。人の心にある一定の構造がある限り、人は同じことを繰り返すのだろう。もう懲りたはずの悲しい過ちさえも。
作品から作者を分離して作品のみを取り上げて研究する構造主義的文学研究は刺激的だった。目を開かされた感じがした。
もっとも、なにぶん難解な用語がたくさん出てくるから、むずかしすぎて僕の頭ではよくわからないことも多かった。だが、作品にひそむ構造を解き明かすことで見えることがいろいろある。構造主義は、ある問題を一個人の枠のなかや、民族の枠のなかや、時代の枠のなかに閉じこめるのではなく、もっとスケールを大きくとって、時空を超えて変わることのない人類の普遍的な課題としてとらえるということだ。文学作品を比較することで構造が浮き彫りになる。構造主義による文学研究は物の見方を教えてくれた。
ただし、構造主義は万能ではない。
構造はただの骨組みに過ぎない。骨組みばかりに目が行き過ぎると、作品に通っている人間の魂や血潮といったものを忘れることになる。いわば、人間を研究するつもりが、人間の骨格ばかり研究するようになってしまう。人間には死ぬまで鼓動し続ける心臓もあれば、体を巡り続ける血もある。見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れるといった五感は骨格には現れない。骨格標本だけを調べても人間のことがわからないように、構造だけを見ていたのでは大切なことを見落としてしまう。
文章の味わい、といったものは構造主義ではとらえることができない。たとえば、「どくとるマンボウ」こと北杜夫先生の詩情やユーモアに溢れた文体を構造主義的に分析しようとしてもむりだ。感覚や感性に属するものを構造主義によって分析するのはかなりむずかしい。たとえ分析したとしてもこじつけになってしまうだろう。文章の味はいわく言いがたいものだが、作家それぞれにそれぞれの文体があってそれが読者を惹きつける。小説の大切な要素であるにもかかわらず分析は困難だ。
プーシキンの文体にはロシア人の心を躍らせる独特のなにかがあるらしい。僕がロシアを旅行した時に出会ったロシア人は、じつに楽しそうに「自由」という詩を朗読した。このことなんだなと僕は感じた。だが、プーシキンを研究して何十年という研究者でも、なぜプーシキンの文体がロシア人の心のつぼを押すのかはわからないそうだ。プーシキンをプーシキンたらしめているものを構造主義では分析することはできない。
分析できないものは文体ばかりではない。
ありとあらゆる構造を究めたとしても、「なぜ生きるのか」「なぜ恋をするのか」「神は存在するのか」「私の魂はどこからきたのか」といった根源的な問いかけには答えてくれない。構造の分析はこういう仕組みになっているということを明かすだけであって、その構造を突き動かす根源的な力までは分析できない。
「なぜ彼女のことが好きなのか?」
と問いかけてみても、その答えは出ない。たとえ、「恋をするのは人間の本能だ。なぜなら、子孫を残そうとする本能に突き動かされているのだから」といった答えが返ってきても、それは問いかけに対する答えにはなっているようでなっていない。
人は誰でも恋をする。
だが、誰にでも恋をするわけではない。
先の骨格と血肉の例えでいえば、「恋は誰でもする」というのは構造にあたり、「なぜ彼女なのか?」というのは、血肉や感覚の問題に当たる。数多《あまた》いる異性のなかで、その人だけを選ぶのだから、なぜ彼女なのか、というのは非常に重要な問題だ。なぜ彼女でなければいけないのか、そこにその人の人生にとって大切なことを解き明かす鍵がある。いささか大袈裟な言い方をすれば、人生の神秘がある。
なぜ、彼女なのか?
なぜ、彼なのか?
だが、この謎は容易には解明できない。
だからこそ、時代や民族を超えて数多くの恋愛小説が執筆され、大勢の人々に読まれるのだろうけど。
さらに、
「私《わたくし》の存在の意味は?」
と問いかけても、なんにも答えてくれない。
構造主義は、この世の仕組みや存在の仕組みを教えてくれても、存在の意味までも明らかにしてくれるものではない。構造主義は機械論だ。世の中を機械仕掛けの時計ととらえている節がある。人間の心やその心が紡ぎだす物語のメカニズムを理解することは大事だが、人間は完全な機械仕掛けではない。機械は意味を問いかけたりはしない。時として、意味を問わずにいられないのが人間だ。もっとも、人生の意味といった根源的な問いかけに対する答えを見つけようとするのは、もはや宗教的な領域になるのだろうけど。
作家は血の通った人間だ。
そして、作品は血の通った人間によって書かれるものだ。
もちろん、読み手である「私《わたくし》」も血の通った人間だ。
構造論だけでは割り切れないものを抱えている。それだけでは解き明かせない魂を持っている。作品を機械仕掛けのもののようにとらえるわけにはいけない。
作家には作品を書くために血反吐を吐くようにして格闘した人生があり、作品はそうした格闘から生まれてきたものだ。そう考えれば、作家の伝記的文学研究を読み、作者の人生や想いを理解してから作品を読み返せば、また違う味わいが出てくる。構造主義は非常に有効な方法だが、作品と作者を完全に分離したままにすることはできない。
要はバランスなのだろう。作品の構造と作家の人となりや人生をバランスよく見ることができれば、つまり、人類の普遍的なテーマとそれに対する作家という一個人の格闘を同時に見ることができれば、もっと深くておいしい小説の読み方ができるのではないだろうか。