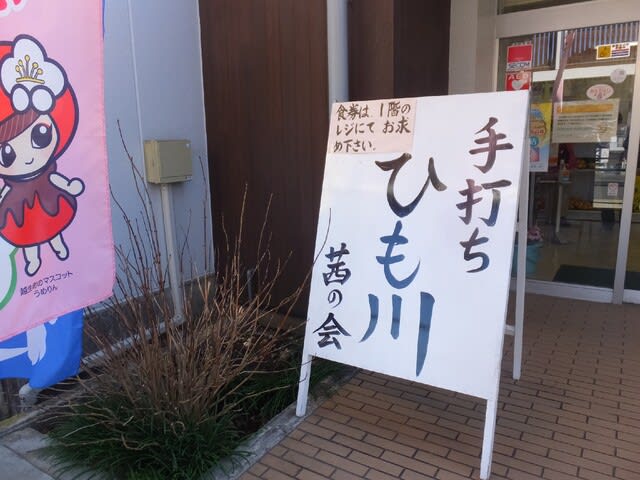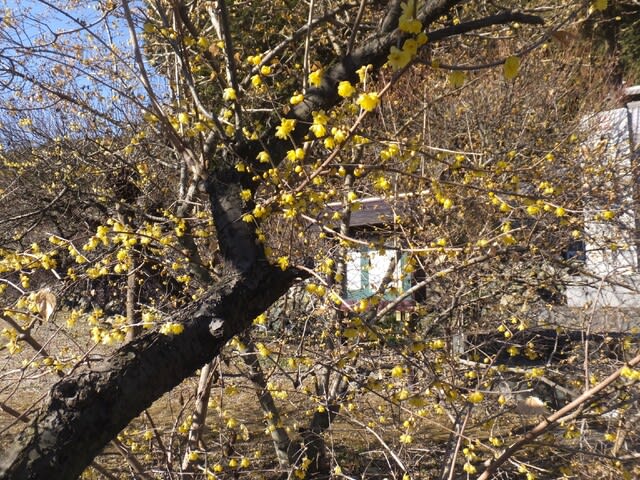5月21日荒川最奥の集落(?)川又を午前10時30分に出発(上の写真位置)。この手の登山には些か遅すぎるスタートなんだけど、兎に角雁坂峠を目指しました。霧雨で視界は良くない。それでも秩父往還雁坂道のまだ雁坂トンネル開通以前、現在の入川橋が出来る前まで使われていた八間橋があった時代のコースを辿りたいと思い、入川橋を渡ってすぐ右の尾根に取りついて、その道型を探しながら行くも所々それらしき道跡はあるものの、ほとんど獣道、あるいは作業道を繋ぎながらの登行と相成ってしまいました。現在の雁坂峠入り口からの道といずれ合流するものと思っていたのに、どうやらその位置より上を歩いていたらしく、途中から古道を探すのは諦めて稜上まで上り詰め、1163mピークからは稜上を辿り1298m地点で正規のコースに合流しました。

荒川が川又で滝川と入川に分岐するその上に架かる入川橋です。

その入川橋から入川に沿って真の沢に向かう道を見下ろす。

入川橋から1163m地点までは杉、ヒノキの植林帯で、それらは冬の間に鹿による食害がひどく、上記の写真のように無残に食い荒らされています。

やはり変人は私以外にもいるようで、所々に赤いテープがつけられていました。そして正規の道に合流するとなんと歩き易い事よ。

1198m地点に出てから初めて出会った標識です。

突出峠からはゆるい登りが続き、樺避難小屋に着いたのが午後3時20分でした。天候は相変わらず霧雨。小屋内には2リットルのペットボトルに水が入っていて、下の水場から汲んできたものです。御自由にお使いくださいとメモがありました。親切な人がいるものです。

午後5時半、やっと雁坂小屋に着きました。7時間の長い登りでした。小屋には若い男女の小屋番が二人いて、主の山中さんは所要で下山中とか。予約も無しでいきなり飛び込んできたジジイにちょっと驚いた様子だったのですが、とても親切にしてくれました。当日の客は私一人。


小屋の内部はこのように昔懐かしい作りです。今はまだ素泊まりのみということなので、夕食はご覧のようにカップラーメンとレトルトのご飯、サンマの缶詰で済ませました。結構おいしく頂きました。就寝午後8時。夜もずっと雨は続いていました。

22日午前4時20分に小屋を出ました。この時期になるともう薄明るくてライトは不要。



雁坂峠には賑やかに看板や標識が立ち並んでいて、一気に娑婆臭くなりました。峠はまだ雲が低く何も見えません。

峠の秩父側と山梨県側とでは全く眺めが違っています。秩父側はあくまでも鬱蒼とした原生林で谷も深く陰鬱さがありますが、山梨県側は反対に熊笹の原が広がり明るい雰囲気です。ただその熊笹はバリカンで刈ったように短く刈り取られています。どうやら冬場の鹿の餌になったようです。

どんどん下って笹が無くなると斜面一帯が落ち葉の絨毯に変わります。新緑の緑と落ち葉の赤の配色が面白いです。

峠沢の流れも美しく、朝まだ早い時間の渓流の音がとても心地ち良く耳に響きます。

上から見た登山道の終了点である沓切沢橋です。立派な車道がここまで上がって来ているので、車で来れば楽なものと思いましたが、途中土砂が道を覆っていたり、大石がゴロゴロ転がっていたりしていて、車は無理でバイクくらいしか通ることはできないです。車道終点にスーパーカブが駐車していました。

白樺の白と新緑の混ざり具合が最高で疲れを忘れさせます。

雁坂トンネルの山梨県側の入り口です。

雁坂トンネルへの国道140号の高架橋を下から見上げます。




午前8時に笛吹小屋キャンプ場に着きました。笛吹小屋は奥秩父の山小屋としては最も古い小屋で、キャンプ場の管理棟は其のころの建物です。とてもレトロで良き時代の面影をそのまま残していています。ここに立ち寄って頼んでおいたコンビニ弁当で朝食を済ませました。ここの管理人さんは私と同じ昭和18年生まれの78歳。昔話に花が咲き1時間も居座ってしまいました。

キャンプ場の向かいが三富道の駅です。雁坂トンネルの手前にあって土日には多くのドライバーたちが立ち寄っています。

さて私は秩父往還歩きでゴールと決めている山梨市駅まで行かなくてはならないので、9時前にキャンプ場を後にしました。広瀬ダム手前に木材を積んだトロッコが置いてありました。昭和43年まで走っていたといいます。私が初めて笛吹川東沢を遡行した時にはまだ走っていました。長い長いトロッコ道歩きのことを今も覚えています。

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/12/aa/1d7edbb250f2644759b2d03d7e2ff218.jpg" border="0">

広瀬ダムに着いた頃には天候はすっかり回復して夏の日差しに変わり、ここからTシャツ一枚になって歩きました。

広瀬の旧道にはこのような道祖神がありました。この後も旧道に入る度にこの形の道祖神を見ました。

天科の旧道から釜口橋を渡って、名所と言われる一の釜に立ち寄りましたが、女滝、雄滝共に西沢渓谷や東沢釜の沢の景観に較べると全然そのスケールが小さくて、寄り道して大事な時間を潰してしまいました。釜口橋の手前に旧川浦小学校があって、笛吹小屋の親父さんは学校の往復にトロッコ道を歩いていたと話していました。

川浦のお伊勢の宮です。街道脇にあって、昔お伊勢参りや三峰神社参拝に、雁坂峠を越えた旅人が後に置いて行ったお地蔵さんが並んでいます。


川浦のバイパス左の一段高い所に口止め番所がありました。これは秩父往還栃本関所と同じく、甲府側の番所で現在の建物は復元されたものです。

川浦口止め番所跡を示す標木が旧道の隅に道祖神と並んで立っていました。

旧道を歩いているとこのような形の屋根を持った家が散見されます。この地域独特の屋根の作りです。


これは湯の平で見た、いのぶた供養塔です。またこのような丸い道祖神や風化した六地蔵などもいくつか目にしました。

上萩原を過ぎたところで道は笛吹川右岸に移り、三富下釜口の民家の木陰で昼飯にしました。笛吹小屋で昼飯として持たせてくれた三角おにぎりと、ミニカップラーメンで不思議とおなか一杯になりました。旧三富小学校の下を通って、三富道の駅手前の神社で一服。このころから太ももや足首、つま先が痛くなり出して休まずにはいられなくなりました。真夏を思わせる空の向こうには越えて来た秩父の山並みが見えていました。

窪平の古い町並みを抜けて武田信玄の菩提寺である恵林寺に着いたのが午後3時20分で、本当はここで恵林寺に寄って行きたかったのですが、時間が気になり素通りしました。荒神山に新しいトンネルが出来ていて、それを横目に見て窪八幡神社で最後の休憩。歴史のある神社ですが、蚊が多くて見物もままならず10分ほど居ただけで立ち去りました。




午後5時に亀甲橋に着いて青梅街道と合流。「差出の碑」を見て万力公園に入ると夕方の散歩を楽しむ人たちが結構歩いていました。園内の鹿公園には鹿がこちらの苦労も知らずのんびり遊んでいました。


最後に根津橋を渡る時北の方を振り返ると、遠くに雁坂嶺や大菩薩の峰々が連なって見えていました。今回のゴールである山梨市駅には午後5時32分に着きました。長い舗装道路歩きで、しかも底の堅い登山靴のために膝や太もも、足首まで痛みが出て、3日経った今でも階段の上り下りに苦労しています。

荒川が川又で滝川と入川に分岐するその上に架かる入川橋です。

その入川橋から入川に沿って真の沢に向かう道を見下ろす。

入川橋から1163m地点までは杉、ヒノキの植林帯で、それらは冬の間に鹿による食害がひどく、上記の写真のように無残に食い荒らされています。

やはり変人は私以外にもいるようで、所々に赤いテープがつけられていました。そして正規の道に合流するとなんと歩き易い事よ。

1198m地点に出てから初めて出会った標識です。

突出峠からはゆるい登りが続き、樺避難小屋に着いたのが午後3時20分でした。天候は相変わらず霧雨。小屋内には2リットルのペットボトルに水が入っていて、下の水場から汲んできたものです。御自由にお使いくださいとメモがありました。親切な人がいるものです。

午後5時半、やっと雁坂小屋に着きました。7時間の長い登りでした。小屋には若い男女の小屋番が二人いて、主の山中さんは所要で下山中とか。予約も無しでいきなり飛び込んできたジジイにちょっと驚いた様子だったのですが、とても親切にしてくれました。当日の客は私一人。


小屋の内部はこのように昔懐かしい作りです。今はまだ素泊まりのみということなので、夕食はご覧のようにカップラーメンとレトルトのご飯、サンマの缶詰で済ませました。結構おいしく頂きました。就寝午後8時。夜もずっと雨は続いていました。

22日午前4時20分に小屋を出ました。この時期になるともう薄明るくてライトは不要。



雁坂峠には賑やかに看板や標識が立ち並んでいて、一気に娑婆臭くなりました。峠はまだ雲が低く何も見えません。

峠の秩父側と山梨県側とでは全く眺めが違っています。秩父側はあくまでも鬱蒼とした原生林で谷も深く陰鬱さがありますが、山梨県側は反対に熊笹の原が広がり明るい雰囲気です。ただその熊笹はバリカンで刈ったように短く刈り取られています。どうやら冬場の鹿の餌になったようです。

どんどん下って笹が無くなると斜面一帯が落ち葉の絨毯に変わります。新緑の緑と落ち葉の赤の配色が面白いです。

峠沢の流れも美しく、朝まだ早い時間の渓流の音がとても心地ち良く耳に響きます。

上から見た登山道の終了点である沓切沢橋です。立派な車道がここまで上がって来ているので、車で来れば楽なものと思いましたが、途中土砂が道を覆っていたり、大石がゴロゴロ転がっていたりしていて、車は無理でバイクくらいしか通ることはできないです。車道終点にスーパーカブが駐車していました。

白樺の白と新緑の混ざり具合が最高で疲れを忘れさせます。

雁坂トンネルの山梨県側の入り口です。

雁坂トンネルへの国道140号の高架橋を下から見上げます。




午前8時に笛吹小屋キャンプ場に着きました。笛吹小屋は奥秩父の山小屋としては最も古い小屋で、キャンプ場の管理棟は其のころの建物です。とてもレトロで良き時代の面影をそのまま残していています。ここに立ち寄って頼んでおいたコンビニ弁当で朝食を済ませました。ここの管理人さんは私と同じ昭和18年生まれの78歳。昔話に花が咲き1時間も居座ってしまいました。

キャンプ場の向かいが三富道の駅です。雁坂トンネルの手前にあって土日には多くのドライバーたちが立ち寄っています。

さて私は秩父往還歩きでゴールと決めている山梨市駅まで行かなくてはならないので、9時前にキャンプ場を後にしました。広瀬ダム手前に木材を積んだトロッコが置いてありました。昭和43年まで走っていたといいます。私が初めて笛吹川東沢を遡行した時にはまだ走っていました。長い長いトロッコ道歩きのことを今も覚えています。

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/12/aa/1d7edbb250f2644759b2d03d7e2ff218.jpg" border="0">

広瀬ダムに着いた頃には天候はすっかり回復して夏の日差しに変わり、ここからTシャツ一枚になって歩きました。

広瀬の旧道にはこのような道祖神がありました。この後も旧道に入る度にこの形の道祖神を見ました。

天科の旧道から釜口橋を渡って、名所と言われる一の釜に立ち寄りましたが、女滝、雄滝共に西沢渓谷や東沢釜の沢の景観に較べると全然そのスケールが小さくて、寄り道して大事な時間を潰してしまいました。釜口橋の手前に旧川浦小学校があって、笛吹小屋の親父さんは学校の往復にトロッコ道を歩いていたと話していました。

川浦のお伊勢の宮です。街道脇にあって、昔お伊勢参りや三峰神社参拝に、雁坂峠を越えた旅人が後に置いて行ったお地蔵さんが並んでいます。


川浦のバイパス左の一段高い所に口止め番所がありました。これは秩父往還栃本関所と同じく、甲府側の番所で現在の建物は復元されたものです。

川浦口止め番所跡を示す標木が旧道の隅に道祖神と並んで立っていました。

旧道を歩いているとこのような形の屋根を持った家が散見されます。この地域独特の屋根の作りです。


これは湯の平で見た、いのぶた供養塔です。またこのような丸い道祖神や風化した六地蔵などもいくつか目にしました。

上萩原を過ぎたところで道は笛吹川右岸に移り、三富下釜口の民家の木陰で昼飯にしました。笛吹小屋で昼飯として持たせてくれた三角おにぎりと、ミニカップラーメンで不思議とおなか一杯になりました。旧三富小学校の下を通って、三富道の駅手前の神社で一服。このころから太ももや足首、つま先が痛くなり出して休まずにはいられなくなりました。真夏を思わせる空の向こうには越えて来た秩父の山並みが見えていました。

窪平の古い町並みを抜けて武田信玄の菩提寺である恵林寺に着いたのが午後3時20分で、本当はここで恵林寺に寄って行きたかったのですが、時間が気になり素通りしました。荒神山に新しいトンネルが出来ていて、それを横目に見て窪八幡神社で最後の休憩。歴史のある神社ですが、蚊が多くて見物もままならず10分ほど居ただけで立ち去りました。




午後5時に亀甲橋に着いて青梅街道と合流。「差出の碑」を見て万力公園に入ると夕方の散歩を楽しむ人たちが結構歩いていました。園内の鹿公園には鹿がこちらの苦労も知らずのんびり遊んでいました。


最後に根津橋を渡る時北の方を振り返ると、遠くに雁坂嶺や大菩薩の峰々が連なって見えていました。今回のゴールである山梨市駅には午後5時32分に着きました。長い舗装道路歩きで、しかも底の堅い登山靴のために膝や太もも、足首まで痛みが出て、3日経った今でも階段の上り下りに苦労しています。