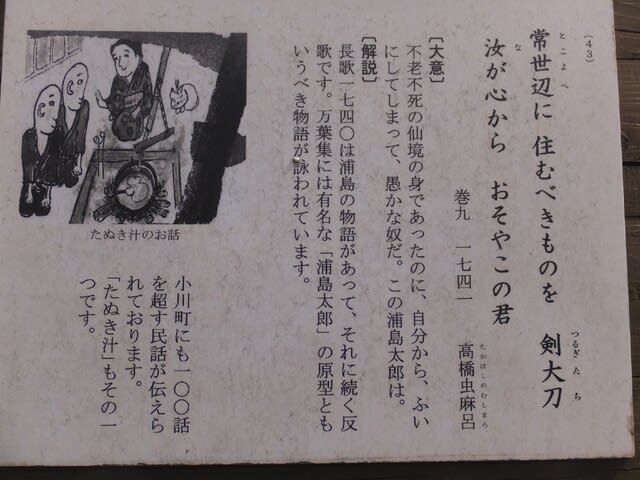一昨年春に新宿御苑前からスタートした旧青梅街道歩きは、秋に小菅まで到達以来ずっと休止状態でした。今年3月以来膝の痛みが酷くなり、小さな山は愚かウォーキングすらままならず、せいぜい朝夕の犬の散歩が精一杯の毎日でした。
最近いくらか具合も良くなり、中断していた青梅街道歩きを再開せねばと、内心不安を抱えながらこの3連休を利用して16日の午後から家を出て奥多摩駅に向かいました。奥多摩駅に午後5時過ぎに着き、5分ほど歩いた先の民宿和尚にお世話になりました。
宿は日原川に架かる氷川大橋からも見える奥の白い建物です。

奥多摩駅を午前7時25分のバスに乗って小菅村役場で下車。ここでバスを降りたのは私一人だけ。駅から乗った人たちはみんな深山橋までで降りてしまいました。役場前に人影はなし。ただ一人役場前のベンチで準備をして午前8時半スタートしました。

少し行けば右に丹波山村への分岐です。一昨年秋にこの道を歩いて丹波山村まで行き、のめこい湯に入って帰りました。

もうここは秋の気配。彼岸花が満開です。

白糸の滝までの道はずっと緩やかな登りが続き、歩き易い道ですが単調で飽きがきます。バイクの若者が数人先へ行きましたが、何をしに行くのだろうと不思議に思いましたが、彼らは途中にあった通行止めの看板が目に入ってなかったようです。案の定引き返して
帰って行きました。白糸の滝駐車場の先で道は塞がれていて車は通れません。

右の崖が崩落して修復工事が行われていますが、現在大きな石は取り除かれて、崖にはネットが張られています。人の通行には支障ありませんが、実際は人も通行は禁止ということになっています。休日には作業をする人はいませんから、自己責任ということで私は通り抜けました。

白糸の滝にちょい寄りしました。結構な落差があり垂直に落下する滝はなかなか見事です。

最近ここを訪れる人が少ないと見えて、小菅川に架かるアーチ橋には落ち葉が乗って滑りやすくなっていました。おまけに熊に注意などと看板もあっては少々ビビッてしまいます。

林道が左にカーブしている所の橋の手前の大菩薩峠入り口に11時少し前に到着。峠への道はこの林道を更に行った先からもありますが、私は手前の白糸の滝登山口から登り始めました。登り出してすぐに下山してくる中年女性二人組と出会いました。今日初めて出会う登山者です。こちらへ降りてくる人で、しかも女性とは珍しいなと思いました。



登山道とはいえ古くから人馬が登降した峠道なので、今も良く整備されていて緩い登りの歩き易い道です。良く手入れされた杉、ヒノキの森が続き、残暑厳しいこの時期も涼しい木陰を提供してくれています。

この峠道で唯一楽に水が手に入る、小さな流れに丁度12時に着きました。もうこの先水は手に入らないのでここで補給しておきました。この先1時間ほど登った所で、今回2回目の下山中の登山者に会いました。結構お年を召した方二人で私を見て、峠を越えてから初めて人に会ったと喜んでいました。そして心配そうに崩落個所は通れるのかと聞かれたので、大丈夫ですと答えたらすっかり安心した様子でした。

道々沢山の栃の実が落ちていました。熊の好物と聞いているので、もしかして近くに熊が潜んでいるのかもと、周囲を気にしながら歩きました。栃の実は山間部の人たちは近年まで食べていたものです。私も若いころ飛騨の山で山小屋暮らしをしていたころ、用足しに麓に降りると栃餅を良く食べました。結構美味かったことを覚えています。

重荷を背負った牛馬が少しでも楽が出来るよう、平坦な道造りが行われた証拠に今も苔むした石垣が健在です。


丹波山村からの道が合流する、フルコンバの手前に通行止めの札が下がっています。白糸の滝近くの崩落地が危険だと書いてあります。だけど私は通って来ました。確信犯です。フルコンバは明るい尾根上で、丁度良い所にベンチもあって休憩にはもってこいの場所です。ここからは峠まで緩やかな登りが続きますが、疲れから峠まで嫌に長く感じました。


午後4時丁度に大菩薩峠に到着。随分長い時間かかりましたが、私自身は良く登って来れたと満足気分でした。峠の小屋に泊まる人たちでしょうか、のんびりと風景を楽しんでいました。小屋で15ケ入ったマスカットを買っているとき、この小屋に泊まる客でしょうか、3人の女性が店先で小屋の主人に、「ここには何でこんなに石がゴロゴロしているの」と聞いているので、思わず笑ってしまいました。そこで主人が一生懸命説明をしておりました。


峠を越えて甲州側に出ると植生がガラリと変わり、斜面を覆う笹原とダケカンバの明るい山様に気分も明るくなりました。何んといっても大菩薩峠は西側から登るのが普通。道は広く歩き易いし傾斜も緩い。子供でも登れるファミリー向きのコースなんだから。

懐かしい福ちゃん荘の前を通過。私の子供が小さかったころ、ここまで車で上がって来て峠経由で大菩薩嶺に登りました。現在小屋の周りはキャンプをする人が多く、沢山のテントがありました。

午後5時10分に今夜の泊りとなる上日川峠のロッヂ長兵衛に着きました。足の不調とトレーニング不足で、やっとやっとの峠越でした。しかし良くここまで登って来れたもんだと、自分自身の頑張りにちょいと感動です。ロッヂは大きな丸太を組み上げた立派なログハウスです。風呂もあって2階の客室内には大きなベッドが二つ。夕食は豪華、松茸まで出ました。トイレが一階の奥にしかなくて、膝痛の足で階段の登降はきついです。やっぱりトイレは2階にも欲しいです。

18日朝食を終えて午前7時にロッヂを出ました。何んとか塩山駅まで無事に歩けるように、祈る気持ちで登山道に足を踏み入れました。上日川峠から裂石までは立派な自動車道もありますが、私は昔からの登山道を下りました。膝痛には下りが大変なので、なだらかな自動車道を歩くべきなのですが、ここは年は取っても山ヤの意地で山道を選びました。

昔から大変な数の人や牛馬が往来した道なので、道は完全にV字型の大きな溝になってしまっており、雨でも降ったらとても歩けないだろうと気になりました。右上を見れば峠へ向かう車列が木々の間から見えるのです。ロッヂを出てから1時間と50分かけてやっと千石茶屋の前まで降りてきました。これで今日の最悪部分は終了で、この後は普通の道を塩山まで歩くだけです。

千石茶屋から10分で丸川峠分岐に着きました。こちらから大菩薩嶺に向かう人も結構いると見えて、車が沢山並んでいます。

裂石の手前,雲峰寺入り口で持参のスニーカーに履き替えました。底の堅い登山靴で舗装路を長く歩くのは膝に悪いです。履き替えて歩き始めたらなんと、膝への当たりも殆どなく、重い靴を引きずって歩いて来たことが馬鹿みたいに思えました。
大菩薩峠への石の道しるべの所で、私は411号国道(柳沢峠と塩山を結ぶ現在の青梅街道)へは出ずに、この位置から直接塩山駅に向かう一葉の道(県道201号)と呼ばれている道を選びました。国道は車が多く疲れるから嫌です。

一葉の道は最初の部分が少し登りになりますが、それを越せば後は塩山市街を目がけてただ一直線に下って行くだけです。道幅も広く車の往来も殆どないという、もったいないと思うほどの道です。ただ標高が下がるにつれて強烈な太陽に照らされるので、その熱気には些か疲れました。


塩山駅北口に向かうのに、町の中で道を間違えて余計な遠回りをしてしまいました。それでも午後1時35分には無事に着くことが出来て、二年越しの目的を達成できました。青梅街道は塩山が終わりではなく、石和温泉の先,酒折が終点なのであと一回塩山まで来る必要があります。それは今年の内に済ませることが出来るでしょう。
最近いくらか具合も良くなり、中断していた青梅街道歩きを再開せねばと、内心不安を抱えながらこの3連休を利用して16日の午後から家を出て奥多摩駅に向かいました。奥多摩駅に午後5時過ぎに着き、5分ほど歩いた先の民宿和尚にお世話になりました。
宿は日原川に架かる氷川大橋からも見える奥の白い建物です。

奥多摩駅を午前7時25分のバスに乗って小菅村役場で下車。ここでバスを降りたのは私一人だけ。駅から乗った人たちはみんな深山橋までで降りてしまいました。役場前に人影はなし。ただ一人役場前のベンチで準備をして午前8時半スタートしました。

少し行けば右に丹波山村への分岐です。一昨年秋にこの道を歩いて丹波山村まで行き、のめこい湯に入って帰りました。

もうここは秋の気配。彼岸花が満開です。

白糸の滝までの道はずっと緩やかな登りが続き、歩き易い道ですが単調で飽きがきます。バイクの若者が数人先へ行きましたが、何をしに行くのだろうと不思議に思いましたが、彼らは途中にあった通行止めの看板が目に入ってなかったようです。案の定引き返して
帰って行きました。白糸の滝駐車場の先で道は塞がれていて車は通れません。

右の崖が崩落して修復工事が行われていますが、現在大きな石は取り除かれて、崖にはネットが張られています。人の通行には支障ありませんが、実際は人も通行は禁止ということになっています。休日には作業をする人はいませんから、自己責任ということで私は通り抜けました。

白糸の滝にちょい寄りしました。結構な落差があり垂直に落下する滝はなかなか見事です。

最近ここを訪れる人が少ないと見えて、小菅川に架かるアーチ橋には落ち葉が乗って滑りやすくなっていました。おまけに熊に注意などと看板もあっては少々ビビッてしまいます。

林道が左にカーブしている所の橋の手前の大菩薩峠入り口に11時少し前に到着。峠への道はこの林道を更に行った先からもありますが、私は手前の白糸の滝登山口から登り始めました。登り出してすぐに下山してくる中年女性二人組と出会いました。今日初めて出会う登山者です。こちらへ降りてくる人で、しかも女性とは珍しいなと思いました。



登山道とはいえ古くから人馬が登降した峠道なので、今も良く整備されていて緩い登りの歩き易い道です。良く手入れされた杉、ヒノキの森が続き、残暑厳しいこの時期も涼しい木陰を提供してくれています。

この峠道で唯一楽に水が手に入る、小さな流れに丁度12時に着きました。もうこの先水は手に入らないのでここで補給しておきました。この先1時間ほど登った所で、今回2回目の下山中の登山者に会いました。結構お年を召した方二人で私を見て、峠を越えてから初めて人に会ったと喜んでいました。そして心配そうに崩落個所は通れるのかと聞かれたので、大丈夫ですと答えたらすっかり安心した様子でした。

道々沢山の栃の実が落ちていました。熊の好物と聞いているので、もしかして近くに熊が潜んでいるのかもと、周囲を気にしながら歩きました。栃の実は山間部の人たちは近年まで食べていたものです。私も若いころ飛騨の山で山小屋暮らしをしていたころ、用足しに麓に降りると栃餅を良く食べました。結構美味かったことを覚えています。

重荷を背負った牛馬が少しでも楽が出来るよう、平坦な道造りが行われた証拠に今も苔むした石垣が健在です。


丹波山村からの道が合流する、フルコンバの手前に通行止めの札が下がっています。白糸の滝近くの崩落地が危険だと書いてあります。だけど私は通って来ました。確信犯です。フルコンバは明るい尾根上で、丁度良い所にベンチもあって休憩にはもってこいの場所です。ここからは峠まで緩やかな登りが続きますが、疲れから峠まで嫌に長く感じました。


午後4時丁度に大菩薩峠に到着。随分長い時間かかりましたが、私自身は良く登って来れたと満足気分でした。峠の小屋に泊まる人たちでしょうか、のんびりと風景を楽しんでいました。小屋で15ケ入ったマスカットを買っているとき、この小屋に泊まる客でしょうか、3人の女性が店先で小屋の主人に、「ここには何でこんなに石がゴロゴロしているの」と聞いているので、思わず笑ってしまいました。そこで主人が一生懸命説明をしておりました。


峠を越えて甲州側に出ると植生がガラリと変わり、斜面を覆う笹原とダケカンバの明るい山様に気分も明るくなりました。何んといっても大菩薩峠は西側から登るのが普通。道は広く歩き易いし傾斜も緩い。子供でも登れるファミリー向きのコースなんだから。

懐かしい福ちゃん荘の前を通過。私の子供が小さかったころ、ここまで車で上がって来て峠経由で大菩薩嶺に登りました。現在小屋の周りはキャンプをする人が多く、沢山のテントがありました。

午後5時10分に今夜の泊りとなる上日川峠のロッヂ長兵衛に着きました。足の不調とトレーニング不足で、やっとやっとの峠越でした。しかし良くここまで登って来れたもんだと、自分自身の頑張りにちょいと感動です。ロッヂは大きな丸太を組み上げた立派なログハウスです。風呂もあって2階の客室内には大きなベッドが二つ。夕食は豪華、松茸まで出ました。トイレが一階の奥にしかなくて、膝痛の足で階段の登降はきついです。やっぱりトイレは2階にも欲しいです。

18日朝食を終えて午前7時にロッヂを出ました。何んとか塩山駅まで無事に歩けるように、祈る気持ちで登山道に足を踏み入れました。上日川峠から裂石までは立派な自動車道もありますが、私は昔からの登山道を下りました。膝痛には下りが大変なので、なだらかな自動車道を歩くべきなのですが、ここは年は取っても山ヤの意地で山道を選びました。

昔から大変な数の人や牛馬が往来した道なので、道は完全にV字型の大きな溝になってしまっており、雨でも降ったらとても歩けないだろうと気になりました。右上を見れば峠へ向かう車列が木々の間から見えるのです。ロッヂを出てから1時間と50分かけてやっと千石茶屋の前まで降りてきました。これで今日の最悪部分は終了で、この後は普通の道を塩山まで歩くだけです。

千石茶屋から10分で丸川峠分岐に着きました。こちらから大菩薩嶺に向かう人も結構いると見えて、車が沢山並んでいます。

裂石の手前,雲峰寺入り口で持参のスニーカーに履き替えました。底の堅い登山靴で舗装路を長く歩くのは膝に悪いです。履き替えて歩き始めたらなんと、膝への当たりも殆どなく、重い靴を引きずって歩いて来たことが馬鹿みたいに思えました。
大菩薩峠への石の道しるべの所で、私は411号国道(柳沢峠と塩山を結ぶ現在の青梅街道)へは出ずに、この位置から直接塩山駅に向かう一葉の道(県道201号)と呼ばれている道を選びました。国道は車が多く疲れるから嫌です。

一葉の道は最初の部分が少し登りになりますが、それを越せば後は塩山市街を目がけてただ一直線に下って行くだけです。道幅も広く車の往来も殆どないという、もったいないと思うほどの道です。ただ標高が下がるにつれて強烈な太陽に照らされるので、その熱気には些か疲れました。


塩山駅北口に向かうのに、町の中で道を間違えて余計な遠回りをしてしまいました。それでも午後1時35分には無事に着くことが出来て、二年越しの目的を達成できました。青梅街道は塩山が終わりではなく、石和温泉の先,酒折が終点なのであと一回塩山まで来る必要があります。それは今年の内に済ませることが出来るでしょう。