とう人も思ひ絶えたる山里の
さびしさなくばすみ憂からまし
『~特に右(上の歌のこと)の歌は西行の孤独感の深さを歌ったもので、この山里の庵に自分を訪ねてくる人もいないと観念しきった孤独な境界にあっては、さびしさこそが慰めであって、そのさびしさがなかったらここも住み憂いことであろうというのです。
兼好法師も「徒然草」で[まぎるる方なく、ただひとりあるのみぞよき]といっていますが、こういう深く人生を生きた人たちが向き合ったさびしさ、無常観には現代に生きる我々にはとても思い及ばない醒めきった凄みを感じます。』
『』内は元首相の細川護熙氏の言葉である。
この西行の歌と細川氏の解説は、ずいぶん前に発行された平凡社の「別冊太陽」に載っているものだ。
この本には作家も含めてほかにも名だたる人々の解説が載っているが、そのどれもほとんど僕の心に残っていないにもかかわらず、この細川氏の解説だけは楔のようにしっかりと今でも僕の胸に刻まれている。それほどまでに鋭い…と思った。
とくに「こういう深く人生を生きた人たちが向き合ったさびしさ、無常観には現代に生きる我々にはとても思い及ばない醒めきった凄みを感じます。」という部分は、「人生」というものを真に知悉した人でなければ書けない言葉であろう。
いや、実は僕が初めてこの西行の歌と解説を読んだときには感じ取れなかったものを、今の僕は感じている。
つまり、初めて書店でこの雑誌を手に取った時から、今までの何年という時間が経過する間に、僕自身の立ち位置も変わった、ということだろうと思う。
以前の僕はこの言葉の上を上滑りして読んでいただけだった。
しかし今は…この細川氏のいう「西行の凄み」というものが、僕の心眼に〈見える〉気がする。
僕はある芸術を違うジャンルの芸術と比べてみることがよくあるのだが、この歌を音楽でいうならバッハの The art of fuge フーガの技法を思い浮かべる。
グールドがバッハの作品の中でも白眉であるといった作品だ。
いや、もっとわかりやすい対比はやはり小津安二郎の作品かもしれない。
あのどこにでもあるホームドラマのなかにそれとなくつつみこんだ「醒めきった凄み」…
いずれにしても、今改めてこの歌と細川氏の解説を読んでみて、僕は日本の和歌というものの、いや西行の芸術のもつ「深度」のあなどりがたさを見せつけられたような気がする。
さびしさなくばすみ憂からまし
『~特に右(上の歌のこと)の歌は西行の孤独感の深さを歌ったもので、この山里の庵に自分を訪ねてくる人もいないと観念しきった孤独な境界にあっては、さびしさこそが慰めであって、そのさびしさがなかったらここも住み憂いことであろうというのです。
兼好法師も「徒然草」で[まぎるる方なく、ただひとりあるのみぞよき]といっていますが、こういう深く人生を生きた人たちが向き合ったさびしさ、無常観には現代に生きる我々にはとても思い及ばない醒めきった凄みを感じます。』
『』内は元首相の細川護熙氏の言葉である。
この西行の歌と細川氏の解説は、ずいぶん前に発行された平凡社の「別冊太陽」に載っているものだ。
この本には作家も含めてほかにも名だたる人々の解説が載っているが、そのどれもほとんど僕の心に残っていないにもかかわらず、この細川氏の解説だけは楔のようにしっかりと今でも僕の胸に刻まれている。それほどまでに鋭い…と思った。
とくに「こういう深く人生を生きた人たちが向き合ったさびしさ、無常観には現代に生きる我々にはとても思い及ばない醒めきった凄みを感じます。」という部分は、「人生」というものを真に知悉した人でなければ書けない言葉であろう。
いや、実は僕が初めてこの西行の歌と解説を読んだときには感じ取れなかったものを、今の僕は感じている。
つまり、初めて書店でこの雑誌を手に取った時から、今までの何年という時間が経過する間に、僕自身の立ち位置も変わった、ということだろうと思う。
以前の僕はこの言葉の上を上滑りして読んでいただけだった。
しかし今は…この細川氏のいう「西行の凄み」というものが、僕の心眼に〈見える〉気がする。
僕はある芸術を違うジャンルの芸術と比べてみることがよくあるのだが、この歌を音楽でいうならバッハの The art of fuge フーガの技法を思い浮かべる。
グールドがバッハの作品の中でも白眉であるといった作品だ。
いや、もっとわかりやすい対比はやはり小津安二郎の作品かもしれない。
あのどこにでもあるホームドラマのなかにそれとなくつつみこんだ「醒めきった凄み」…
いずれにしても、今改めてこの歌と細川氏の解説を読んでみて、僕は日本の和歌というものの、いや西行の芸術のもつ「深度」のあなどりがたさを見せつけられたような気がする。










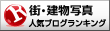

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます