
湯島聖堂
大昔だが鴎外のある文章が目に留まりそれについてその当時メールで交流していた人に送ったことがある。
それからしばらくはそのこと自体を忘れていたのだが、よほどふかく自分に刻まれたのだろう、あれからたぶん20年近い歳月がたつというのに、昨今ふたたび深い水底からゆっくりと浮かび上がるように思い出されてきている。
『近頃井上通泰、熊沢蕃山の伝を校正上本せしを見るに、蕃山の詞(ことば)に、敬義を以てする時は髪を梳(くしけづ)り手を洗うも善をなす也。
然らざる時は九たび諸侯を合すとも徒為のみと有之候。
蕃山ほどの大事業ある人にして此言始めて加味なるべしと雖(いえども)、即是先日申上候道の論を一言にて申候者と存候。
朝より暮れまで為す事一々大事業と心得るは、即一廉(ひとかど)の人物といふものと存候。遇々(たまたま)感じ候故序に申上候。』
(小金井きみ子宛書簡 森鴎外 永遠の希求 佐々木雄爾 p335)
敬義ということばを僕なりに捉えると「尊敬、敬意あるいはまごころ」とでもなるだろうか、そういう感じの意味だろう。
敬意、まごころをもってするときはたとえそれが髪を梳るとき、手を洗うときのような日常の些事であっても、善をなしていることになる、もしそのような心なしに大事をなしても何の意味もない、というようなことを蕃山は言っている。
鴎外はこの手紙の中で、これは「道」というものを一言で語っている言葉だと述べている。朝から晩までなすことすべてを大事業と思いながらするという者は、「一廉(ひとかど)の人物」だと。
僕は蕃山の原文はもちろん読んだことはないが、鴎外はその原文に接しこの蕃山の言葉に深い感銘を受けたのだろうと思う。一廉の人物というのは鴎外にとって最高度の褒め言葉だろう。
それにしても、もう20年近くも前に読んだことばをたとえその時感じるものがあったとはいえ、なぜいまごろ思い出されてくるのか正直わからない。
僕などは言葉という者の持つ影響力を普段かなり過小評価してきたように思う。この鴎外の手紙の一文はこの長い歳月の間僕の中の深くまで沈んでいき、その間ずっとそこで生きていた…としか言いようがない。
ようやくこの言葉の本当の価値というものをあじわえる状況になり、それがふたたび目に見えるところに浮かび上がってきたように思える。
「即是先日申上候道の論を一言にて申候者と存候」先日申上げました『道』についての私の考えを一言で述べたものと存じます、という鴎外のこの表現からは蕃山に対する並々ならぬ敬意が浮き出ている。
「敬義を以てする時は髪を梳り手をあらふも善をなす也」
鴎外とは関係ないのだが、禅僧の道元が留学のため中国に入港した船の中で待機している時、中国のあるお寺で修行している老僧がたまたま日本から積んできた椎茸を買いに入船してきた。道元はその老僧が修行中のお寺で炊事係をしていると知って驚き、なぜあなたのようなご住職の経験もある年長の僧侶がそのようなことをしているのですかと聞いたという。するとその僧は大きく笑い、あなたはまだ仏道修行というものがわかっていない、それが禅というものだ、と答えたという話をどこかで読んだことがある。
道元がこの話をずっと覚えていて後年どこかに書いたかあるいは誰かに話したということは、そうとうこの出来事に感じるものがあったのだろう。彼は後年「修行」というものの本質をこの名もない老僧から教えてもらったと述懐している。このはなしなども、鴎外の云う「道」と一脈通じるものがあるように思う。
まぁ、いずれにしても、最近とみに頭から離れないことなので書いてみることにした。
じつはこの鴎外の文章を探すためほかにも彼の文章をいろいろと読んでいる間に、鴎外の文章の持つ独特の味わいというものにたまたま触れることになった。そうしているうちに実はこれに関して昔読んだ三島由紀夫の鴎外の文章に対する評論というか感想というか、そういうものが浮かんできて、あぁ、あのとき三島が言っていたことはこういうことを言っていたのかといまさらながら感じた。
この文章の引用元である佐々木氏の序文の冒頭に次のようなものがある。
『鴎外の文章を読んでいると、簡素でしかも風格のある座敷に一人安座している時のような、閑雅な気分に誘われる』
というものがあり、まさにこの感覚、ここにすべてが尽くされているといってもいいとさえおもった。三島はもとより、永井荷風などの文人たちがまるで神のようにあがめた鴎外の文章。まるで骨董品屋の倉庫の奥のほうで塵をかぶっていた貴重な宝を見せてもらったような、そんな気持ちでいま読んでいる。










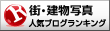
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます