多くの人にとって老後の最大の心配はお金だが、先々どうなるかは誰にも分からない。もし、長生きしすぎて一文無しになったら、知人や周りの人にたかるが、どうにもならないと「野垂れ死にを覚悟するしかない」と言う。そして、死ぬまで働くことを勧める。お金にならなくても、何か人の役に立つことをする。
老人になると孤独は避けられない。だから、老人の仕事は「孤独に耐えること。そして、孤独だけがもたらす時間の中で自分を発見する」こと。「孤独と絶望こそ、人生の最後に充分味わうべき境地」で、その究極を体験しないと「たぶん人間として完成しない」。そうやって自分の人生を再編集するために、老後の時間はあるのだろう。
「」内の文章だけが曽野綾子の言葉です。「老いの才覚」 曽野綾子
曽野綾子の文章は10代の中ごろからよく読んだ覚えがある。
あのころ、ちょうど僕の中で「善」「悪」という問題が大きなウェイトを占め始めていて、自然、キリスト教作家であるこの人の作品にひかれていった。
ある時期まで来ると、この人の文章から、なにか一段高いところから読者を見下ろすような雰囲気、臭いを感じ始めてきて、少しづつはなれていったのを覚えている。
それは宗教というものをバックグランドに持つ作家だからなのかとも思ったが、同じキリスト教作家である遠藤周作の作品を読んだときはそのようなにおいはみじんも感じなかった。
やはり、そういうもの(宗教的バックグランド)とは無縁のところからきているのだろうと僕は感じる。
だが、そうはいっても、この人の文章は今読んでも、おもわず首肯せざるを得ないような、なにか洞察の鋭さ精確さを持っているような気がする。
とくに『「孤独と絶望こそ人生の最後に充分味わうべき境地」で、その究極を体験しないと「たぶん人間として完成しない」。そうやって自分の人生を再編集するために、老後の時間はあるのだろう。』
という言葉は、深くしみこんでくる。
それにしてもこの「味わう」という言葉遣いの中に、なんとも言えない滋味がにじみ出ている。
そう、ここにはなにがしかの肯定感がある。
「晩年になったら、人生にイエスと言えるようにならなければならない」
といったのは、敬愛する作家ヘルマン・ヘッセだった。
この言葉は裏を返せば、何千かい、何万回、No!と叫んできたことのあかしでもあるだろう。
彼のような理想主義者であれば当然のこと。しかし、そんな彼でさえ、最後は人生にイエスと言えるようにならなければならない、といった。
その背景にはやはり、神、そういうのが不適切であれば、この宇宙を作ったエネルギーとでも言えるだろうか、自分もその中の一部である以上、それを包み込んでいる「全体」を否定したまま死んではいけない、ということなのかもしれない。それは何となれば、自分自身を否定することと同じことだから。
この世のありとあらゆるもの、清濁、美醜、善悪、正邪、条理不条理、すべてをありのままで「よし」としなければならない。
創造主の前では、否定すべきものなど何もないのだから。
よって、二元論的な対立構造でみる段階の「向こう側」に行かなければならないということ…ではないか
と、ここまで書いてきたとき、やはりどうしてもレンブラントの最晩年の自画像が目に浮かんでしまう。
そのNoからYesへ至るまでの過程を経験できるのが、「老年期の孤独」なのではないか。
僕は最近そんな風に考えている。

老人になると孤独は避けられない。だから、老人の仕事は「孤独に耐えること。そして、孤独だけがもたらす時間の中で自分を発見する」こと。「孤独と絶望こそ、人生の最後に充分味わうべき境地」で、その究極を体験しないと「たぶん人間として完成しない」。そうやって自分の人生を再編集するために、老後の時間はあるのだろう。
「」内の文章だけが曽野綾子の言葉です。「老いの才覚」 曽野綾子
曽野綾子の文章は10代の中ごろからよく読んだ覚えがある。
あのころ、ちょうど僕の中で「善」「悪」という問題が大きなウェイトを占め始めていて、自然、キリスト教作家であるこの人の作品にひかれていった。
ある時期まで来ると、この人の文章から、なにか一段高いところから読者を見下ろすような雰囲気、臭いを感じ始めてきて、少しづつはなれていったのを覚えている。
それは宗教というものをバックグランドに持つ作家だからなのかとも思ったが、同じキリスト教作家である遠藤周作の作品を読んだときはそのようなにおいはみじんも感じなかった。
やはり、そういうもの(宗教的バックグランド)とは無縁のところからきているのだろうと僕は感じる。
だが、そうはいっても、この人の文章は今読んでも、おもわず首肯せざるを得ないような、なにか洞察の鋭さ精確さを持っているような気がする。
とくに『「孤独と絶望こそ人生の最後に充分味わうべき境地」で、その究極を体験しないと「たぶん人間として完成しない」。そうやって自分の人生を再編集するために、老後の時間はあるのだろう。』
という言葉は、深くしみこんでくる。
それにしてもこの「味わう」という言葉遣いの中に、なんとも言えない滋味がにじみ出ている。
そう、ここにはなにがしかの肯定感がある。
「晩年になったら、人生にイエスと言えるようにならなければならない」
といったのは、敬愛する作家ヘルマン・ヘッセだった。
この言葉は裏を返せば、何千かい、何万回、No!と叫んできたことのあかしでもあるだろう。
彼のような理想主義者であれば当然のこと。しかし、そんな彼でさえ、最後は人生にイエスと言えるようにならなければならない、といった。
その背景にはやはり、神、そういうのが不適切であれば、この宇宙を作ったエネルギーとでも言えるだろうか、自分もその中の一部である以上、それを包み込んでいる「全体」を否定したまま死んではいけない、ということなのかもしれない。それは何となれば、自分自身を否定することと同じことだから。
この世のありとあらゆるもの、清濁、美醜、善悪、正邪、条理不条理、すべてをありのままで「よし」としなければならない。
創造主の前では、否定すべきものなど何もないのだから。
よって、二元論的な対立構造でみる段階の「向こう側」に行かなければならないということ…ではないか
と、ここまで書いてきたとき、やはりどうしてもレンブラントの最晩年の自画像が目に浮かんでしまう。
そのNoからYesへ至るまでの過程を経験できるのが、「老年期の孤独」なのではないか。
僕は最近そんな風に考えている。











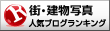
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます