
東京のお茶の水にある東京復活大聖堂(通称 ニコライ堂)に行ってきた。
この聖堂は昔から知っていていつかはいきたいと思っていたのだが、念願かなって何日か前に行く機会を得た。
なぜ行きたかったかというと、この教会は正教会(ギリシャ正教ともいわれる)の教会だからだ。
キリスト教系の教会ではいろんな教会を訪れたことがあるぼくも、正教会の教会にはいまだ行ったことがなかったから。
入り口を入ろうとすると、ちょうどお葬式が終わったばかりの日本人の信者さんたちが何人か集団で出てきた。お葬式だというのはそのいでたちでわかった。
ぼくはそれをみてちょっと新鮮な感じがした。というのも、正教会というのはギリシャや主に東欧のキリスト教というイメージが強くて、その信者に日本人がいること自体が僕の頭の中にはなかった。
でもここに立派に正教会の聖堂があり、その布教の歴史が明治にまでさかのぼるのだから、日本人の信者がいても全然不思議ではないのだ。
それにしても、あなたの信仰する宗教は何ですか?と問われて、日本人が正教会です、と答えるのはかっこいい!と思う僕はミーハーなのだろうか(笑)
さてそれはともかく、今日ようやく谷崎の「陰翳礼賛」を読み終えた。
読んだ今感じることは、谷崎のものの感じ方の繊細さとその美意識の高さ(深さ)である。そして、これがいわゆる日本で昔から言われている「数寄者」「風流人」とか言われる人なのだろうなと思った。
早速、その一部を載せてみたい。
(前略)「わらんじゃ」(谷崎が食事をした京都の料理屋)の座敷と云うのは四畳半ぐらいの子じんまりした茶席であって、床柱や天井なども黒光りに光っているから、行燈式の電灯でも勿論暗い感じがする。が、それを一層暗い燭台に改めて、その穂のゆらゆらとまたたく蔭にある膳や椀を見詰めていると、それらの塗り物の沼のような深さと厚みを持ったつやが、全く今までとは違った魅力を帯び出してくるのを発見する。
そして我々の祖先が漆という塗料を見出し、それを塗った器物の色沢に愛着を覚えたことの偶然ではないのを知るのである。
中略~茶事とか、儀式とかの場合でなければ、膳と吸い物椀の外は殆ど陶器ばかりを用い、漆器というと、野暮くさい、雅味のないものにされてしまっているが、それは一つには、採光や照明の設備がもたらした「明るさ」のせいではないであろうか。事実、「闇」を条件に入れなければ漆器の美しさは考えられないと云っていい。
今日では白漆と云うようなものも出来たけれども、昔からある漆器の肌は、黒か、茶か、赤であって、それは幾重もの「闇」が堆積した色であり、周囲を包む暗黒の中から必然的に生れ出たもののように思える。
派手な蒔絵などを施したピカピカ光る蝋塗りの手箱とか、文台とか、棚とかを見ると、いかにもけばけばしくて落ち着きがなく、俗悪にさえ思えることがあるけれども、もしそれらの器物を取り囲む空白を真っ黒な闇で塗り潰し、太陽や電灯の光線に代えるに一点の燈明か蝋燭のあかりにして見給え、、忽ちそのけばけばしいものが底深く沈んで、渋い、重々しいものになるであろう。
古(いにしえ)の工芸家がそれらの器に漆を塗り、蒔絵を画く時は、必ずそう云う暗い部屋を頭に置き、乏しい光の中における効果を狙ったのに違いなく、金色を贅沢に使ったりしたのも、それが闇に浮かび出る具合や、燈火を反射する加減を考慮したものと察せられる。
つまり金蒔絵は明るいところで一度にぱっとその全体を見るものではなく、暗いところでいろいろの部分がときどき少しずつ底光りするのを見るように出来ているのであって、豪華絢爛な模様の大半を闇に隠してしまっているのが、云い知れぬ余情を催すのである。
そして、あのピカピカに光る肌のつやも、暗いところに置いてみると、それがともし火の穂のゆらめきを映し、静かな部屋にもおりおり風のおとずれのあることを教えて、そぞろに人を瞑想に誘い込む。
もしあの陰鬱な室内に漆器と云うものがなかったなら、蝋燭や燈明の醸し出す怪しい光の夢の世界が、その灯のはためきが打っている夜の脈搏が、どんなに魅力を減殺されることであろう。
まことにそれは、畳の上に幾すじもの小川が流れ、池水が湛(たた)えられている如く、一つの灯影を此処彼処(ここかしこ)に捉えて、細く、かそけく、ちらちらと伝えながら、夜そのものに蒔絵をしたような綾を織りだす。
~中略~私は、吸い物椀を手に持った時の、掌が受ける汁の重みの感覚と、生あたたかい温味(ぬくみ)とをなにより好む。それは生まれたての赤ん坊のぷよぷよした肉体を支えたような感じでもある。
~中略~漆器の椀のいいことは、まずその蓋を取って、、口に持っていくまでの間、暗い奥深い底のほうに、容器の色と殆ど違わない液体が音もなく澱(よど)んでいるのを眺めた瞬間の気持ちである。
人は、その椀の中の闇に何があるかを見分けることはできないが、汁がゆるやかに動揺するのを手の上に感じ、椀の縁がほんのり汗を掻(か)いているので、そこから湯気が立ち昇りつつあるのを知り、その湯気が運ぶ匂(におい)によって口にふくむ前にぼんやり味わいを予覚する。その瞬間の心持、スープを浅い白ちゃけた皿に入れて出す西洋流に比べて何という相違か。それは一種の神秘であり、禅味であるとも云えなくはない。
ここまで写してきて本当に疲れた(笑)
だが、どうしても谷崎の見出したこの稀有な、そしてもう今ではほぼ失われてしまった、世界を共有してもらいたい一途で書いた。
今こうして読み返してみて感じるのは、非常に貧弱な表現で申し訳ないが、非常にいい文章だなということである。
いいという言葉には、ちょっと言葉にはできないぐらいの思いが込められている。
巧緻、繊細、匠、名工の技、技巧の極致……とでもいおうか……
とくに「古(いにしえ)の工芸家がそれらの器に漆を塗り…」からはじまり「細く、かそけく、ちらちらと伝えながら、夜そのものに蒔絵をしたような綾を織り出す。」までに至る一文は、絶品といっていい。
今この文章を読みながら、自分は日本人でよかったと思った。
もし日本語を母国語としない人間だったら、絶対この文章の味わいを堪能することはできないだろうからだ。
むかし、たしかドナルド・キーンだったと思うが、彼がシェイクスピアの文章を読んだとき、しみじみ自分は英語を母国語とする人間でよかったと思ったとおっしゃった。
要は、どれほど英語に堪能な人であったとしても、そのひとが英語を母国語としない人であれば、絶対にあの名文の『本当の味わい』を感じとることはできないからだ、ということを言いたかったのだろう。
たしかに僕はシェイクスピアの作品の偉大さは理解できても、僕の英語力が『仮に』どれ程優れていたとしても、その文章そのものが持つ「真のあじわい」をネイティブと同じほどには感じ取れないだろう。
しかし、逆もまた然りであり、幸いにも日本にも優れた作家、名文家は存在している。そして、ドナルド・キーンがどれ程優れた日本語能力を持っていたとしても、僕と同じほどにはそれらの味わいを感じ取れないだろう、ということもまた事実であろうと思う。
そのことは川端康成もノーベル賞受賞時のインタビューで、『こと文学作品に関する限り』人間がどうしてもこえられない言語というもののもつ壁であり、厳密にいえば、文学作品の翻訳というものは不可能である、というようなことをおっしゃっていた。かほどさように繊細かつ微妙なものである。
話は少しそれてしまったが、もう一つ書き添えるとすると、谷崎の文章というのはなにか視覚的な感じがする。
彼の文章を読んでいると、その文章の展開にそってまるで映画の映像がスクリーンの中で流れるように動的に見えるような気がするのだ。
これはひとえに彼の優れた描写力によるものだろうか、それとも彼の文章そのものが持つ独特の味わいなのだろうか……











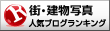
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます