
年たけてまた越ゆべしと思ひきや
命なりけりさやの中山
この歌は西行が東大寺再建の砂金を勧進する目的で東北へと旅立った時、難所で有名な掛川の小夜の中山を通過するときに読んだものだ。
このとき西行は69歳。彼は30代の時も同じ場所を通っている。
40年近い年月が流れて、また難所といわれるこの場所に来た、あぁ、俺は生きているんだ…と思い、その年月の間に体験したことが走馬灯のように彼の心中で駆け巡っている、そういう刹那に詠んだ歌だろうと思う。
この「命なりけり」という言葉に彼の全感慨がこもっている。
生きてきたんだなぁ、という思いと同時に、そう思っていられるのは今だけであり、明日もこの世にとどまっているという保証はない世界、そういう世界に彼は、そして僕らも生きている、そして、目の前に広がっている山河、これらも含めて全体が「命なり」という感慨。
しかし、この「命なりけり」はうまい。
当時の東北への旅といえば、今に喩えれば、さしずめアフリカかアマゾンの奥地へいくぐらいのものだったのではないか。
ようは生きて帰ってこれるという保証はない旅であった。
そこへ寿命がこの当時なら40~50歳ぐらいといわれていたころ、69歳でそういうところに入っていったのだ……
「死」というものが観念ではなく、それこそオブラート1枚先には存在している、そういう覚悟で旅を続けていたことだろう。
そのことはこの時代から数百年を経た芭蕉の時代でもほぼ変わりなく、彼のかいたものを読んでいると、明らかに死の覚悟というものが根底にあるのがわかる。
昨日は恒例の湯河原へ行き、先祖に思いを伝えてきた。
ここからの相模湾の眺めが素晴らしく、僕は例年晴れの日を選んでいっている。
そして丘の上からの眺めを見ながら、また年を越せた、とおもう。
それにしても西行や芭蕉をあのような旅に突き動かしていたものは何だったのだろう。
西行の公的な動機の一つは勧進のため、芭蕉は…創作のためか…
でも僕はおもう、彼らの旅は「死」にかぎりなく近づいていく旅ではあっても、まさにそれだからにこそ「生」に再び出会う旅だったのではないか。
そのためには死に限りなく近づいていく必要があったのではないだろうか。
死に極限まで近づいて初めて見えてくるもの、そう、芥川の云った「末期の眼」でものを見るために。
そうして見えてくるものは、生への執着か、それともそれを超えた世界か、現世への諦念か、それとも、現世全体への愛か
しかし、芥川は自裁することでかえって死から逃げた…ともいえる、それに対して、西行や芭蕉は死に向かって一歩一歩歩いていき、死の中に入っていった、いや、生死が織りなすえもいわれぬ綾の中に入っていきそれを見きっていった










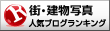
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます