2019年6月11日(火)
「ご当地お魚図鑑めぐり」 第17回は茨城県。

利根川という大きな淡水域、霞ケ浦という多様な汽水域と用水路
そして黒潮と親潮のぶつかる豊かな漁場となる太平洋に接する県。
そりゃ、当然のことながら魚種も豊富になるよね。
『茨城の淡水魚』(レイモン・アザディ著 筑波書林 1983年)
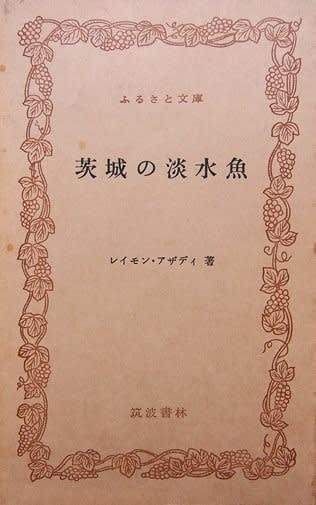
100ページ足らずの薄い文庫本なのに、124種もの魚種が紹介されてる。
もちろん周縁魚まで包括した淡水魚について1種ずつ解説。
茨城での方言にもページを割き、詳しく記録してるし
生息流域となる河川や湖沼を網羅しておられるので、記録の緻密さ正確さを強く感じる。
すごい本だよ。
ケド、著者のレイモン・アザディさんがどんな人かわからない。
ネット検索しても出てこない。
茨城の水生植物の本も出されてるみたいだし
文章もとても上手いので、長く茨城に暮らされ、水産関連に携わったのかな?
『平成調査 新・霞ケ浦の魚たち』(荻原富司・熊谷正裕編 (社)霞ケ浦市民協会 2007年)

オールカラーで画像もきれいだし、詳しいし、いろんなコラムも読みやすい。
特に、絶滅種の記録と多様な外来種を抱えた状況説明がいい。
とってもいい図鑑だなあ。
茨城県にとどまらず、近隣の県の人たちには是非購入をお勧め。
ま、後々編者の熊谷さんは
日本全国にわたるタナゴ釣り関連の名著を出されてて
元々関東地方中心だったタナゴ釣りを全国展開のブームの火種になっちゃった。
これらの本もとてもいいケド、ちょっぴり悪用されちゃった感もする。
『茨城の海の生き物』(茨城新聞社編 茨城新聞社 1985年)

茨城大学卒の4人の研究者さんが、分野別に執筆されてる。
あまり興味の湧かない藻類や植物をとばして読もうとしても
「潮上帯の生き物たち」などと、生息環境別に生き物をまとめてるので
苦手な藻類や植物もついつい見てしまうという優れものの図鑑。
そうなんだよな。
1つの生態系に暮らす生き物をある程度把握しておかなきゃいけないんだよね。
魚やエビ・カニだけ追ってても
環境激変なんかのときに気付かなかったり、対応できなかったりするもんな。
分厚いし、オールカラーだし、大きな画像なのもいい。
解説も短いので読みやすい。
比較的安価だしね。
手元にあるのはこの3冊だケド、茨城県関連はもっと出版されてるんだろうな。
もしご存知の方がおられればお教えくだされば幸いです。
やるね! 茨城県!
「ご当地お魚図鑑めぐり」 第17回は茨城県。

利根川という大きな淡水域、霞ケ浦という多様な汽水域と用水路
そして黒潮と親潮のぶつかる豊かな漁場となる太平洋に接する県。
そりゃ、当然のことながら魚種も豊富になるよね。
『茨城の淡水魚』(レイモン・アザディ著 筑波書林 1983年)
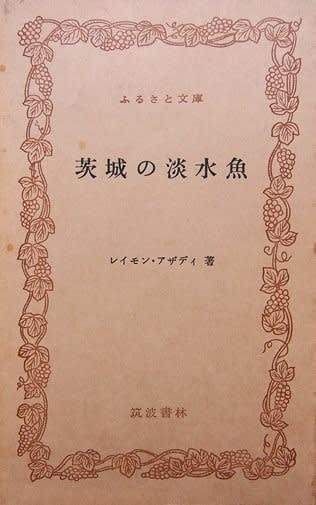
100ページ足らずの薄い文庫本なのに、124種もの魚種が紹介されてる。
もちろん周縁魚まで包括した淡水魚について1種ずつ解説。
茨城での方言にもページを割き、詳しく記録してるし
生息流域となる河川や湖沼を網羅しておられるので、記録の緻密さ正確さを強く感じる。
すごい本だよ。
ケド、著者のレイモン・アザディさんがどんな人かわからない。
ネット検索しても出てこない。
茨城の水生植物の本も出されてるみたいだし
文章もとても上手いので、長く茨城に暮らされ、水産関連に携わったのかな?
『平成調査 新・霞ケ浦の魚たち』(荻原富司・熊谷正裕編 (社)霞ケ浦市民協会 2007年)

オールカラーで画像もきれいだし、詳しいし、いろんなコラムも読みやすい。
特に、絶滅種の記録と多様な外来種を抱えた状況説明がいい。
とってもいい図鑑だなあ。
茨城県にとどまらず、近隣の県の人たちには是非購入をお勧め。
ま、後々編者の熊谷さんは
日本全国にわたるタナゴ釣り関連の名著を出されてて
元々関東地方中心だったタナゴ釣りを全国展開のブームの火種になっちゃった。
これらの本もとてもいいケド、ちょっぴり悪用されちゃった感もする。
『茨城の海の生き物』(茨城新聞社編 茨城新聞社 1985年)

茨城大学卒の4人の研究者さんが、分野別に執筆されてる。
あまり興味の湧かない藻類や植物をとばして読もうとしても
「潮上帯の生き物たち」などと、生息環境別に生き物をまとめてるので
苦手な藻類や植物もついつい見てしまうという優れものの図鑑。
そうなんだよな。
1つの生態系に暮らす生き物をある程度把握しておかなきゃいけないんだよね。
魚やエビ・カニだけ追ってても
環境激変なんかのときに気付かなかったり、対応できなかったりするもんな。
分厚いし、オールカラーだし、大きな画像なのもいい。
解説も短いので読みやすい。
比較的安価だしね。
手元にあるのはこの3冊だケド、茨城県関連はもっと出版されてるんだろうな。
もしご存知の方がおられればお教えくだされば幸いです。
やるね! 茨城県!













































