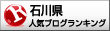時は、元禄16年(1703年)春。
所は、上方の大都会・大坂(※当時「坂」)。
遊郭「天満屋」に、器量よしと評判の遊女がいた。
名前は「初(はつ)」。
どんな客にも分け隔てなく愛想を振りまく彼女には、将来を誓った相手がいた。
その男、馴染みの「徳兵衛(とくべえ)」は、醤油屋で丁稚(でっち)から手代(てだい)、
--- 例えるなら---アルバイトの身分から部課長クラスになった苦労人。
イケメンで誠実ながら、お人好しでやや気が弱いところがあった。
ある日、偶然2人は神社の境内で居合わせる。
娘らしく喜ぶ「お初」に対し、どこか浮かない顔の「徳兵衛」。
それもそのはず。
彼は叔父である醤油屋の主人から、望まない結婚をゴリ押しされていた。
もちろん断りを入れたが、継母に渡した持参金の返済を迫られる。
やっとのことで取り戻したものの、
金に困っているという親友「九平次(くへいじ)」に懇願され転貸。
ところが期限が過ぎても、未だ返してくれない。
そこまで語り終えたところで、仲間を連れた「九平次」がやって来た。
当然食ってかかるも、友と信じていた男は白を切り、
詐欺師呼ばわりした挙句、袋叩きに。
公衆の面前で、また恋人の目の前で醜態をさらし「徳兵衛」の面目は丸つぶれ。
身も心も打ちのめされ、魂のどん底にあえぐ彼は、ある決心をするのだった。
その夜、天満屋。
男の身を案じ気を揉む「お初」のところへ、こっそり「徳兵衛」が訪ねてくる。
折悪しく、客として「九平次」まで来訪。
慌てて「徳兵衛」を打掛で隠し、死角になる縁の下へ引き入れる「お初」。
昼の一件について「徳兵衛」を罵倒する「九平次」。
拳を握り歯がみする「徳兵衛」。
「お初」は怒りに震える男を足先で制しこう言い放った。
『徳様は、胸の内を明かし合った大切な人。
自分の甘さから身の破滅を招いてしまいましたが、
潔白を示す証拠がないのでは、仕方がない。
かくなる上は、死んで身の証を立て、恥をそそぐ他ない。
覚悟を聞けたなら、私も一緒に---。』
「徳兵衛」は、裾から伸びた女の真白な足を自らの喉笛にあて、死ぬ覚悟を伝えた。
この世のなごり 夜もなごり
死にに行く身を喩えれば 墓地へとつづく道の霜
一足づつに消えゆくそれは 夢で見る夢のように儚い
夜明け前の七ツ時 六つ響いた鐘の音
残るひとつがこの世との 別れの鐘の聴き納め
されど心中穏やか 迷いなくためらいもなし
輝く星の下、2人が手に手を取って向かったのは曾根崎・天神の森。
互いを松の木に縛り、「徳兵衛」は脇差で「お初」を一突き。
独りで逝かせてはならないと、返す刀で自らの喉をかき切り、
揃って黄泉の国へと旅立ったのである。
ほんの手すさび 手慰み。
不定期イラスト連載 第百九十八弾「曾根崎心中~お初と徳兵衛」。

「曾根崎心中」は、実際の心中事件がモデル。
発生から僅か一ヶ月後、騒動が世間の耳目を集める中、
人形浄瑠璃(文楽)として初演された。
観客にとって身近な市井の義理人情・悲哀を取り上げた出し物は、
センセーショナルを巻き起こし、文字通りの大ヒットを記録。
そのブームは劇場の中だけに収まらず、社会へ溢れ出した。
来世で愛が結ばれることを誓うカップルの心中が多発。
お上から上演禁止を命じられるほどの過熱ぶりだったという。
しかし、一度起こった文化の潮流は押しとどめられることはなかった。
それまでは“時代物”と呼ばれる、武士や貴族を主人公にした英雄譚が主だったが、
これを機に“世話物”と呼ばれる、町人にスポットを当てた現代劇が確立してゆく。
つまり、人形浄瑠璃の歴史は「曾根崎以前と以後」に分類されるほどの
エポックメイキングでもあるのだ。
作者は「近松門左衛門(ちかまつ・もんざえもん)」。
江戸前期、上方で花開いた町人文化を代表する人物のひとりだ。
このあたりの時代背景については、過去投稿の拙文を引用したい。
<元禄期(1688~1703年)は、開幕以降続いた内乱が落ち着き、徳川体制が固まった頃。
国内開発に力が注がれ、人口が急増、農業・漁業、商工業が発達。
後に「元禄バブル」と呼ばれる経済成長を背景に、富を得た豪農や豪商が現れ、
パトロンとなって文化振興に資金を投じた。
中心となったのは「上方(かみがた)」。
開発途上のお江戸に比べ“千年の都”京都や“天下の台所”大坂は、
経済、気運が充実。
先進的で自由な都市型町人文化が形成されてゆく。
華やかな装飾画・蒔絵・作陶などの工芸分野で、後世に残る傑作が生まれた。
木版印刷による浮世絵が生まれ、アートを楽しむ裾野が拡大。
ファッション分野では、友禅染が発明。
花鳥風月などを多彩に表現できるようになり、バリエーションが広がった。
節分・花見・月見・節句などの年中行事が浸透し、イベントが盛んに。
歌舞伎・(人形)浄瑠璃といったエンターテイメントも定着。
--- 何かと上り調子なのだ。>
そんな時代の流れに乗って元禄文化の寵児となった「近松」。
しかし、先回投稿に書いた通り、彼は元々町人の出自ではない。
越前・吉江藩士の次男坊として生を享けたが、改易以降、仕官の機会に恵まれず、
浪人となった父に連れられ京都へ移住。
刀を置いて芝居の世界へ飛び込んでいった。
およそ半世紀の作家生活を送った「近松門左衛門」。
彼の筆による人形浄瑠璃・歌舞伎狂言は、計160作あまり。
その多くが「虚実皮膜(きょじつひまく/ひにく)」の妙を旨としている。
<芸といふものは実と虚との皮膜の間にあるものなり。
虚にして虚にあらず、実にして実にあらず、この間に慰みがあつたものなり。>
登場人物の名前や史実はそのまま用い、そこに脚色を施す。
虚構と現実、フィクションとリアルを、
絶妙な配分で混ぜ合わせることでお客は満足を得る。
その言葉は、エンターテインメントの真髄を射抜いている気がするのだ。