生命維持に必要不可欠ではないことに時間と労力を費やし、
そこに「価値」や「意味」を見出す生き物は、人間だけかもしれない。
たとえば「芸術」。
絵画も、書も、写真も、映画も、演劇も、文芸も陶芸も、音楽も、
空腹を満たしてはくれない。
しかし、人間は、物質だけでなく、精神的に満たされることを求める。
つまりは「心の飢餓」を解消するために、有ってしかるべきなのだと思う。
今日は、そうした、人ならではの欲求の発露を拝観してきた。


きのう(2021/11/05)から「第17回 津幡美術作家協会展」がスタート。
会場の津幡町文化会館シグナスには、
日本画、洋画、工芸(刀工)、書、写真、70点余りの作品が展示してある。
力作揃いの中、つい興味は絵画に向く。
題材を選び、構想・構図を練り、画材を手に試行錯誤。
それは「生みの苦しみ」かもしれないし「至福の時間」でもある。
好みはそれぞれだが、僕は手仕事の結実に惹かれるのだ。
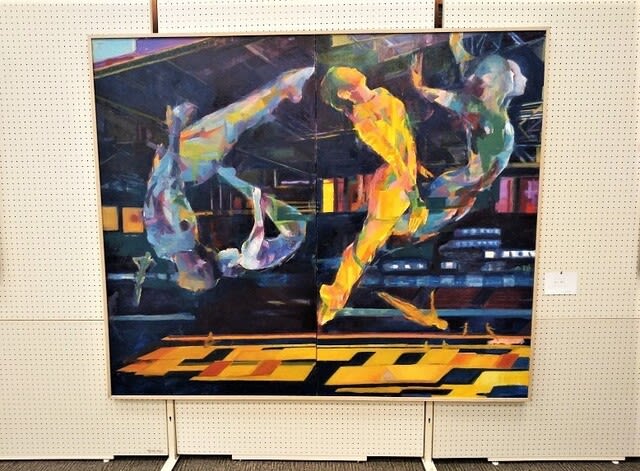
紀元前から人は「絵」に親しんできた。
ビジュアルで何かを伝える手段に於いて、絵画は高い地位にあった。
19世紀、写真の登場によって事態は変化する。
“画家に描いてもらうより早いくて安い”と、
風景画や肖像画のジャンルは深刻な打撃を受けたという。
しかし、絵画は写真によって「写実という呪縛」から解放されたとも言える。

さて、今投稿のタイトルは、英語の慣用句だ。
正確には---
「Man cannot live by bread alone,
but on every word that comes from the mouth of God」
「人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出る言葉によって生きる」
---となる。
「モーセ」が発し「イエス」に受け継がれた有名なフレーズ。
素直に受けとれば「神の言葉(存在)はパンを超越している」となるだろうが、
これが記載された聖書を読み込んでいない僕は、勝手にこう解釈している。
「人は糧を得てこそ、神の言葉に耳を傾け生きがいを見い出す」
日本人の感性には「衣食足りて礼節を知る」に近いだろうか。
何にせよお腹のふくれない芸術を楽しめるのは、まあまあ幸せな証だ。
「第17回 津幡美術作家協会展」は、11月10日(水)まで開催。
期間中各日午前9:00~午後5:00(最終日は午後4:00)。
もちろん、写真も書も工芸も見応え充分。
入場無料。
時間と都合が許せば足を運んでみてはいかがだろうか。





























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます