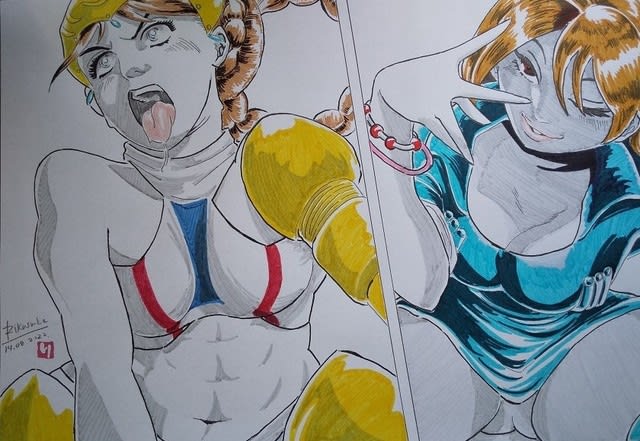先日、富山県の南西端にある南砺市・五箇山(なんとし・ごかやま)へ出かけた。
わが津幡町から下道でも1時間半あまりのドライブ。
左程、遠くはない山間に「世界遺産」がある。


目的地は、9戸の「合掌造り家屋」が残る「菅沼(すがぬま)合掌造り集落」。
平成7年(1995年)、
岐阜県・白川郷(しらかわごう)、五箇山・相倉(あいのくら)と共に、
ユネスコの世界文化遺産に登録された。

周辺の山林、庄川も含めた地域は美しい佇まい。
なるほど、日本の心象風景だ。
一歩足を踏み入れたら、
遙か150年あまり昔へタイムスリップしたかのような錯覚を味わえる。

江戸末期~明治初期に建てた家屋は、今も人が住む一般住宅。
実に合理的にできている。
屋根の傾斜角度は「60度」。
急こう配の理由は、湿った雪の重みに耐える共に、
雪を滑り落としやすくするため。
「対豪雪」の備えである。

素材は「茅(かや)」。
茅葺屋根の吹替えは、およそ30年毎。
作業には「結(ゆい)」と呼ばれる地域共同体から、
200人あまりが従事するという。

各家屋と対角線に設置された放水銃。
「幸い、未だ活躍したことはない」
--- と土産物屋のオバちゃんから聞き、
僕が胸を撫で下ろしたのはいうまでもない。
わが津幡町から下道でも1時間半あまりのドライブ。
左程、遠くはない山間に「世界遺産」がある。


目的地は、9戸の「合掌造り家屋」が残る「菅沼(すがぬま)合掌造り集落」。
平成7年(1995年)、
岐阜県・白川郷(しらかわごう)、五箇山・相倉(あいのくら)と共に、
ユネスコの世界文化遺産に登録された。

周辺の山林、庄川も含めた地域は美しい佇まい。
なるほど、日本の心象風景だ。
一歩足を踏み入れたら、
遙か150年あまり昔へタイムスリップしたかのような錯覚を味わえる。

江戸末期~明治初期に建てた家屋は、今も人が住む一般住宅。
実に合理的にできている。
屋根の傾斜角度は「60度」。
急こう配の理由は、湿った雪の重みに耐える共に、
雪を滑り落としやすくするため。
「対豪雪」の備えである。

素材は「茅(かや)」。
茅葺屋根の吹替えは、およそ30年毎。
作業には「結(ゆい)」と呼ばれる地域共同体から、
200人あまりが従事するという。

各家屋と対角線に設置された放水銃。
「幸い、未だ活躍したことはない」
--- と土産物屋のオバちゃんから聞き、
僕が胸を撫で下ろしたのはいうまでもない。